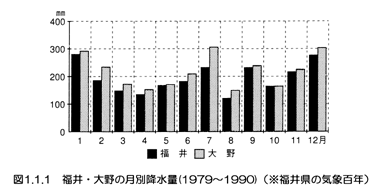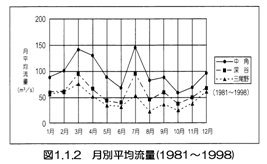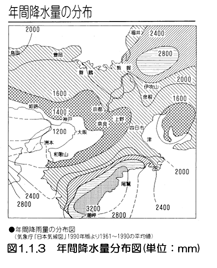九頭竜川流域は、本州日本海側のほぼ中央にあり、福井県嶺北地方に位置している。流域には、福井市をはじめ福井県の5市16町3村と岐阜県白鳥町の一部が含まれている。流域面積は、福井県面積の約70%に相当する2,930km2である。また、山地と平地の割合は、福井平野などの平地が約22.2%であり、残りの約77.8%が山地である。
流域の主流である九頭竜川は、幹川流路延長116kmを有し、北陸地方屈指の大河川であるとともに、この地域を代表する「母なる川」として古くから人々の生活と密接な関わりを持ち、親しまれてきた河川である。九頭竜川の源は、福井県と岐阜県境の油坂峠(標高717m)に発し、九頭竜峡谷を経て大野盆地を北流し、大野市と勝山市との境付近で左支川真名川を合わせ、永平寺町鳴鹿にて福井平野に入り、そこから西流する。そして、福井市高屋において左支川日野川を合流し、流れを北西に転じ三国町で日本海に注いでいる。日野川は、今庄町の夜叉ヶ池(標高1100m)を源として北流し、武生盆地を経て福井市大瀬で右支川足羽川を合流する。足羽川は、岐阜県境の冠山(標高1257m)に源を発し、池田町、美山町の山間地を北流し、上宇坂付近で西流に転じ福井市内を流れる。
九頭竜川水系主要河川の流域面積・流路延長等をまとめると表1.1.1のとおりである。
流域の主流である九頭竜川は、幹川流路延長116kmを有し、北陸地方屈指の大河川であるとともに、この地域を代表する「母なる川」として古くから人々の生活と密接な関わりを持ち、親しまれてきた河川である。九頭竜川の源は、福井県と岐阜県境の油坂峠(標高717m)に発し、九頭竜峡谷を経て大野盆地を北流し、大野市と勝山市との境付近で左支川真名川を合わせ、永平寺町鳴鹿にて福井平野に入り、そこから西流する。そして、福井市高屋において左支川日野川を合流し、流れを北西に転じ三国町で日本海に注いでいる。日野川は、今庄町の夜叉ヶ池(標高1100m)を源として北流し、武生盆地を経て福井市大瀬で右支川足羽川を合流する。足羽川は、岐阜県境の冠山(標高1257m)に源を発し、池田町、美山町の山間地を北流し、上宇坂付近で西流に転じ福井市内を流れる。
九頭竜川水系主要河川の流域面積・流路延長等をまとめると表1.1.1のとおりである。
表1.1.1 九頭竜川水系主要河川の諸元
横にスクロールできます
| 河川名 | 流域面積(km2) | 幹川流路延長 (km) |
備考 | ||
| 山地面積 | 平地面積 | 合計 | |||
| 九頭竜川 | 2,280.0 (77.8%) |
650.0 (22.2%) |
2,930.0 (100%) |
116.0 | 全流域 |
| 日野川 | 962.3 | 313.2 | 1,275.5 | 71.5 | 足羽川含む |
| 足羽川 | 356.8 | 58.8 | 415.6 | 61.7 | 日野川支川 |
| 真名川 | 286.8 | 70.1 | 356.9 | 47.1 | 九頭竜川支川 |
福井県は、県央南寄りの木ノ芽山地によって嶺北地方と嶺南地方とに分けられているが、嶺北地方に位置する九頭竜川流域は、日本海型の気候に入り、万葉歌人にも「み雪降る越」と詠われたように積雪が深く、冬期に降水量が多く年間で2,000~3,000mmに達する多雨多雪地帯に属している。降水量の年サイクルをみると、図1.1.1に示すとおり冬期のほか梅雨期、台風期に多い。したがって、図1.1.2のとおり2月~4月の雪どけ、6~7月の梅雨、9月の台風による降雨が主要因となって、その時期に流出量が多くなる。
九頭竜川は、表1.1.2のとおり年流出総量が約60億m3(中角+深谷)であり、近畿地方建設局が管理する一級水系10水系のうちでは淀川の86億m3に次いで豊富な水量を有して流れる河川である。また九頭竜川は、その一級水系10水系のうちでは淀川、新宮川に次いで流況が安定しており、清らかな流れと河川景観がすばらしい魅力に満ちたわが国を代表する河川の一つである。
九頭竜川は、表1.1.2のとおり年流出総量が約60億m3(中角+深谷)であり、近畿地方建設局が管理する一級水系10水系のうちでは淀川の86億m3に次いで豊富な水量を有して流れる河川である。また九頭竜川は、その一級水系10水系のうちでは淀川、新宮川に次いで流況が安定しており、清らかな流れと河川景観がすばらしい魅力に満ちたわが国を代表する河川の一つである。
表1.1.2 流況(※平成8年流量年表:建設省河川局)
横にスクロールできます
| 河川名 | 観測所名 | 流域面積 (km2) |
平均流況(単位:m3/s) | 年流出総量 ×106m3 |
観測期間 | |||||
| 豊水量 | 平水量 | 低水量 | 渇水量 | 最小流量 | 年平均流量 | |||||
| 九頭竜川 | 中角 | 1,239.0 | 121.59 | 81.24 | 54.82 | 27.96 | 0.00 | 109.49 | 3,455 | 昭和27~ 平成8年 |
| 日野川 | 三尾野 | 688.0 | 61.41 | 36.72 | 19.45 | 5.58 | 0.00 | 50.07 | 1,580 | 昭和41~ 平成8年 |
| 深谷 | 1,281.0 | 92.96 | 47.40 | 27.14 | 13.72 | 0.00 | 80.81 | 2,550 | 昭和33~ 平成8年 |
|
| 北川 | 高塚 | 201.6 | 13.49 | 7.97 | 4.12 | 1.33 | 0.00 | 11.40 | 360 | 昭和47~ 平成8年 |
| 新宮川 | 相賀 | 2,251.0 | 154.80 | 90.60 | 58.72 | 34.65 | 0.00 | 163.25 | 5,152 | 昭和26~ 平成8年 |
| 紀の川 | 船戸 | 1,558.0 | 55.77 | 32.07 | 18.48 | 7.04 | 0.00 | 61.50 | 1,941 | 昭和27~ 平成8年 |
| 大和川 | 柏原 | 962.0 | 20.37 | 11.76 | 7.96 | 3.52 | 0.00 | 24.17 | 763 | 昭和30~ 平成8年 |
| 淀川 | 枚方 | 7,281.0 | 285.25 | 196.31 | 148.40 | 106.94 | 58.30 | 271.62 | 8,572 | 昭和27~ 平成8年 |
| 加古川 | 国包 | 1,656.0 | 44.16 | 21.97 | 13.59 | 7.40 | 0.00 | 47.55 | 1,501 | 昭和26~ 平成8年 |
| 損保川 | 上川原 | 795.5 | 27.12 | 14.65 | 8.83 | 2.94 | 0.02 | 27.50 | 868 | 昭和48~ 平成8年 |
| 由良川 | 福知山 | 1,344.3 | 55.46 | 33.59 | 20.63 | 9.70 | 1.05 | 52.55 | 1,658 | 昭和28~ 平成8年 |
| 円山川 | 府市場 | 837.0 | 38.27 | 21.42 | 12.24 | 5.26 | 0.14 | 37.16 | 1,173 | 昭和46~ 平成8年 |
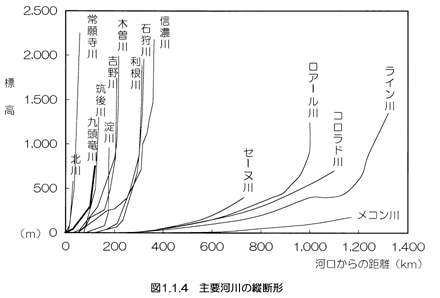
九頭竜川流域を代表する九頭竜川は、油坂峠を源流とすると標高差が約720mであるが、支川真名川の源流は標高約1,600mであり、急流河川に分類される河川であるといえる。図1.1.4に九頭竜川の縦断形を示す。
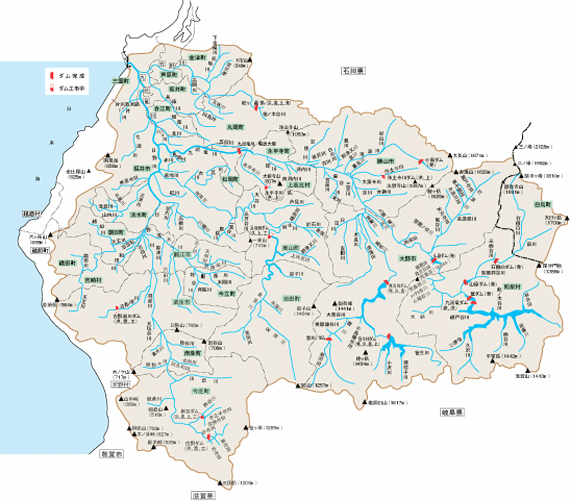
九頭竜川には多くの魚類が生息しているが、上流域ではイワナ・アマゴ・アユなど、中流域にはアユやアラレガコなど、下流域では淡水魚のほかに汽水性のボラ・スズキなどがみられる。
九頭竜川流域内の人口は約66万人、世帯数は約19万世帯(いずれも平成7年度の国勢調査)で、福井県全体の人口では約80%、世帯数では約79%を占めている。なお、想定氾濫区域の365km2には約42万人が住み、その資産額は約5.3兆円にのぼっている(平成2年度末現在「※河川現況調査近畿地方編:建設省近畿地方建設局 平成9年3月」)。
流域内人口の推移をみると、下流域が低平地で肥沃な沖積平野を形成していることから、農業を中心として発展してきたため、大都市地域の発展時期を迎えた昭和35年(1960)~45年には人口の流出が激しくなったが、オイルショック後はUターン現象で人口が増加してきた。しかし、現在ではほぼ横ばい状況となっている。
流域内の産業のうち、農業は早生種の米作りを基幹に、麦、大豆、地域振興作物を中心とした周年型農業の定着化を図りつつある。また工業は、繊維、機械、眼鏡などが主要産業であるが、先端技術産業を積極的に誘致し、新しい産業の創出が進められている。また、三国の福井臨海工業地帯や鯖江工業団地では、高度加工組立型新産業などの導入を図り、地域産業の活性化を促進する方向にある。伝統産業の鯖江市河和田の漆器、今立町五箇の和紙、武生市の打刃物なども、地域ぐるみの総合的な振興策が推進されている。
九頭竜川流域内の人口は約66万人、世帯数は約19万世帯(いずれも平成7年度の国勢調査)で、福井県全体の人口では約80%、世帯数では約79%を占めている。なお、想定氾濫区域の365km2には約42万人が住み、その資産額は約5.3兆円にのぼっている(平成2年度末現在「※河川現況調査近畿地方編:建設省近畿地方建設局 平成9年3月」)。
流域内人口の推移をみると、下流域が低平地で肥沃な沖積平野を形成していることから、農業を中心として発展してきたため、大都市地域の発展時期を迎えた昭和35年(1960)~45年には人口の流出が激しくなったが、オイルショック後はUターン現象で人口が増加してきた。しかし、現在ではほぼ横ばい状況となっている。
流域内の産業のうち、農業は早生種の米作りを基幹に、麦、大豆、地域振興作物を中心とした周年型農業の定着化を図りつつある。また工業は、繊維、機械、眼鏡などが主要産業であるが、先端技術産業を積極的に誘致し、新しい産業の創出が進められている。また、三国の福井臨海工業地帯や鯖江工業団地では、高度加工組立型新産業などの導入を図り、地域産業の活性化を促進する方向にある。伝統産業の鯖江市河和田の漆器、今立町五箇の和紙、武生市の打刃物なども、地域ぐるみの総合的な振興策が推進されている。