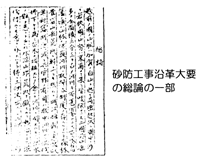廃藩置県以後、森林の伐採や焼畑などが殆ど無制限に行われ、山地は一層荒廃し、一度大雨ともなれば斜面の崩壊などによる土砂害が至るところで発生した。災害は、年を経るごとに激しさを増し、砂防の必要が叫ばれるようになった。
そこで、明治25年(1892)11月に県議会で土砂扞止の建議がなされ可決された。同27年(1894)には臨時県議会で砂防工費2,740円が議決された。これによって、上庄村佐開地区(現大野市)の真名川支川鬼谷川に石積堰堤を築き、明治30年(1897)に完成した。これは、福井県としては最初の砂防工事である。同28年には、大飯郡の佐分利川および滝岩谷川でも砂防堰堤工事に着手した。
その後、明治28、29年の大水害でこれらの施設にも被害を受けるなど、大きな災害となったため、同30年に制定された砂防法に基づき、同31年(1898)には現地調査を実施し、24河川を対象に10ヵ年継続で第一期砂防工事を実施する計画を策定した。
砂防法の施行によって明治32年(1899)4月、佐開地係(現大野市)の鬼谷川、佐分利村川上地係(現大飯町)の永谷川および新鞍谷川の3ヵ所が砂防指定地となり、同年度より国庫補助を得て砂防工事が本格的に施工され始めた。
真名川支川の鬼谷川では同32年度から36年度まで、西勝原(大野市)の白谷川では同33年度から36年度までに砂防堰堤工事が施工された。
明治32年度から実施を始めた第一期工事は、大正4年(1915)に至る15年間に67万余円を費やして進めたが、日露戦争などがあり計画どおり遂行できず、第二期工事に委ねることとなった。
そこで、明治25年(1892)11月に県議会で土砂扞止の建議がなされ可決された。同27年(1894)には臨時県議会で砂防工費2,740円が議決された。これによって、上庄村佐開地区(現大野市)の真名川支川鬼谷川に石積堰堤を築き、明治30年(1897)に完成した。これは、福井県としては最初の砂防工事である。同28年には、大飯郡の佐分利川および滝岩谷川でも砂防堰堤工事に着手した。
その後、明治28、29年の大水害でこれらの施設にも被害を受けるなど、大きな災害となったため、同30年に制定された砂防法に基づき、同31年(1898)には現地調査を実施し、24河川を対象に10ヵ年継続で第一期砂防工事を実施する計画を策定した。
砂防法の施行によって明治32年(1899)4月、佐開地係(現大野市)の鬼谷川、佐分利村川上地係(現大飯町)の永谷川および新鞍谷川の3ヵ所が砂防指定地となり、同年度より国庫補助を得て砂防工事が本格的に施工され始めた。
真名川支川の鬼谷川では同32年度から36年度まで、西勝原(大野市)の白谷川では同33年度から36年度までに砂防堰堤工事が施工された。
明治32年度から実施を始めた第一期工事は、大正4年(1915)に至る15年間に67万余円を費やして進めたが、日露戦争などがあり計画どおり遂行できず、第二期工事に委ねることとなった。