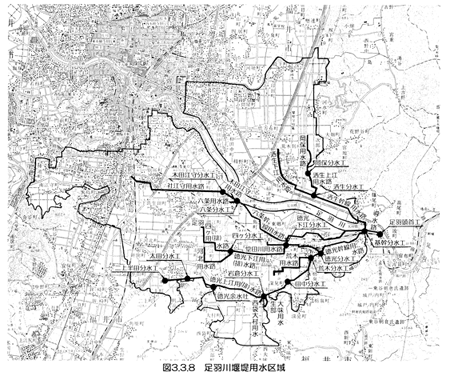
足羽川の堰堤は木工沈床であるため、洪水のたびの修繕と不統一な取水量が水利紛争の原因となり、さらに用水路が曲折していて素掘であったため維持管理費が増加する一方であった。
九頭竜川の鳴鹿堰堤が昭和30年度に完成したので、足羽川統合井堰の建設が叫ばれ、徳光・酒生・六条・四ヵ・木田・江守の各土地改良区および稲津・脇四ヵ用水組合が協定書に調印して統合井堰建設に向けて動き始めた。
そして、県営一般灌漑排水事業として昭和32年度に着手し、昭和38年(1963)11月に足羽川堰堤が完成した。管理運営は、徳光用水・酒生用水・六条用水・足羽四ヶ用水・木田用水・社江守・足羽三ヶの各土地改良区が集まって足羽川堰堤土地改良区連合を発足させ、用水堰ならびに付属施設の維持管理、災害復旧を行うこととなった。こうして、受益面積2,321haの水田を潤すこととなった。
その後、施設の老朽化と漏水等が進み、県営事業として昭和55年度から平成6年度には頭首工護床工や幹線水路工22.31km、分水工などの施設改善が行われた。
九頭竜川の鳴鹿堰堤が昭和30年度に完成したので、足羽川統合井堰の建設が叫ばれ、徳光・酒生・六条・四ヵ・木田・江守の各土地改良区および稲津・脇四ヵ用水組合が協定書に調印して統合井堰建設に向けて動き始めた。
そして、県営一般灌漑排水事業として昭和32年度に着手し、昭和38年(1963)11月に足羽川堰堤が完成した。管理運営は、徳光用水・酒生用水・六条用水・足羽四ヶ用水・木田用水・社江守・足羽三ヶの各土地改良区が集まって足羽川堰堤土地改良区連合を発足させ、用水堰ならびに付属施設の維持管理、災害復旧を行うこととなった。こうして、受益面積2,321haの水田を潤すこととなった。
その後、施設の老朽化と漏水等が進み、県営事業として昭和55年度から平成6年度には頭首工護床工や幹線水路工22.31km、分水工などの施設改善が行われた。

