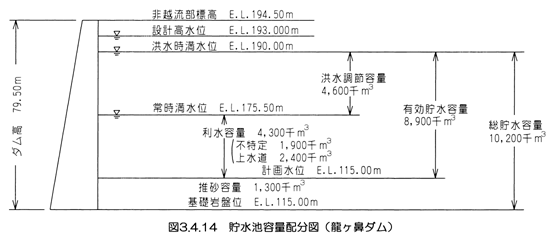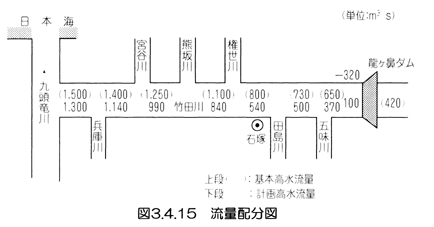(1)概要
竹田川は、昭和32年(1957)度に河道の第一期改修がほぼ完了し、一応整備されたが、昭和36年(1961)の第二室戸台風、昭和39年(1964)、40年(1965)の豪雨などにより甚大な被害を被ったので、早急に抜本的な治水対策を実施する必要に迫られた。
そこで、九頭竜川との合流点での基本高水流量1,500m3/sに対して、上流ダムによって200m3/s調節し、1,300m3/sとする竹田川改修計画が立てられた。
また、本流域は福井県内有数の稲作地帯であるが、渇水時には毎年用水不足を生じ、一方、坂井郡6町の上水道は地下水に依存している。しかし、年々その水位は低下し、また、将来の生活様式の向上と人口の増加に伴う上水道使用量の増加に対処するための用水補給、さらに、代替エネルギーとして水力発電の開発が必要となり、ダム築造が望まれた。
福井県においては、昭和43年度より46年度にわたって河川総合開発事業による実施計画調査を実施し、昭和47年、丸岡町に建設事務所を設置し、昭和53年度に地元とダム建設について合意に達したので、昭和54年(1979)より工事に着手し、平成元年(1989)3月に建設費215億円を要して工事が完成した。
(2)洪水調節計画
- 計画高水流量
- 洪水調節計画
- 発電計画
- 水道計画
流域内雨量観測所の既往最大日雨量は、竹田で235.4mm、三国で254.5mmとなっている。両観測所の50年の超過確率日雨量は237.5mmとなり、竹田川改修計画もこれを採用しているので、当ダムでもこの日雨量を使用し、ダムサイト計画高水流量を求めると420m3/sとなる。
下流兵庫川合流後の基本高水流量1,500m3/sに対し、改修計画では1,300m3/sであり、200m3/sのカットが出来るよう調節する。そこで、龍ヶ鼻ダム地点における計画高水流量420m3/sのうち320m3/sの洪水調節を行う。
調節方法は、ダムサイト流入量が40m3/sよりピーク流入量に達するまでは一定率放流し、ピーク後は100m3/sを一定量放流する。
龍ヶ鼻ダムより最大4.5m3/sを取水し、ダム直下の山口発電所で有効落差52m、最大出力1,900kwの発電(完全従属方式)を行う。
坂井郡6町の上水道は、現在給水人口99,300人に対して、1日最大46千m3を給水しているが、その水源はいずれも地下水である。その地下水位は、年々低下している。また、福井臨海工業地帯および従業員住宅団地の計画がある。このため人口の増加が予想され、計画給水人口を135,000人として給水量も94,200m3/日が必要となる。そこで、このうち47,500m3/日(0.55m3/s)を龍ヶ鼻ダムより供給する。
(3)貯水池使用計画
- 洪水調節
- 不特定利水(灌漑)
- 水道用水
年間を通じてE.L.175.5mから190.0mの間の容量4,600千m3を利用して、ダムサイトにおける計画高水のピーク流量420m3/sのうち320m3/sを調節する。
不足用水に対して、E.L.153.0mから175.5m間の容量4,300千m3のうち、1,900千m3を利用して補給する。
E.L.153.0mから175.5mの容量4,300千m3のうち、2,400千m3を利用して供給する。
参考文献
- 真名川総合開発 昭和35年3月 福井県電気局
- 九頭竜川流域の水害地形と土地利用 昭和43年(1968) 科学技術庁資源調査所
- 真名川ダム工事誌 昭和54年7月
- 福井県土木史 昭和58年5月 編集・発行:福井県建設技術協会
- 九頭竜川-直轄事業のあゆみ- 平成3年3月 近畿地方建設局福井工事事務所
- 九頭竜ダム(建設の記録) 平成4年3月 九頭竜川ダム統合管理事務所
- 福井のダム 平成9年1月 福井県土木部開発課
編集:真名川ダム工事誌編集委員会
発行:建設省近畿地方建設局