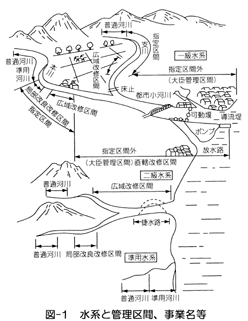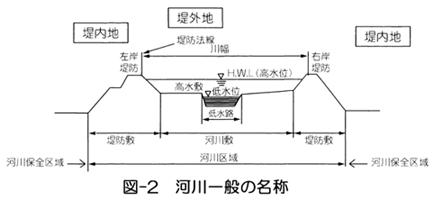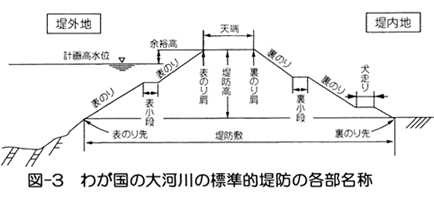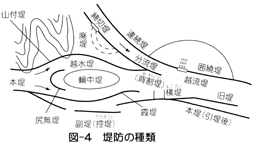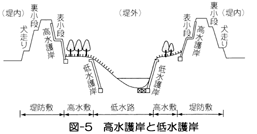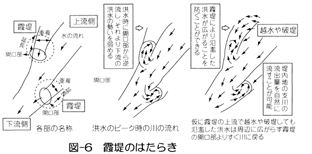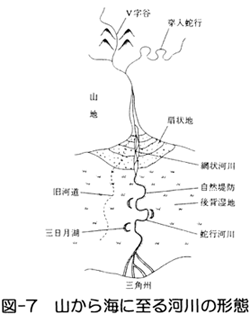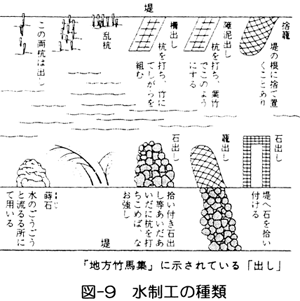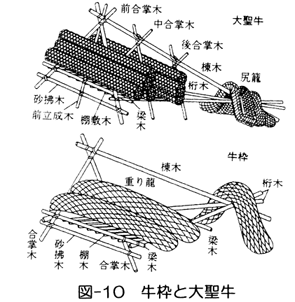1.流域
ある川に雨水が流入する全域を、その川の「流域」という。流域の互いに接する境界を「分水界」という。分水界が山脈の場合は「分水嶺」ともいう。
2.水系
3.河川の等級
日本の河川法では、国土保全や経済的観点から「一級水系」と「二級水系」に分類される。
「一級河川」は、平成11年現在109水系を政令で指定しおり、一級水系の河川のうちで建設大臣が指定した区間を原則として建設省が管理する。しかし、管理の一部を都道府県知事に委任した指定区間もある。「二級河川」は、二級水系のうち都道府県知事が指定したもので、主として各地方自治体が管理する。
これ以外には、市町村長が指定する「準用河川」があり、河川法の一部が準用される。以上の指定を受けた河川以外は、「普通河川」という。
「一級河川」は、平成11年現在109水系を政令で指定しおり、一級水系の河川のうちで建設大臣が指定した区間を原則として建設省が管理する。しかし、管理の一部を都道府県知事に委任した指定区間もある。「二級河川」は、二級水系のうち都道府県知事が指定したもので、主として各地方自治体が管理する。
これ以外には、市町村長が指定する「準用河川」があり、河川法の一部が準用される。以上の指定を受けた河川以外は、「普通河川」という。
4.本川と支川、派川
二つ以上の河川が合流するとき、流域や流量、河川幅が大きく、延長も長く、歴史的経緯からも定められてきた河川を「本川」、それに流入する河川を「支川」という。
本川の右岸側に合流する支川を「右支川」、左岸側に合流する支川を「左支川」と呼ぶ。
本川から分かれて流れる河川を、派川という。
本川の右岸側に合流する支川を「右支川」、左岸側に合流する支川を「左支川」と呼ぶ。
本川から分かれて流れる河川を、派川という。
5.河川一般と堤防の名称
河川一般の名称を図-2に、堤防の名称を図-3に示す。
川の左岸・右岸は、川の流れの方向(下流)に向かって左側を「左岸」、右側を「右岸」と呼ぶ。
堤防に対して水が流れる側を「堤外地」、堤防によって保護されている住居や農地が位置している側を「堤内地」という。
川の左岸・右岸は、川の流れの方向(下流)に向かって左側を「左岸」、右側を「右岸」と呼ぶ。
堤防に対して水が流れる側を「堤外地」、堤防によって保護されている住居や農地が位置している側を「堤内地」という。
6.堤防の種類
横にスクロールできます
堤防の形状や機能などから、さまざまな名前の堤防がある。
| 本堤 | 流水が河川外に流出するのを防ぐために、流路に沿って設ける構造物。土砂を用いて盛土する。 |
|---|---|
| 連続堤 | 連続して造られる堤防。 |
| 輪中堤 | 一定地域の周囲をめぐらして造られる堤防。 |
| 霞堤 | 下流端を開放し上流端を堤内に延長して、重複して造る不連続な堤防。 |
| 瀬割堤 | 分流または合流させるとき、両方の川に兼用される堤防。 |
| 導流堤 | 他の川や海などに注ぐとき、水流を導く目的で造られる堤防。 |
| 越流堤 | 堤防の一部を低く造り、洪水時に流水を計画的に越流させる堤防。 |
| 横堤 | 本堤にほぼ直角方向に堤防を設け、流勢を弱める。 |
| 山付堤 | 堤防を高地へつなぎ、背後地を守る。 |
7.洪水と高水
横にスクロールできます
| 洪水 | 大雨や融雪などを原因として、河川流量が異常に増大すること。 |
|---|---|
| 洪水位 | 数年に1回程度の頻度に起こる洪水の水位。 |
| 高水位 | 毎年1~2回起こる程度の出水時の水位。 |
| 計画高水 | 治水計画を策定するときの基準地点における洪水のこと。 |
| 基本高水流量 | 治水計画を策定するときに計画の基準とする洪水波形の最大流量。 |
| 計画高水流量 | 河道計画を立てるときの洪水の規模のこと。 基本高水を合理的に遊水地や洪水調節ダム等に配分して、河道や洪水調節ダム等の計画の基本となる流量が決定される。 |
| 計画高水位 | 計画流量を流下させるため、河道計画の基準となる最高水位のこと。堤防の形状は、計画高水流量と計画高水位を基に決定する。 |
| 計画降雨 | 治水・利水計画を立案するとき、計画上対象となる降雨。 |
| 洪水災害 | 洪水流と洪水氾濫によって引き起こされる河道災害、浸水災害、流失災害などの総称で、洪水害ともいう。 |
| 洪水氾濫 | 洪水が河岸や堤防を越して溢れること。 |
| 高水管理 | 台風や豪雨による洪水被害の軽減を目的として、河川水を管理すること。洪水を安全に流下させるために、正確な洪水予報に基づいて、洪水調節ダム、貯留施設などを有機的に運用する。 |
8.超過確率について
計画降雨量は、雨量観測所で観測された雨量データを用いて統計解析し決定する。
計画降雨の超過確率(あるいは再現期間)は、現在までに得られた降雨記録に基づいて計算したものであり、将来も同様な降雨分布が期待されるという前提がある。
例えば、10年の再現期間をもつ降雨量は、10年に1回の割合でそれを超えるような降雨量が発生することを意味し、10年のうちどの年も10%の確率でその降雨量が生じることを意味する。超過確率が1/10年の降雨量は、一度発生すれば10年間は決して起こらないということではない。
計画降雨の超過確率(あるいは再現期間)は、現在までに得られた降雨記録に基づいて計算したものであり、将来も同様な降雨分布が期待されるという前提がある。
例えば、10年の再現期間をもつ降雨量は、10年に1回の割合でそれを超えるような降雨量が発生することを意味し、10年のうちどの年も10%の確率でその降雨量が生じることを意味する。超過確率が1/10年の降雨量は、一度発生すれば10年間は決して起こらないということではない。
9.河川の形態
10.ダムの種類
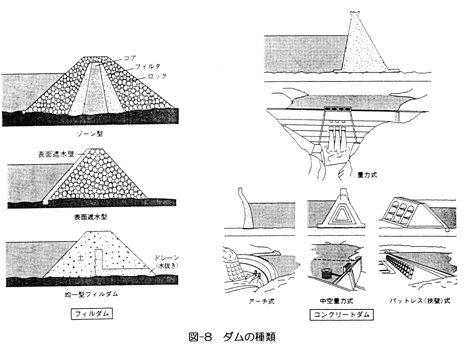
ダムの形式は、材料によってコンクリートダムと土や岩でつくるフィルダムに分類される。さらにコンクリートダムは、水圧をどのように支えるか、その構造で分けられる。また、フィルダムは水をどのように遮水するかによって分類される。
主なダムの種類は、図ー8のとおりである。
主なダムの種類は、図ー8のとおりである。
11.水質に関する用語
横にスクロールできます
| mg/リットル | 濃度を示す単位。1リットル中に1mgの量が溶けていれば1mg/リットル。 |
|---|---|
| BOD(生物化学的酸素要求量) | 水中のバクテリアが、有機物を酸化分解するために消費する酸素の量。値が大きいとその水が汚染されていることを示す。 |
| COD(化学的酸素要求量) | 水中の酸化され易い物質が酸化剤によって化学的に酸化されるのに要する酸素量。COD測定は湖沼や海域では 藻類、塩分等の影響を受けにくいため、BODに代わって用いる。 |
| DO(溶存酸素) | 水中に溶けている酸素のこと。値が少なくなると水がくさり魚が死 ぬことになる。 |
| PH(水素イオン濃度指数) | 中性の水は PH7で、7より低いと酸性、7より高いとアルカリ性を示す指標。 |
12.水制工
「水制」とは川の流速を低下させたり、流れの方向を変えたりするために、河岸から流れの中心部に向かって突きだして設置されるものである。いろいろな種類がある。
九頭竜川上・中流のように急流な所では、木の枠を組み、それに石を入れた籠をのせて、自重で流れに抵抗できる「牛類」などがよく用いられた。下流では、粗朶の上に石を詰めた蛇籠を置いた「水刎工」が多く用いられた。
九頭竜川上・中流のように急流な所では、木の枠を組み、それに石を入れた籠をのせて、自重で流れに抵抗できる「牛類」などがよく用いられた。下流では、粗朶の上に石を詰めた蛇籠を置いた「水刎工」が多く用いられた。