 |
 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| その後、大堰所の普請は鳴鹿村や下浄法寺村(ともに現永平寺町)などの者が契約で請負うようになり、幕末の頃になるといずれの領主も財政が困窮したため、大堰の補修にあたっては井守役が資金調達に奔走しなければならなくなった。 このように、堰の安全度は低く、その最大の原因は洪水にあった。越前最大の河川に築造され、洪水の危険にさらされながら223ヵ村の生命線である用水を確保していた。九頭竜川本川下流に取入口をもつ用水は、このようにして管理されていた。 九頭竜川沿川に住む人々は、九頭竜川本川の一部において堤防が築造されていたとはいえ、洪水に対して安全なものとはいえず、近世において水害は殆ど不可抗力のものと諦めていた。一度洪水ともなれば、広範囲にわたって水害に悩まされてきた農業従事者は、用水を確保するため扇状地の頂部にあたる鳴鹿に大堰所を築造し、放射状に用水路を設けて、少しでも広い地域へ通水することに心血を注いできた。 用水には本支流の全域にわたって古法旧慣があり、藩役所から示された用水御掟書があってそれらを厳守させた。農業従事者が生命線としての用水路の維持管理に全力を尽くしたが、この用水管理の前に、洪水によって被害を受けたので、用水管理の重要性はさらに倍加したものといえる。 このような鳴鹿大堰所の管理は年間を通じての大事業となり、大堰の普請は請負制度になっていった。この制度はきわめて厳重で、業者から証文を提出させ、江守役や用水組合総代の指図に従い、規定の工事をすることとなっていた。請負元から上司に提出した「相渡申請負証文之事」によれば、次のとおりである。 |
|
| これには、堰の作り方、江口の掘り方、人足、堰材料等を詳細に規定しているばかりでなく急水の場合についても入念に規定している。さらに「引請申藤杭証文之事」には、次のように、洪水による堰流失の場合、大堰所の請負の材料の供出および、その賃金などを詳細に規定している。 |
|
| このなかで、竹田藤(竹田川上流の竹田村に自生する藤)は堰立ての越中三叉のしめ縄に用いるもので、この藤は特に水に強かったところから産地まで指定したものである。このことについては、竹田村(現丸岡町)の坪川家に「相定申一札之事」という古文書があり、この中に「先林新林共に山の内へ道具を持ち出入沙汰相成不申候 鳴鹿藤は苦しからず候事」と記されており、山奉行も特例を設けていた。このように厳重な規定によって大堰所は毎年堰立てられるのであるが、年によって洪水のため大堰所が流れ二番堰、三番堰を必要とすることがあった。 この地方では毎年、半夏生水、盆水、彼岸水と決まって出水があり、特に大水の年などは、この洪水によって堰が流出し二番堰、三番堰が行われた。享保12年(1727)、寛政元年(1789)、文化13年(1816)はこのような年で、証文によれば、請負者も藤杭供出者も年額で伐採が決まっており、しかも二番堰、三番堰まで責任を持たなければならないことになっていた。文化13年は特に大水で、規定に基づいて藩では竹田村外5ヵ村に二番藤、杭の供出を申込んだところ、新たな代米がなければ、これを渡せないということになり、この解決に1ヵ月を要した。 このように堰立ては大事業であったにも関わらず、大堰所は春の彼岸に新たに造り、秋の彼岸には左岸側24間(43.6m)を切り落とすこととなっていた。これは寛延4年(1751)8月五領ヶ島との争いによるものであり、4年の後(宝暦5年2月)江戸評定所によって、「越国鳴鹿堰所切候儀 前々棒杭より堰之上に向二十四間切可申候。尤切候所にも新規棒杭打可申事。」の決定によるものである。これは五領ヶ島村民が秋より冬にかけて、九頭竜川右岸の浄法寺山に薪取に行くための交通上の便宜によるものであった。 鳴鹿大堰所はこのように洪水にも、渇水時の取水にも管理には苦労が多く困難を極めた。 |
| (3) | 明治時代以後の堰堤 | ||
| 明治維新後、井守役は選挙制度となり、土肥氏、大連氏、藤井氏が選出され、明治23年(1890)の水利組合条例の公布まで、従前どおりの管理が続いた。 明治24年(1891)2月に十郷大堰所普通水利組合を設置し、坂井郡長が管理者となった。ここで、従来からの井守役制度が改正され、半官半民の体制がスタートしたのである。 しかし、構造は松杭を鉄線で結び三叉組にして3列並べ、その間に玉石を詰めたものであり、藤蔓から鉄線に変わった程度である。その前方に周3尺(91cm)、長さ10尺(3m)の粗朶を並べ、その上に筵1枚をかけて漏水を防ぐ。また、堰裏には長さ5間(9.06m)、直径2尺(61cm)の蛇籠を400〜500個3列に並べ、落水によって川底を洗掘されないように保護するようにした。
このようにして、鳴鹿山鹿と東古市の間の九頭竜川を遮断して、長さ160間(約291m)、幅5間の取入堰を構築し、水流を坂井平野へと導いたのである。なお、三叉・框・蛇籠は陸上で作り、10隻の川舟で運んだという。 したがって、出水のたびに流失するため、絶えず補修しなければならなかった。 6ヵ所の用水取入口を統合する堰とする構想が芽生え、昭和初期には当局への陳情が行われた。昭和10年(1935)には、農林省を動かせ予算計上まで至ったが、過重負担であるということで着工に至らなかった。 そして、昭和23年(1948)には、長さ7尺5寸(2.27m)、末口5寸(15cm)の松丸太を方形に組立て、長さ7尺5寸、末口2寸(6cm)の松丸太を根太木2寸と敷成木7本で十文字に組んで針金で締め付けた木工沈床を採用した。4尺3寸(1.3m)の方形の四隅を5分(1.5cm)ボルトで締め付け、内部に玉川石を投入して流れないようにした。九頭竜川の締め切り長170間(309m)に1,700の小間を作って半永久としたのである。 さらに、昭和21年(1946)に国営農業水利事業制度が発足したのを受けて、昭和24年からは国営九頭竜川地区農業水利事業によって、堰長273mの内、中央108mの固定堰を除いた箇所に可動門扉を設置して、計画高水流量3,058m3/sを流下させるとともに、左右両岸に取り入れ口を設置して最大42.5m3/sの取水を可能とした堰堤工事を行い、昭和30年(1955)3月に完成した。 |
|||
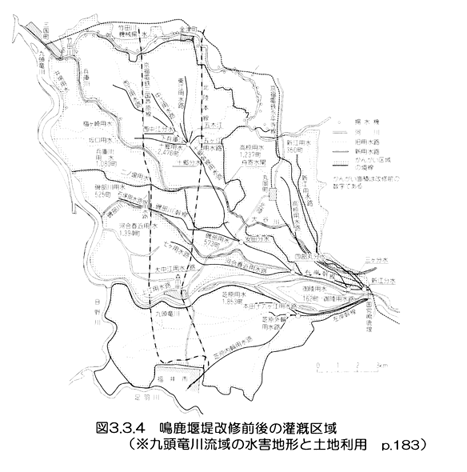 |
Copyright (c) 国土交通省近畿地方整備局 福井工事事務所 2001 All
Rights Reserved.

