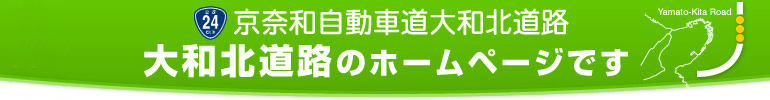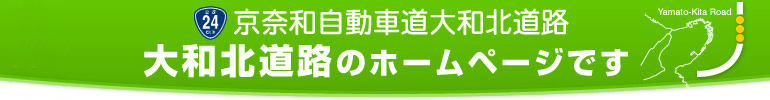1) |
委員長は大西有三教授とすることで了承されました。 |
2) |
委員会設立趣旨について以下のように確認しました。 資料−1
- 当委員会は、文化財の保全等の観点より、地下水の状況を把握し、適切な地下水のモニタリング方針を定めるものである。
|
3) |
事務局から、大和北道路の検討の流れについて説明がありました。
資料−2 |
4) |
事務局から、大和北道路地下水モニタリング検討委員会規約(案)について説明があり、一部事務局で訂正案を説明し、確認されました。
資料−3
- 第5条 職務を代理する → 訂正 職務を代行する。
|
5) |
今後の委員会に進め方について確認しました。 資料−4
| (1) |
本委員会では、施工後の地下水の状況も含めて、検討を行う。 |
| (2) |
検討内容について、各委員が専門的な立場から意見を述べ、それについて議論を行う。 |
| (3) |
討論内容をもとに、モニタリングの方針「委員会の提言」としてまとめる。 |
|
| 6) |
事務局から地下水の現況について以下の説明がありました。 資料−5
- 地下水流動は地形の高さに沿って南北方向への流下を基本とした状態で、現在の観測状況と一致している。
- 第1帯水層の地下水位は観測データを見ると、降水に対して敏感に反応、水位については、一定若しくは上昇傾向にある。
|
| 7) |
意見交換の内容
- 現況の水位観測箇所について、周辺状況を勘案して、調査する。
- 木簡の出土は、古代の遺構の溝、井戸で発見されることが多い。
- 木簡が発見されるのは、井戸の場合は、砂の層からでも発見される。溝の場合は、粘土の中から発見される事が多い。
- 木簡は、遺構面から80cm〜1m、地表から約1.5mぐらいで発見される。
- 井戸については、第一帯水層の水位との関係が大きい、第一帯水層とその上の粘土層との関係については、粘土層の水位保持力の関係がある。
- 土のサンプルを現地採取し、土質の性質を調べること。バクテリアの関係については、地下水質のEh(酸化還元反応)を調査し検討すること。
|
| 8) |
次回は、これまでの地下水に関する検討結果や観測状況を踏まえ、地下水位の変動傾向等の状況分析や、地下水モニタリングの具体的な内容について、各委員の専門分野についてご意見を頂き、検討を行うこととなりました。
以上 |