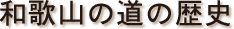
徳川家を始めとする将軍家に関わる人物が藩主を務め、
西国の要衝として栄えた和歌山には、多くの人・もの・情報を運び、
人々の暮らしとともに歴史を刻んできた道がいまも残されています。
古代から現代へ、和歌山の道は、古くから重要な役割を果たしてきました。
西国の要衝として栄えた和歌山には、多くの人・もの・情報を運び、
人々の暮らしとともに歴史を刻んできた道がいまも残されています。
古代から現代へ、和歌山の道は、古くから重要な役割を果たしてきました。
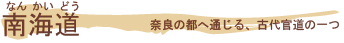
日本初の古代の官道「七道駅路」のひとつで、都から紀伊・淡路を経て四国に通じる道。 一部が大和街道といわれ、天皇の御幸路でした。街道沿いに旅人たちの万葉歌が残されています。 萩原駅(和歌山市)、名草駅(かつらぎ町)など、馬の中継地「駅」が置かれ、鎌倉時代から江戸時代にかけては「宿」と呼ばれました。


紀の川河口、紀州藩の和歌山城下から流域の岩出、粉河、那賀へと遡り橋本に至る街道。 京橋御門外・札の辻を起点に、岩出の紀の川南岸から北岸へ。 岩出の渡し、対岸の清水には伝馬所、宿屋や酒店も賑わいました。 根来街道の分岐を北上すると国宝重文を擁する「根来寺」、打田を経た先に「粉河寺」があります。

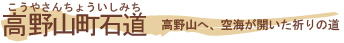
高野七口(登山道七本)のうち、弘法大師空海が高野山を開いてすぐ設けた参詣道。 慈尊院から西口大門を経て奥の院に至る約24kmの表参道で、 一町(約109m)ごとに町数の刻まれた町石が216基もあります。 木製の五輪卒塔婆でしたが、鎌倉幕府の有力御家人の力で、朝廷、貴族、武士などが寄進し石造となりました。


平安時代中期、阿弥陀信仰の聖地・熊野三山へ法皇や上皇などが御幸を行い、貴族も庶民も参詣に使った街道。 近世以後、口熊野(田辺)までは「紀伊路」、田辺から熊野三山は「中辺路」と呼ばれ、 紀伊半島南沿岸を大きく回る「大辺路」、高野山から峠を越えて南下する最短の「小辺路」、山伏による「大峯路」も開かれます。

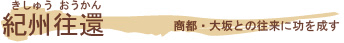
城下町和歌山から、商都・大阪へ通じる道。城下を後に紀の川を渡り、 海抜106mの孝子峠を越えると小高い山が連なる岬町へ。 さらに、大阪湾岸沿いの北東にある商都として栄えた泉佐野を抜けて、岸和田に入ります。 岸和田城の北側に沿って進み、貿易、鍛冶で繁栄を極めた堺を抜け、大阪へと至る道です。

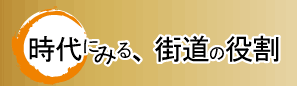
奈良に都が誕生し、大和朝廷は国家の道づくりの始まり、全国を統治するための官道をつくります。 紀の川沿いに和歌山と奈良を結ぶ紀北のみち「南海道」は、中央と地方を結ぶ道。奈良時代に皇族の御幸ルートとなります。
信仰の道 平安-室町時代
平安時代には聖地の熊野三山へ向かう皇族や貴族の熊野詣が盛んとなり、 室町時代からは庶民にも広がり、「蟻の熊野詣」といわれるほど賑わいます。 室町時代以降、参詣道は複数でき、熊野街道はこれらの総称となります。
参勤交代の道 近 世
江戸時代以降、徳川吉宗など歴代の紀州藩主の参勤交代に利用されたことから、 紀州街道と呼ばれた道は、その後、庶民が大和地方との関わりを深くもつようになり、 大和街道というように名を変えていきます。
自動車の道 近 代
街道は近代に入り県道や国道に改修され、「現代の街道」としての役割を果します。 大和街道があった紀ノ川沿いに国道24号、南海岸沿いには国道42号が通っていますが、今後新たな道が整備され、より便利になります。
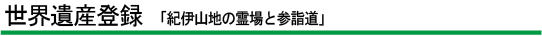
「紀伊山地の霊場と参詣道」は、3つの霊場(熊野三山、吉野・大峯、高野山)と
そこへ至る参詣道(熊野参詣道、大峯奥駈道、高野山町石道)から構成されます。
高野山や熊野三山に至る参詣道も信仰の拡大とともに、整備され、周辺の文化的な景観とともに当時の状態が維持されています。
平成12年に文化庁の国内リストに記載され、平成16年7月の世界遺産委員会により世界遺産へ登録されました。

このシンボルマークは、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」
(「吉野・大峯」、「熊野三山」、「高野山」の三霊場と、それらをつなぐ参詣道で構成されています)
を広くPRするために作成されたものです。
デザインの意図 紀伊山地の3つの霊場とそれらへ向かう道をイメージ。
紀伊山地の奥深さ、霊場の神秘性、参詣道の精神性が、グラデーションを活かした淡い緑とアクセントに用いた黄色で表現されています。

“ことはじめ”とは物事の始まりを意味します。
ここでは、「和歌山発」の「日本初」・・・和歌山県に日本で初めて誕生した物、事柄、そのルーツをいくつかご紹介しましょう。

高野豆腐
豆腐を凍結乾燥させた「高野豆腐」の発祥地は、名前の通り、高野山。
豆腐を凍結乾燥させた「高野豆腐」の発祥地は、名前の通り、高野山。
冬に修行僧が豆腐を雪の中に落としてしまうという偶然から生まれた産物といわれています。 宿坊で作り始められたことから、精進料理に多く使われ、高野山名物のおみやげとしても有名です。

ルミナリエ
光の芸術「ルミナリエ」を日本で初めて開催しました
光の芸術「ルミナリエ」を日本で初めて開催しました
幻想的な光の芸術「ルミナリエ」といえば、神戸を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、実は和歌山が日本初。 和歌山マリーナシティ(和歌山市)で開催された「世界リゾート博1周年記念イベント」の一環として、 平成7年(1995年)7月に行われたのが最初です。 ちなみに、ルミナリエの語源はイタリア語のluminaの複数形luminarieで、小電球などによる光の装飾を意味します。

「鈴木」姓
海南市は日本でもっとも多い「鈴木」姓の発祥地です
海南市は日本でもっとも多い「鈴木」姓の発祥地です
全国に200万人いるといわれる一番多い「鈴木」姓、その発祥地は海南市。 社家や神官に付けられた姓で、古くは平安時代末期に後鳥羽上皇等が熊野詣の際、 熊野古道の玄関口である海南市の藤白でお迎えした時についたとされています。 藤白神社の境内には、鈴木姓のルーツにあたる旧家があり、「鈴木邸」の表札がかかっています。

醤油
湯浅から醤油が生まれ、全国に広がりました
湯浅から醤油が生まれ、全国に広がりました
由良町にある「興国寺」の法燈国師が、中国で製法を習った「金山寺味噌」を持ち帰りました。 野菜と大豆で作られる金山寺味噌は、健康食として盛んに作られるようになりました。 醸造の際、樽底に溜まった汁や上澄み液をなめると美味しく、調味料として使われるようになり、 これが「醤油」の始まりだといわれています。
