【海南・有田の魅力を知る】
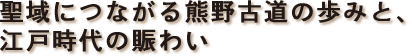
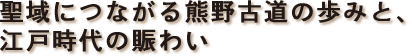
平安時代中期ごろ、熊野本宮、熊野速玉、熊野那智は「熊野三山」と称され、
阿弥陀信仰の聖地として法皇・上皇が御幸を行い、貴族も庶民も相次いで参詣するようになりました。
「蟻の熊野詣」といわれたほどです。
熊野三山への道は紀州回りと伊勢回りがありましたが、紀伊路である「熊野古道」を行く人が多く、
途中には「九十九王子」と呼ばれる数多くの社があり、宿泊を兼ねた参詣者の休息場となっていました。
京都から大阪を経て熊野に入る熊野古道は、現在の海南市、有田市、広川町を縦断するルート。
和歌山市から海南市の多田−大野中−鳥居裏−藤白坂に通じています。
藤白神社はかつての藤白王子で、7世紀中ごろの斉明天皇期に創建され、ここからが熊野聖域の入口といわれています。
 黒江の街並み |
街道沿いは古くから賑わい、商いが生まれ、そこにまちが生まれています。 鎌倉から江戸時代に入ると職人が栄え、海南市の黒江地区では漆器づくりが盛んでした。 「黒江塗」として紀州藩の保護を受け、全盛期には2000人余りの職人が集まり、 その風情は黒江の街並みとして今も偲ばれます。 また、湯浅は金山寺味噌から醤油が発祥した地として知られ、江戸時代には100軒にも及ぶ醸造元がありました。 |
道の歴史とともに広川町には、今も人々に語り継がれる和歌山の災害の歴史があります。
安政元年、紀伊半島を襲った大津波の被害を軽減するため、
稲むらに火を放って人々を救った浜口梧稜の史話です。
私財を投げ打ってまちの復興や防災に尽力した働きは、
今なおまちを守る防災の考えの基本として受け継がれています。
そして、今年、平成19年4月22日には、「稲むらの火の館」が広川町にオープン。
防災の取り組みの姿勢の象徴として、また新たな名所にもなっています。
 稲むらの火の館 |
 藤白王子(藤白神社) |
街道が生まれ、人々が行き交い、まちが賑わい、当時を偲ぶ多くの歴史文化が現代に継がれるこの地域では、
今も交通の要衝として国道が利用され、暮らしの安全に対する問題が浮上しています。
このため、住民が安心できるまちづくりを目指して、
交通渋滞の緩和や事故危険箇所に対する安全性向上の取り組みが必要です。

 リンク集
リンク集