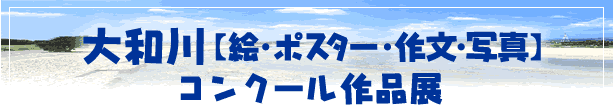
作文部門2
<大和川河川事務所長賞>
「きれいな川を未来に残すために」
今、地球では大変なことが起きています。ごみ問題、大気汚染、さばく化、酸性雨、熱帯雨林の減少、水質汚濁……
実は、この「水質汚染」、私たちの生活と身近な川でも起きているのです。
川は、魚や鳥のすみかで、海とつながっているという、とっても大切な自然です。ところが、その川が、今どんどんよごれているのです。川をよごしている原因はなんなのでしょうか。
現在、日本で最も川をよごしているのは、実は生活はい水なのです。下水道が整っていないところもあり、生活はい水は全体の3分の1は処理できずにそのまま流れてしまっているのです。海や川の近くの工場では有害物質をそのまま流しているところもあります。
また、つりやキャンプで出るつりの糸やはり、ごみなどがすてられています。
川がよごれれば、まず魚や鳥など、川にすむ生き物が被害にあいます。水質の汚染により死んでしまった魚や、つりの糸やはりを鳥が飲みこんで死んでしまうこともあるのです。
また、川は海につながっているので、川をよごせば海をよごすことになるのです。海も、水質汚染や人々がすてたゴミで、生き物たちが命を落としてしまっているのです。しかし、そんな水環境を改善しようと、近年ではいろいろな取り組みが行われています。子どもたちに川の大切さを知ってもらおうとイベントを行ったり、川の水質調査をしたり……。
大阪の川、大和川の水環境はどうなっているのでしょう。調べてみると、日本で最もきたない川だった大和川も、水質調査などいろんな取り組みで、少しずつだけれど、きれいになっているようです。
川は、私たちのくらしに関係するとても大切な自然です。川の自然を守るために、私たちにできることはたくさんあります。おふろの残り湯をせんたくに使ったり、米のとぎじるを植物にあげたり、少しずつやっていくこ
とが大切です。
“きれいな川を未来に残したい”という思いを強くして、自分たちにできることから一生けんめいやっていく。これが、今のわたしたちにあたえられた課題なのだと思います。
<大和川河川事務所長賞>
「私たちの町の大和川」
王寺町立王寺南中学校2年
大和川は人と人とが会話する一つのきっかけを作ってくれる川だと思います。
例えばクリーンキャンペーン。みんなが一生懸命にそうじをしてきれいになった時には、自然と会話が生まれてくるのではないかと思います。
その他にもベルフェスタでいろいろな種類の船を浮かばせて、見る人たちを楽しませてくれたり、川をきれいにすることを心がけた活動など、さまざまな取り組みが行われています。
私はこの前、川のことをもっと知るために、学校で案内された「川を知ろう」というような活動に参加しました。行ってみると思ったより参加者が多く少しおどろきました。大和川以外にもいろんな川を見に行って川の中にすんでいる魚を観察したりして、とてもたのしい一日でした。
そして帰ってきて、あらためて大和川を見ると、私の町にもこんなに大きな川があるんだなあ、もっときれいにしたら町の人々がもっと明るくよりよくなれるんじゃないかな、と思いました。
だからこれからも、ぜひ積極的に、いろんな活動に参加して、たくさんしゃべって、明るい町づくりができたらいいなあと思います。
ポイ捨てをしたり、川をよごすような行為が自然になくなると同時に、人と人とのつながりも深まって、笑顔のあふれるよりよい町になると思います。
大和川は人と人とが会話する一つのきっかけを作ってくれる川だと思います。
例えばクリーンキャンペーン。みんなが一生懸命にそうじをしてきれいになった時には、自然と会話が生まれてくるのではないかと思います。
その他にもベルフェスタでいろいろな種類の船を浮かばせて、見る人たちを楽しませてくれたり、川をきれいにすることを心がけた活動など、さまざまな取り組みが行われています。
私はこの前、川のことをもっと知るために、学校で案内された「川を知ろう」というような活動に参加しました。行ってみると思ったより参加者が多く少しおどろきました。大和川以外にもいろんな川を見に行って川の中にすんでいる魚を観察したりして、とてもたのしい一日でした。
そして帰ってきて、あらためて大和川を見ると、私の町にもこんなに大きな川があるんだなあ、もっときれいにしたら町の人々がもっと明るくよりよくなれるんじゃないかな、と思いました。
だからこれからも、ぜひ積極的に、いろんな活動に参加して、たくさんしゃべって、明るい町づくりができたらいいなあと思います。
ポイ捨てをしたり、川をよごすような行為が自然になくなると同時に、人と人とのつながりも深まって、笑顔のあふれるよりよい町になると思います。
<大和川河川事務所長賞>
「看板を見たなら」
斑鳩町立斑鳩南中学校1年
小学校五年生の夏休みに、私が通っていた小学校で、「ゴミを捨てないで」という看板を作る企画があった。参加、不参加は自由だったが、私は自主的に参加することにした。期間は一週間で毎日九時から十二時ぐらいまでだった。
まずは板に描く絵のスケッチからだった。一日目はそれだけで終了だった。二日目は、自分たちが決めた絵を下書きした。板が十五枚で、参加者は三十人。二人一組になって一つの看板を仕上るのだ。私は、大親友とペアを組んだ。それからは、ペンキで色をぬるばっかりだった。他のペアの作品も見に行ったり、その時間は、とても楽しくて、あっという間に時間が過ぎていってしまった。
最後の日、仕上げにとりかかった。板のうしろに、脚を取り着けるのだ。木を同じ長さに切って、どことどこにつけるのか決め、先生に電動ドライバーでクギを打ってもらった。
できた看板といっしょに、写真も撮った。できたあと、すごく嬉かった。これが大和川に立てられるんだなって思うと、よくがんばったやって自分をほめてあげたくなった。
その日、看板ができたあと、みんなで大和川の川ぞいに看板を立てに行ったらしい。私は別の用事があって、実際に立てられる所は見れなかったが、とても心残りだ。
私たちが心を込めて作った看板は、今でも大和川のほとりに立ててある。大和川の近くを通る時、もしそんな看板があったなら、その看板に心動かされたなら、奈良県民の一人として、大和川をきれいにする活動にご協力願いたい。
奈良県自慢の大和川をみんなの手で救ってみせようじゃないか。助けを求めるこの川を。
小学校五年生の夏休みに、私が通っていた小学校で、「ゴミを捨てないで」という看板を作る企画があった。参加、不参加は自由だったが、私は自主的に参加することにした。期間は一週間で毎日九時から十二時ぐらいまでだった。
まずは板に描く絵のスケッチからだった。一日目はそれだけで終了だった。二日目は、自分たちが決めた絵を下書きした。板が十五枚で、参加者は三十人。二人一組になって一つの看板を仕上るのだ。私は、大親友とペアを組んだ。それからは、ペンキで色をぬるばっかりだった。他のペアの作品も見に行ったり、その時間は、とても楽しくて、あっという間に時間が過ぎていってしまった。
最後の日、仕上げにとりかかった。板のうしろに、脚を取り着けるのだ。木を同じ長さに切って、どことどこにつけるのか決め、先生に電動ドライバーでクギを打ってもらった。
できた看板といっしょに、写真も撮った。できたあと、すごく嬉かった。これが大和川に立てられるんだなって思うと、よくがんばったやって自分をほめてあげたくなった。
その日、看板ができたあと、みんなで大和川の川ぞいに看板を立てに行ったらしい。私は別の用事があって、実際に立てられる所は見れなかったが、とても心残りだ。
私たちが心を込めて作った看板は、今でも大和川のほとりに立ててある。大和川の近くを通る時、もしそんな看板があったなら、その看板に心動かされたなら、奈良県民の一人として、大和川をきれいにする活動にご協力願いたい。
奈良県自慢の大和川をみんなの手で救ってみせようじゃないか。助けを求めるこの川を。
<大和川河川事務所長賞>
「大和川のゴミの問題」
斑鳩町立斑鳩南中学校1年
私は大和川のゴミの問題について書きました。大和川は昔はきれいだったそうですが今は川がゴミの山です。ペットボトルやおかしの包み紙などが捨ててあります。どうしたらこのゴミを減らしていくか、私は考えました。
一度小学生のころにクリーンキャンペーンなどもして少しはゴミを減らしていきました。
かんばんを作ったり、ポスターなども作りました。でもゴミはなかなか減りませんでした。小学校でも呼びかけをしたりもしてみました。
すると役場の人達が「せっかくこのかんばんを作ってくれたんだからどこかに立てようか」と声をかけてくれました。そして、かんばんを立てて一週間ぐらいして見に行くと、なんとかんばんがたおされていました。私達はその時、とてもショックを受けました。中にはちゃんとビニールの様な物でよごれないように工夫されている所もありましたが一生けん命作ったかんばんがたおれていたのはやはり、ショックでした。私はその時にもっと地球の大切さを知ってもらいたいと思いました。川をよごせば魚などが死んでいく。魚だって人間と同じ生き物なのに自分さえよければいいという考えで何十ぴきの魚たちを殺している人がこの地球にはいる。せっかくきれいにしている川がよごれてしまっては遠い所から来た人にココの川はきたないなと思われてしまいます。
もっと一人一人が気づけ合えば、きたなくはなくなるし、魚なども死ななくてすむ、だから私はもっと生活の日常の中で少しでもいいからちょっとした心がけをしていこうと思いました。
私は大和川のゴミの問題について書きました。大和川は昔はきれいだったそうですが今は川がゴミの山です。ペットボトルやおかしの包み紙などが捨ててあります。どうしたらこのゴミを減らしていくか、私は考えました。
一度小学生のころにクリーンキャンペーンなどもして少しはゴミを減らしていきました。
かんばんを作ったり、ポスターなども作りました。でもゴミはなかなか減りませんでした。小学校でも呼びかけをしたりもしてみました。
すると役場の人達が「せっかくこのかんばんを作ってくれたんだからどこかに立てようか」と声をかけてくれました。そして、かんばんを立てて一週間ぐらいして見に行くと、なんとかんばんがたおされていました。私達はその時、とてもショックを受けました。中にはちゃんとビニールの様な物でよごれないように工夫されている所もありましたが一生けん命作ったかんばんがたおれていたのはやはり、ショックでした。私はその時にもっと地球の大切さを知ってもらいたいと思いました。川をよごせば魚などが死んでいく。魚だって人間と同じ生き物なのに自分さえよければいいという考えで何十ぴきの魚たちを殺している人がこの地球にはいる。せっかくきれいにしている川がよごれてしまっては遠い所から来た人にココの川はきたないなと思われてしまいます。
もっと一人一人が気づけ合えば、きたなくはなくなるし、魚なども死ななくてすむ、だから私はもっと生活の日常の中で少しでもいいからちょっとした心がけをしていこうと思いました。
<大和川河川事務所長賞>
「未来に伝えたい大和川」
桜井市立安倍小学校4年
ぼくは、時々お母さんと自転車で買い物に行った帰り道、遠回りをする事があります。それは、川を見たいからです。
近どう百か店から小西橋をわたり、坂をおりてすぐ右に曲がると寺川にそった道があります。とつぜん見はらしがよくなり、夏はすずしい風が吹いて、車も来ないしとても好きな場所です。小さな段差のたきがあって、その流れる水の音を聞くと、気分が
「スー。」
とします。小さな魚も泳いでいます。
ところが、今年の夏、その川を見に行くと草だらけになっていて滝には水が流れていませんでした。いくらさがしても、小さな魚もいなくなっていました。
ぼくは少しがっかりして、お母さんに
「何でこんなことになったの。」
と聞きました。お母さんは、
「上流にダムがあって、流す水の量をかげんしているのと、下水が発達して、小さな川には反対に水が流れなくなったんとちがうか。」
と言いました。
みんなのくらしを守るためのダムと、川をよごさないための下水と、川の水の量のバランスをとる事は、とてもむずかしいとぼくは思います。
でも、やっぱりきれいな水の川がもどって来てほしいし、ぼくたちが大人になってこの道を通った時
「ホッ。」
とできるような場所のままでいてほしいと思います。
ぼくは、時々お母さんと自転車で買い物に行った帰り道、遠回りをする事があります。それは、川を見たいからです。
近どう百か店から小西橋をわたり、坂をおりてすぐ右に曲がると寺川にそった道があります。とつぜん見はらしがよくなり、夏はすずしい風が吹いて、車も来ないしとても好きな場所です。小さな段差のたきがあって、その流れる水の音を聞くと、気分が
「スー。」
とします。小さな魚も泳いでいます。
ところが、今年の夏、その川を見に行くと草だらけになっていて滝には水が流れていませんでした。いくらさがしても、小さな魚もいなくなっていました。
ぼくは少しがっかりして、お母さんに
「何でこんなことになったの。」
と聞きました。お母さんは、
「上流にダムがあって、流す水の量をかげんしているのと、下水が発達して、小さな川には反対に水が流れなくなったんとちがうか。」
と言いました。
みんなのくらしを守るためのダムと、川をよごさないための下水と、川の水の量のバランスをとる事は、とてもむずかしいとぼくは思います。
でも、やっぱりきれいな水の川がもどって来てほしいし、ぼくたちが大人になってこの道を通った時
「ホッ。」
とできるような場所のままでいてほしいと思います。
<大和川河川事務所長賞>
「大和川にタッチ」
奈良市立飛鳥小学校3年
「カシャカシャ、ピカピカー。」
「カシャカシャカシャ、ピカピカピカー。」
今年の三月に大和川水かんきょうサミットがあり、ぼくはさんかしました。その時、北がわ国土交通大じんと知事と市町村長たちとステージの上で、写真をとりました。ものすごくたくさんのシャッター音とまぶしいくらいのフラッシュが光っていました。大じんが、ぼくとお兄ちゃんのかたに、手をおいてくれました。客せきには、八百人ぐらいの人と、たくさんのカメラマンがこっちにカメラを向けていたので、ぼくはびっくりして、にっこりわらう事ができませんでした。サミットは、むずかしい話ばかりだったけど、さい後に川をきれいにするせん言をした事は、わすれません。
四月になり、さほ川ぞいに家ぞくで、お花見に行きました。さくらの木の下でおべん当を食べていると、風にふかれてさくらの花びらがヒラヒラと落ちてきて、ぼくのおにぎりにくっつきました。
「さくらおにぎりのできあがりー。」
と言うと、みんながわらいました。それからさほ川は、大和川へつづくとサミットで、べん強した事を思い出しました。ぼくは大和川の上流のさほ川で遊んでいるので、きれいに後かたづけをして下流の人たちに
タッチして帰ります。
「やっぱりいいよね!大和川。」
と言う声が聞こえてきそうです。
「カシャカシャ、ピカピカー。」
「カシャカシャカシャ、ピカピカピカー。」
今年の三月に大和川水かんきょうサミットがあり、ぼくはさんかしました。その時、北がわ国土交通大じんと知事と市町村長たちとステージの上で、写真をとりました。ものすごくたくさんのシャッター音とまぶしいくらいのフラッシュが光っていました。大じんが、ぼくとお兄ちゃんのかたに、手をおいてくれました。客せきには、八百人ぐらいの人と、たくさんのカメラマンがこっちにカメラを向けていたので、ぼくはびっくりして、にっこりわらう事ができませんでした。サミットは、むずかしい話ばかりだったけど、さい後に川をきれいにするせん言をした事は、わすれません。
四月になり、さほ川ぞいに家ぞくで、お花見に行きました。さくらの木の下でおべん当を食べていると、風にふかれてさくらの花びらがヒラヒラと落ちてきて、ぼくのおにぎりにくっつきました。
「さくらおにぎりのできあがりー。」
と言うと、みんながわらいました。それからさほ川は、大和川へつづくとサミットで、べん強した事を思い出しました。ぼくは大和川の上流のさほ川で遊んでいるので、きれいに後かたづけをして下流の人たちに
タッチして帰ります。
「やっぱりいいよね!大和川。」
と言う声が聞こえてきそうです。