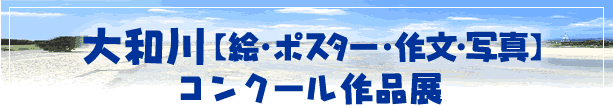
作文部門2
<優秀賞 大和川工事事務所長賞>
「ふるさと大和川」
わたしは、小さいころおじいちゃんと、よく大和川に、遊びに行きました。川の中に入って、土でおしろを、作ったり、川で魚つりをしている人が、パンくずを、入れるのでそれが、流れてきて、そのパンくずを使って魚つりごっこをしたりしました。そのパンくずは、たくさん、流れてきました。そのたびに、わたしたちが、そのパンくずであそびました。
おじいちゃんも、川の中へ入ったので、ちょっとたんけんのような気分で、川のむこうまで行ってみました。そして、わたしが川の水の中に、しずんでいる自転車のタイヤを、へびとまちがえて、「へびがいてる!こわい!」と言って、はなれると、おじいちゃんは「これは、自転車のタイヤやで。」と、教えてくれました。それからまた、歩きはじめた時、大きい、魚を、おじいちゃんが、見つけて、とりました。「もってかえろう」と、わたしと妹が言うと、おじいちゃんは、「車の中は、暑いから、死んでしまうで、だから、もうかえしたろう。」と、言ったので、わたしと、妹は、あきらめました。もう一度あのわたしと妹が、作ったおしろを、見に行くと、まだ、つぶれていなかったので「よかったね。」と妹とわたしが、言いました。今度は、おしろのまわりに、ほりを、作りはじめました。そのほりは、川の水につたわっていきました。水が、ほりの中に入りはじめました。わたしと妹は、うれしいのと、楽しいので、ずっと、ほりを、深くしました。今度は、ちがう場所に、行きました。そこには、水が、たまっていて、わたしが、ぱっと見た時、水が、にじ色になっていたので「これなに?」と、わたしが、きくとおじいちゃんは、「油が、うかんでるだけや。」と、言ってくれました。
大和川のことは、ずっとわすれていません。
<優秀賞 大和川工事事務所長賞>
「大和川をきれいに」
大和高田市立磐園小学校6年
大和川は、奈良県の北部から、大阪湾へ流れこんでいる川です。お父さんから、工場排水や、家庭排水などが原因でとてもよごれていると聞いて、五年の時勉強したように、工場排水の問題は、とても重大なことだと思いました。
今、日本では、少しずつ「自然破かいをやめよう」という声が多くなってきているようです。まだ、お父さんのこどものころのような野山の様子にはなっていないけれど、一人ひとりが自然を大切にして、自分から自然を守ろうというふうに考えるようになったら、自然がもとにもどる日も、そう遠くはないと思います。
私は「自然」についてもう一度考え直してみました。まず、自然というのは、いろいろな物の関係で成り立っています。だから、一度に、自然をもとにもどすのは無理だと思います。
今、私の一番身近にある川について考えてみました。私たちの市を流れている高田川は、大和川につながっています。この川は、とてもきれいだとはいえません。確かに、春になると桜が満開になり、あたり一面すばらしい風景にかわりますが、川の水は、汚れています。私はいつも、なんとかならないものだろうかと考えさせられます。川にごみを捨てないこと、下水の処理をきちんとすることなど、みんなが、川を大切にする心をもっていれば、自然は、もとにもどっていくと思います。だから、私は身近な川から自然をとりもどしていき、その川が通じている大和川、そして日本中の川がきれいになるようにしたいです。
お父さんの子供の頃は、川はとてもきれいで泳げたと聞きました。私も自分の子供に自然の中で遊んだ話をしてあげたいのです。だから、私たちは、これからそんな川がもどってくるように努力していきたいと思います。
大和川は、奈良県の北部から、大阪湾へ流れこんでいる川です。お父さんから、工場排水や、家庭排水などが原因でとてもよごれていると聞いて、五年の時勉強したように、工場排水の問題は、とても重大なことだと思いました。
今、日本では、少しずつ「自然破かいをやめよう」という声が多くなってきているようです。まだ、お父さんのこどものころのような野山の様子にはなっていないけれど、一人ひとりが自然を大切にして、自分から自然を守ろうというふうに考えるようになったら、自然がもとにもどる日も、そう遠くはないと思います。
私は「自然」についてもう一度考え直してみました。まず、自然というのは、いろいろな物の関係で成り立っています。だから、一度に、自然をもとにもどすのは無理だと思います。
今、私の一番身近にある川について考えてみました。私たちの市を流れている高田川は、大和川につながっています。この川は、とてもきれいだとはいえません。確かに、春になると桜が満開になり、あたり一面すばらしい風景にかわりますが、川の水は、汚れています。私はいつも、なんとかならないものだろうかと考えさせられます。川にごみを捨てないこと、下水の処理をきちんとすることなど、みんなが、川を大切にする心をもっていれば、自然は、もとにもどっていくと思います。だから、私は身近な川から自然をとりもどしていき、その川が通じている大和川、そして日本中の川がきれいになるようにしたいです。
お父さんの子供の頃は、川はとてもきれいで泳げたと聞きました。私も自分の子供に自然の中で遊んだ話をしてあげたいのです。だから、私たちは、これからそんな川がもどってくるように努力していきたいと思います。
<優秀賞 大和川工事事務所長賞>
「やまとがわ」
大阪市立矢田小学校2年
やまとがわでおよぎたいねん
みずきたないから
いややねん
やまとがわで
およぎたいねん
やまとがわでおよぎたいねん
みずきたないから
いややねん
やまとがわで
およぎたいねん
<優秀賞 大和川工事事務所長賞>
「大和川をきれいに」
大和高田市立磐園小学校6年
大和川は、奈良県の、笠置山のふもとから、ほとんど横一文字に大阪湾に流れこんでいる川です。地図で、位置を確認してから、川の状況を資料で調べてみることにしました。そして、美しい川といえるほどではないことを知りました。
ぼくは、大和川へは、行ったことがありませんが、調べた資料に、写真もでていたので、それを見たら、とても清らかな水とは言えないなと思いました。
以前、島根県の山の中で、とても清らかな水が流れている小川がありました。その川には、魚がたくさん泳いでいて、さわがにもいました。そんな川に、大和川がなればと思っています。
それには、どうしたらいいのか、ぼくは、考えました。そして、考えた結果、みんなが大和川にゴミを投げ捨てたり、下水を流したりしないでみんな、協力して、川を美しくしようと計画を立て、それを実行していくのがいいと思いついたのです。ぼくの考えついたことは、わかりきったことなのです。しかし、こんな簡単なことができないのです。よく、簡単なことほど、見失いがちだと言われますが、本当にそのとおりなのだと思いました。しかし、ぼくは、今、強く訴えます。
これは、大和川だけでなく、他の川でもいえることだと思いました。そして、このことが実行できれば、日本の川は、とても美しく清らかな川になると思いました。日本は、水が豊かな、四季のはっきりした緑の多い国です。その自然の風景に、川はなくてはならないものです。川を美しくすることは、日本の国を美しくすることなのです。
ぼくたちは、今、そのことに気づき、立ち上がらなければならないのです。川を美しくする計画を立て、それを実行にうつしていかなければならないと思いました。
大和川は、奈良県の、笠置山のふもとから、ほとんど横一文字に大阪湾に流れこんでいる川です。地図で、位置を確認してから、川の状況を資料で調べてみることにしました。そして、美しい川といえるほどではないことを知りました。
ぼくは、大和川へは、行ったことがありませんが、調べた資料に、写真もでていたので、それを見たら、とても清らかな水とは言えないなと思いました。
以前、島根県の山の中で、とても清らかな水が流れている小川がありました。その川には、魚がたくさん泳いでいて、さわがにもいました。そんな川に、大和川がなればと思っています。
それには、どうしたらいいのか、ぼくは、考えました。そして、考えた結果、みんなが大和川にゴミを投げ捨てたり、下水を流したりしないでみんな、協力して、川を美しくしようと計画を立て、それを実行していくのがいいと思いついたのです。ぼくの考えついたことは、わかりきったことなのです。しかし、こんな簡単なことができないのです。よく、簡単なことほど、見失いがちだと言われますが、本当にそのとおりなのだと思いました。しかし、ぼくは、今、強く訴えます。
これは、大和川だけでなく、他の川でもいえることだと思いました。そして、このことが実行できれば、日本の川は、とても美しく清らかな川になると思いました。日本は、水が豊かな、四季のはっきりした緑の多い国です。その自然の風景に、川はなくてはならないものです。川を美しくすることは、日本の国を美しくすることなのです。
ぼくたちは、今、そのことに気づき、立ち上がらなければならないのです。川を美しくする計画を立て、それを実行にうつしていかなければならないと思いました。
<優秀賞 大和川工事事務所長賞>
「ふるさと大和川」
賢明学院中学校2年
大和川は、わがふるさと大阪では、淀川につぎ、二番目に長い川です。と、同時に日本の川の中で、きたなさの順位が三本の指の中にはいってしまうというくらい、よごれきっています。そして、大和川をこんなにまできたなくしてしまったのは、ほかでもないこの私たち人間なのです。それなのに私たち人間は、この川をけっして元の美しい川にもどそうと努力しません。その中でも、特に大阪に住んでいる人はずるいと思います。
それは、私達大阪に住んでいる人達は、現在びわこの水を飲料水としています。また私達がこの水を使って生活していけるのはびわこのふ近に住む人達の気くばりともいえることだと思います。びわこのふ近に住んでいる人達は、少しでもびわこをよごさないでおこうと、できるだけ洗ざいをつかわないで、ほとんど石けんであらったりしているのにそれにもかかわらず私たち大阪にすんでいる人達はすきほうだい洗ざいなどを使いまくっています。だから私は大阪に住んでいる人達はずるいといっているのです。何の努力もしないで私達のふるさとの川の水をのまずによその県の水をのむなんて少し、なさけないように感じられます。
外の国では水という資源はあまりなくて、高いお金で水を買ったりしているのにそれにくらべて、水という資源にめぐまれているのだからもっと、もっと有効に使えばいいと思います。
今では、あんなによごれきった大和川も、昔は、国民が飲料水にしていたのだから、そのころの大和川をとりもどしたいと思います。
そのためには、長い年月とみんなの努力が必要だと思います。
だけど、それだけたくさんの努力をして、元の美しい大和川にすることこそ、「我がふるさと大和川」ではないかと思います。
みんなで協力して、美しい元のすがたに大和川をもどしたいです。
大和川は、わがふるさと大阪では、淀川につぎ、二番目に長い川です。と、同時に日本の川の中で、きたなさの順位が三本の指の中にはいってしまうというくらい、よごれきっています。そして、大和川をこんなにまできたなくしてしまったのは、ほかでもないこの私たち人間なのです。それなのに私たち人間は、この川をけっして元の美しい川にもどそうと努力しません。その中でも、特に大阪に住んでいる人はずるいと思います。
それは、私達大阪に住んでいる人達は、現在びわこの水を飲料水としています。また私達がこの水を使って生活していけるのはびわこのふ近に住む人達の気くばりともいえることだと思います。びわこのふ近に住んでいる人達は、少しでもびわこをよごさないでおこうと、できるだけ洗ざいをつかわないで、ほとんど石けんであらったりしているのにそれにもかかわらず私たち大阪にすんでいる人達はすきほうだい洗ざいなどを使いまくっています。だから私は大阪に住んでいる人達はずるいといっているのです。何の努力もしないで私達のふるさとの川の水をのまずによその県の水をのむなんて少し、なさけないように感じられます。
外の国では水という資源はあまりなくて、高いお金で水を買ったりしているのにそれにくらべて、水という資源にめぐまれているのだからもっと、もっと有効に使えばいいと思います。
今では、あんなによごれきった大和川も、昔は、国民が飲料水にしていたのだから、そのころの大和川をとりもどしたいと思います。
そのためには、長い年月とみんなの努力が必要だと思います。
だけど、それだけたくさんの努力をして、元の美しい大和川にすることこそ、「我がふるさと大和川」ではないかと思います。
みんなで協力して、美しい元のすがたに大和川をもどしたいです。
<優秀賞 大和川工事事務所長賞>
「大和川」
奈良女子大学附属小学校4年
わたしは、いろいろな川を見てみるとすぐにきたない川に気がつきました。そして大和川はあきかんなどのゴミがたくさんありました。一度、社会の時間にグループに分かれてあきかん拾いをしました。すごくたくさんのあきかんが見つかりました。その時に、思った事は、だいぶ前からあるのと、最近の物とのあきかんのく別がつきました。どうしてかというと前からあるのは、きたなくて、ぺちゃんこになっているからです。だから、だれかが落ちているのを見つけても拾ってゴミばこまでもっていかなかったのでみんなしらんふりして通りすぎてそしてそんな古いあきかんまでが見つかりました。お父さんに聞いたところ、
「むかしはどこの川でも泳いでいた。そしてどじょうやふなもたくさんいたんだよ。」
と言ってくれました。そんなに楽しく遊んでいたのに今では。とお父さんはつぶやいていました。わたし達はそんなたいけんをしていません。だからこれからでもわたしたちだけで協力しあってむかしみたいにきれいな川をつくっていきたいです。そして川をみんなでよごしていくと生活にこまるのでみんなでよごすんじゃなくてみんなできれいにしたいです。川の中も虫たちが住みやすいところでして、川原もきれいにしたいです。川の気もちもみんな考えたらいいと思います。川もきっと命をもっているのでみんなとその気もちを分かってあげて一日も早くきれいな川にしていきたいです。
わたしは、いろいろな川を見てみるとすぐにきたない川に気がつきました。そして大和川はあきかんなどのゴミがたくさんありました。一度、社会の時間にグループに分かれてあきかん拾いをしました。すごくたくさんのあきかんが見つかりました。その時に、思った事は、だいぶ前からあるのと、最近の物とのあきかんのく別がつきました。どうしてかというと前からあるのは、きたなくて、ぺちゃんこになっているからです。だから、だれかが落ちているのを見つけても拾ってゴミばこまでもっていかなかったのでみんなしらんふりして通りすぎてそしてそんな古いあきかんまでが見つかりました。お父さんに聞いたところ、
「むかしはどこの川でも泳いでいた。そしてどじょうやふなもたくさんいたんだよ。」
と言ってくれました。そんなに楽しく遊んでいたのに今では。とお父さんはつぶやいていました。わたし達はそんなたいけんをしていません。だからこれからでもわたしたちだけで協力しあってむかしみたいにきれいな川をつくっていきたいです。そして川をみんなでよごしていくと生活にこまるのでみんなでよごすんじゃなくてみんなできれいにしたいです。川の中も虫たちが住みやすいところでして、川原もきれいにしたいです。川の気もちもみんな考えたらいいと思います。川もきっと命をもっているのでみんなとその気もちを分かってあげて一日も早くきれいな川にしていきたいです。
<優秀賞 大和川工事事務所長賞>
「ふるさと大和川」
賢明学院中学校3年
-大和川-、今は、日本の中で汚い川としてワースト5に入っています。平気で空カンやゴミを捨てていっています。そして家庭用水、工業用水を流し込むのでますます汚くなる一方です。私の母の子供の頃の話をよく聞きました。大和川で泳げたそうです。ほんの30~40年前までは、大和川は泳げるほどきれいな水だったのです。母の生まれたのは戦後です。だから日本は、これから経済大国へと進んでいく時期だったのです。日本が、先進工業国で、又、経済大国で、日本という国が発展すれば、そのことに伴って川も汚くなっていかなければならないのでしょうか。
本来、川は自然の一部としてみんなの心をなぐさめて、そしてみんなの役に立って、そういった存在だったのに、今は大和川にそういう言葉は似合わなくなってしまいました。
大和川は、そして全ての川は、あらゆるものの源となって、そしてそれらの上に日本という経済大国が成り立っています。だからこれからは、ゴミを捨てないように、大和川をみんなの共同のゴミ捨て場としないように、少しずつきれいに、みんなで守ってあげましょう。
-大和川-、今は、日本の中で汚い川としてワースト5に入っています。平気で空カンやゴミを捨てていっています。そして家庭用水、工業用水を流し込むのでますます汚くなる一方です。私の母の子供の頃の話をよく聞きました。大和川で泳げたそうです。ほんの30~40年前までは、大和川は泳げるほどきれいな水だったのです。母の生まれたのは戦後です。だから日本は、これから経済大国へと進んでいく時期だったのです。日本が、先進工業国で、又、経済大国で、日本という国が発展すれば、そのことに伴って川も汚くなっていかなければならないのでしょうか。
本来、川は自然の一部としてみんなの心をなぐさめて、そしてみんなの役に立って、そういった存在だったのに、今は大和川にそういう言葉は似合わなくなってしまいました。
大和川は、そして全ての川は、あらゆるものの源となって、そしてそれらの上に日本という経済大国が成り立っています。だからこれからは、ゴミを捨てないように、大和川をみんなの共同のゴミ捨て場としないように、少しずつきれいに、みんなで守ってあげましょう。
<優秀賞 大和川工事事務所長賞>
「大和川の顔」
王寺町立王寺小学校5年
「春」「夏」「秋」「冬」
この季節の中で一番いい顔してる川は春です。
私の家は、大和川にそって建っています。習い物など行くときは、いつも川を見ながら歩いていきます。いつも思うことは、どうしてこんなに川がにごったのかなあと思います。おじいちゃんに聞いてみると、昔は大和川で水泳をしていたこともあったんだよ。とおしえてくれました。春は、ゆるやかですきとおった川、やさしい顔。
梅雨には、水がまし、にごり、おそろしい顔。
秋には、川は、おちつきをもたせてくれる。
冬は、雪が積もり、雪がとける時には日光を浴びとてもきれいな川。
川にも季節によっていろいろな顔があるということがわかる。
もし仮に日本に川がなかったらどうだろうか?。今飲んでいる水も、飲めなくなったり、季節による川の顔も見れなくなるし、また、きれいだなあと思うこともなくなるだろう。もし川がなかったら……ということを考えれば、一人一人がむだなごみをださないようにする心がけが必要だと思う。
一人一人がそういうことに注意すれば、いつもいい顔をしている、大和川が見れると思います。
「春」「夏」「秋」「冬」
この季節の中で一番いい顔してる川は春です。
私の家は、大和川にそって建っています。習い物など行くときは、いつも川を見ながら歩いていきます。いつも思うことは、どうしてこんなに川がにごったのかなあと思います。おじいちゃんに聞いてみると、昔は大和川で水泳をしていたこともあったんだよ。とおしえてくれました。春は、ゆるやかですきとおった川、やさしい顔。
梅雨には、水がまし、にごり、おそろしい顔。
秋には、川は、おちつきをもたせてくれる。
冬は、雪が積もり、雪がとける時には日光を浴びとてもきれいな川。
川にも季節によっていろいろな顔があるということがわかる。
もし仮に日本に川がなかったらどうだろうか?。今飲んでいる水も、飲めなくなったり、季節による川の顔も見れなくなるし、また、きれいだなあと思うこともなくなるだろう。もし川がなかったら……ということを考えれば、一人一人がむだなごみをださないようにする心がけが必要だと思う。
一人一人がそういうことに注意すれば、いつもいい顔をしている、大和川が見れると思います。
<優秀賞 大和川工事事務所長賞>
「むかしの大和川」
大阪市立矢田西中学校1年
大和川をそうじしに行った時、ずっと前よりすこしきれいになっていたと思う。小学校の時大和川に遊びに行った時川の中にバイクがおちていたりぶたの死体が流れていたりしてたのを見た事があるからだ。バイクなんて何を思って川の中にすてているんかな。
魚をとりに行った時はごみがたくさんとれたからうっとしかったけど金魚がとれた。その金魚はほっぺがふくらんでいるすいほうがんと言う名前だ。だけどおなかがまっ青だったからたぶん病気をもっていると思って川ににがした。ほかにあさい所なんかに大きなコイがあばれていたからふかい所にやったりした。すごくびっくりしたことは大きな金色のコイがぴょんぴょんはねてたことだ。そのコイをねらって長い時間をかけてずっとつりをしてたこともあったし、かにをとってたこともあった。かにと言ってもと十センチぐらいの大きさだった。今はいくらさがしてもいないと思う。
今家でかめを二ひきかっている。そのかめはかったんじゃあなくて大和川でつかまえたやつだ。一ぴきはこうらがわれている。もう一ぴきはどてすべりしてる時に川をみたらおおきなかめがおったからつかまえてかっている。ほかにもかめをつかまえたことがあるけどうじ虫がかめの体にすみついていたのでぼうでおっぱらおうと思ってすこしやったけどきもち悪いからやめた。もっと川をきれいにしたらいいのに。
みんなで川のまん中の島を二つにわってダムをつくったりその場所に行ける道をつくったりした。その道は一つまちがえれば川の中にはまってしまう。たけし城のりゅう神の池みたいなやつだ。ほかにも色々大和川と遊んだけど今はもうそういうことはあまりできない。もっと川をきれいにしてもっと色々遊びたい。
大和川をそうじしに行った時、ずっと前よりすこしきれいになっていたと思う。小学校の時大和川に遊びに行った時川の中にバイクがおちていたりぶたの死体が流れていたりしてたのを見た事があるからだ。バイクなんて何を思って川の中にすてているんかな。
魚をとりに行った時はごみがたくさんとれたからうっとしかったけど金魚がとれた。その金魚はほっぺがふくらんでいるすいほうがんと言う名前だ。だけどおなかがまっ青だったからたぶん病気をもっていると思って川ににがした。ほかにあさい所なんかに大きなコイがあばれていたからふかい所にやったりした。すごくびっくりしたことは大きな金色のコイがぴょんぴょんはねてたことだ。そのコイをねらって長い時間をかけてずっとつりをしてたこともあったし、かにをとってたこともあった。かにと言ってもと十センチぐらいの大きさだった。今はいくらさがしてもいないと思う。
今家でかめを二ひきかっている。そのかめはかったんじゃあなくて大和川でつかまえたやつだ。一ぴきはこうらがわれている。もう一ぴきはどてすべりしてる時に川をみたらおおきなかめがおったからつかまえてかっている。ほかにもかめをつかまえたことがあるけどうじ虫がかめの体にすみついていたのでぼうでおっぱらおうと思ってすこしやったけどきもち悪いからやめた。もっと川をきれいにしたらいいのに。
みんなで川のまん中の島を二つにわってダムをつくったりその場所に行ける道をつくったりした。その道は一つまちがえれば川の中にはまってしまう。たけし城のりゅう神の池みたいなやつだ。ほかにも色々大和川と遊んだけど今はもうそういうことはあまりできない。もっと川をきれいにしてもっと色々遊びたい。
<優秀賞 大和川工事事務所長賞>
「ふるさと大和川」
川西町三宅町中学校組合立式下中学校2年
ぼくは奈良県のほぼ中央、三宅町にすんでいる。となりの町の川西町に大和川が流れている。しかし、ぼくの知っている大和川ははっきり言ってきたないと思う。
昔、大和川もすごくきれいで泳げるほどだったのに、それなのに今の大和川はどうだ、水は汚いし、ゴミはういているわそれに第一水がくさい。
なぜそれほどまでに汚くなったのか。
それは、おもにぼく達私達の生活用水それに、工場が増えたからである。なぜ、これらが原因かそれは、ぼく達が粉石けんを使わずに、合成洗剤を使ったり、油をそのまま流したりする所に問題がある。なぜ問題かと言うと粉石けんだと、流してもそれを分解してくれるプランクトンがいるからである。反対に合成洗剤がだめなのは、そのプランクトンを殺し水を汚すからである。
それと工業用水が問題なのは、これもそのままたれ流ししていることである。たれ流しすればこれもまた、水が汚れてしまう。
川の汚染を食い止めるには、まずできるだけ粉石けんを使って、できるだけが合成洗剤を使わない。それと無秩序な開発を厳しく規制することが肝要である。人間の手によって汚され、汚染された大和川を再びきれいな大和川にするためにあらゆる努力を払うことこそわたしたちがなさねばならない後世への責務なのである。
ぼくは奈良県のほぼ中央、三宅町にすんでいる。となりの町の川西町に大和川が流れている。しかし、ぼくの知っている大和川ははっきり言ってきたないと思う。
昔、大和川もすごくきれいで泳げるほどだったのに、それなのに今の大和川はどうだ、水は汚いし、ゴミはういているわそれに第一水がくさい。
なぜそれほどまでに汚くなったのか。
それは、おもにぼく達私達の生活用水それに、工場が増えたからである。なぜ、これらが原因かそれは、ぼく達が粉石けんを使わずに、合成洗剤を使ったり、油をそのまま流したりする所に問題がある。なぜ問題かと言うと粉石けんだと、流してもそれを分解してくれるプランクトンがいるからである。反対に合成洗剤がだめなのは、そのプランクトンを殺し水を汚すからである。
それと工業用水が問題なのは、これもそのままたれ流ししていることである。たれ流しすればこれもまた、水が汚れてしまう。
川の汚染を食い止めるには、まずできるだけ粉石けんを使って、できるだけが合成洗剤を使わない。それと無秩序な開発を厳しく規制することが肝要である。人間の手によって汚され、汚染された大和川を再びきれいな大和川にするためにあらゆる努力を払うことこそわたしたちがなさねばならない後世への責務なのである。