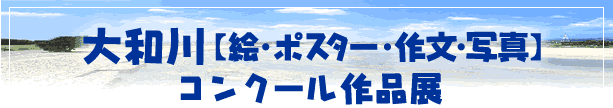
作文部門1
<金賞 大阪府知事賞>
「ぼくの大和川」
大阪教育大学教育学部附属平野中学校1年
「水は流れる大和川、うつすさやかな雲の色、さあみんな、この清らかな流れの岸に力を合わせてやすみなく、みなぎって行こう、水のように。」と、ぼくの卒業した小学校の校歌に歌われているように、ぼくにとって大和川は、なじみのある心のふるさとのような存在だ。川原でのたこあげ、すすきとり、そして花火。流れは、ぼく達をいつもあたたかく見守ってくれている。川といえば大和川なのである。
さて、今年の夏、うれしいニュースがあった。
「大和川の水質が、少しずつ改善されてきました。二年連続ワースト1から二位に転じて…今年の調査では…」
ラジオだったので、くわしくは聞きとれなかったが、とにかくぼくにとってはビッグニュースだった。そして、それをさらにうらづけるように、こんな話題をテレビで伝えていた。
「大和川に流れ込む奈良市の佐保川では、よごれの代名詞になっていた水生生物サホコカゲロウがほとんど姿を消そうとしています。それに変わって清流に住むカワニナが確認されるようになりました。これは、近くに住んでいる人々の地道な清掃活動と行政、企業とのとりくみの成果といえます。」
このように、大和川の水質が少しずつ浄化されている。しかし、まだまだ油断はできない。自然破壊、環境破壊は、人間のちょっとしたすきをみのがしたりしないからだ。すぐにもとにもどってしまう。
淀川とともに、その流れによって大阪の平野を作り、ぼく達のくらしや田畑に必要な水をもたらしてきた歴史ある大切な川、大和川。これからも、この川を守り続け、未来に残していくことは、ぼく達一人一人の責任だ。
<金賞 奈良県知事賞>
「若草橋の上から」
三郷町立三郷中学校3年
空き缶、お菓子の袋、誰かの靴…。若草橋の上から大和川を見ると、次から次へといろんな物が流れてきた。川の魚達は、そのゴミを避けるようにみんな端っこで泳いでいた。
「魚も大変やろな。」
と私は思った。
なぜなら、自分達の川なのに真ん中で、堂々と泳げない。もし泳いでみたとしても、後ろから流れてくる空き缶にぶつかったり、すっぽりお菓子の袋の中に入ってしまうかもしれないと思ったからだ。
この前友達と興味半分で、初めて大和川に足を入れた。始めは汚いと思って怖かったけど、ちゃんと水を通して足が見えた、もちろん足の下にある石も砂も。
今、大和川沿いに住んでいる人達みんながゴミ拾いをしたら「日本一汚い川」が「日本一きれいな川」になるのではないかなとその時本当に思った。
でもその日家に帰って、お風呂場で足を洗おうと思ったら、足がくさかった。自分の足くさいのではなくて、足が大和川のゴミ臭かったのだ。その時は、なぜだか分からないけど、ショックだった。きっと、
「大和川はみんなでがんばっても、きれいにならないんじゃないかな。」と考えたからだと思う。けれども、
「今なら、まだ間に合う。」
ともその時思った。
なぜなら、あの時川の魚は一生懸命がんばって泳いでいたからだ。
今がんばらなければこの先、もっともっと川は汚くなるし、川に住んでいる生き物も減っていってしまうと思う。
いつか若草橋の上から、
「『大和川に入って泳ぎたい。』と思う日が来るといいのにな。」
と思った。
空き缶、お菓子の袋、誰かの靴…。若草橋の上から大和川を見ると、次から次へといろんな物が流れてきた。川の魚達は、そのゴミを避けるようにみんな端っこで泳いでいた。
「魚も大変やろな。」
と私は思った。
なぜなら、自分達の川なのに真ん中で、堂々と泳げない。もし泳いでみたとしても、後ろから流れてくる空き缶にぶつかったり、すっぽりお菓子の袋の中に入ってしまうかもしれないと思ったからだ。
この前友達と興味半分で、初めて大和川に足を入れた。始めは汚いと思って怖かったけど、ちゃんと水を通して足が見えた、もちろん足の下にある石も砂も。
今、大和川沿いに住んでいる人達みんながゴミ拾いをしたら「日本一汚い川」が「日本一きれいな川」になるのではないかなとその時本当に思った。
でもその日家に帰って、お風呂場で足を洗おうと思ったら、足がくさかった。自分の足くさいのではなくて、足が大和川のゴミ臭かったのだ。その時は、なぜだか分からないけど、ショックだった。きっと、
「大和川はみんなでがんばっても、きれいにならないんじゃないかな。」と考えたからだと思う。けれども、
「今なら、まだ間に合う。」
ともその時思った。
なぜなら、あの時川の魚は一生懸命がんばって泳いでいたからだ。
今がんばらなければこの先、もっともっと川は汚くなるし、川に住んでいる生き物も減っていってしまうと思う。
いつか若草橋の上から、
「『大和川に入って泳ぎたい。』と思う日が来るといいのにな。」
と思った。
<金賞 近畿地方建設局長賞>
「大和川の昔と未来」
堺市立登美丘東小学校4年
大和川は、奈良県の笠置山を水源地とし、大和ぼん地で、小さな川を集め、大阪わんへとそそぐ、一級かせんです。
川の流れにそった地いきの面積は、一〇七〇平方キロメートルで、川の流れにそった地いき内の人口は、二百万人になります。
人類は、大昔から、川にそって、文明を作りあげ、川のめぐみにより発てんしてきました。
大和川も清流でした。川は昔より自分で自分をきれいにする事ができます。川は瀬とふちのくり返しで、こう成され、瀬では、さんそをとりこみ多数の生物を、生息させ、それらの生物が、水中のよごれた物質を食べたり、吸着することにより水を、きれいにします。ふちでは生物に食べたり吸着されず残った物がしずみ、きれいな水が得られます。このくりかえしによって川の自浄作用は続けられるのです。
しかし時代は流れ、私たちは、川を生活排水の捨て場として利用してまいました。川はよごされ本来の美しさをわすれてしまいました。大和川も、例外ではありません。平成7年には、全国一級河川の中で、水質ワースト・1位になってしまいました。
大阪府は21世紀を目ざし、下水道整びや工場排水きせいなどの河川浄化に取り組んでいるそうです。私たちが流いきに住む人たちも子孫に美しい川を残すため努力したいと思います。米のとぎ汁や煮物の汁は、意外と水をよごします。とぎ汁は草木にやり、煮物は食べる量だけを作りましょう。使用済みの油は新聞紙に吸わせるなどしてごみとして出しましょう。洗ざいは、つかいすぎないようにしましょう。川が気持ちのゆとりを持たせていた。かつての水の都大阪をもう一度、見てみたいと思います。
大和川は、奈良県の笠置山を水源地とし、大和ぼん地で、小さな川を集め、大阪わんへとそそぐ、一級かせんです。
川の流れにそった地いきの面積は、一〇七〇平方キロメートルで、川の流れにそった地いき内の人口は、二百万人になります。
人類は、大昔から、川にそって、文明を作りあげ、川のめぐみにより発てんしてきました。
大和川も清流でした。川は昔より自分で自分をきれいにする事ができます。川は瀬とふちのくり返しで、こう成され、瀬では、さんそをとりこみ多数の生物を、生息させ、それらの生物が、水中のよごれた物質を食べたり、吸着することにより水を、きれいにします。ふちでは生物に食べたり吸着されず残った物がしずみ、きれいな水が得られます。このくりかえしによって川の自浄作用は続けられるのです。
しかし時代は流れ、私たちは、川を生活排水の捨て場として利用してまいました。川はよごされ本来の美しさをわすれてしまいました。大和川も、例外ではありません。平成7年には、全国一級河川の中で、水質ワースト・1位になってしまいました。
大阪府は21世紀を目ざし、下水道整びや工場排水きせいなどの河川浄化に取り組んでいるそうです。私たちが流いきに住む人たちも子孫に美しい川を残すため努力したいと思います。米のとぎ汁や煮物の汁は、意外と水をよごします。とぎ汁は草木にやり、煮物は食べる量だけを作りましょう。使用済みの油は新聞紙に吸わせるなどしてごみとして出しましょう。洗ざいは、つかいすぎないようにしましょう。川が気持ちのゆとりを持たせていた。かつての水の都大阪をもう一度、見てみたいと思います。
<金賞 近畿地方建設局長賞>
「私は大和川」
三郷町立三郷北小学校6年
私は大和川の水だ。しかし、私はただの大和川の水ではない。昔の、きれいな大和川の水だ。魚がたくさんいて人間たちは夏になると私と一緒になって遊んでいた。私の中にはいろんな生き物がいた。私の中で産まれ、育っていった。私は楽しかった。いつもにぎやかだった。私はとてもきれな水だった。
だが、今私は悲しい。なぜならば人間たちのせいで私は汚くなってしまった。昔、私と人間たちの仲はうまくいっていた。しかし、いつの頃からか人間達は私を『ゴミ捨て場』のようにあつかっていた。いろんな物を私の中に捨てた。野菜のくずや木のくずの時はまだ良かった。人間は自分達が汚した水や自然界には無い化学物質で汚れた水を私の中に流し始めた。私の中で元気よく泳いでいた魚がどんどんへってきた。小さな生物ももちろんへってしまった。人間達も泳げるような水ではなくなってしまった。私はとてもさびしくなった。
最初、私はただの一滴の水だった。仲間がしだいに集まり旅を続け、細い流れがやがて大きな大和川になった。
みんな、覚えていて、私も生きている。
たかが川なんて言わないで
川を汚さないで……。
私は長い間待っていた。人間達が気付いてくれるのを。
そして少しずつだけれど人間達は気付いてくれた。私をきれいにしてくれるようになった。でもまだ気付かずに私を汚していく人間もいる。だけど私は、希望をもっている。私をきれいにしようと努力してくれる人がいる限り、私はきっと昔のあのきれいな大和川に戻れるだろう。いやきっと戻れるはずだ。
私は大和川の水だ。しかし、私はただの大和川の水ではない。昔の、きれいな大和川の水だ。魚がたくさんいて人間たちは夏になると私と一緒になって遊んでいた。私の中にはいろんな生き物がいた。私の中で産まれ、育っていった。私は楽しかった。いつもにぎやかだった。私はとてもきれな水だった。
だが、今私は悲しい。なぜならば人間たちのせいで私は汚くなってしまった。昔、私と人間たちの仲はうまくいっていた。しかし、いつの頃からか人間達は私を『ゴミ捨て場』のようにあつかっていた。いろんな物を私の中に捨てた。野菜のくずや木のくずの時はまだ良かった。人間は自分達が汚した水や自然界には無い化学物質で汚れた水を私の中に流し始めた。私の中で元気よく泳いでいた魚がどんどんへってきた。小さな生物ももちろんへってしまった。人間達も泳げるような水ではなくなってしまった。私はとてもさびしくなった。
最初、私はただの一滴の水だった。仲間がしだいに集まり旅を続け、細い流れがやがて大きな大和川になった。
みんな、覚えていて、私も生きている。
たかが川なんて言わないで
川を汚さないで……。
私は長い間待っていた。人間達が気付いてくれるのを。
そして少しずつだけれど人間達は気付いてくれた。私をきれいにしてくれるようになった。でもまだ気付かずに私を汚していく人間もいる。だけど私は、希望をもっている。私をきれいにしようと努力してくれる人がいる限り、私はきっと昔のあのきれいな大和川に戻れるだろう。いやきっと戻れるはずだ。
<銀賞 堺市長賞>
「庶民の川・大和川」
賢明学院中学校1年
大阪の二大河川、淀川と大和川
大阪市と堺市の境を流れる大和川は、まさに庶民の川である。上水道源・工場用水源・放水路と、生活にかかせない川である。
昔、母は八尾の大和川で泳いだという。とても、きれいだったそうだ。今も、上流では泳げるだろうが、私の住む堺では無理だと思う。
難波へ行き来する度に見るだけの大和川であったが、先日、常磐町三丁の堤防から、川岸に降りてみた。堤防には、雑草が生い茂り、キリギリスが鳴いていた。岸辺は砂地で気持ち良い感触がした。川は全体に浅く見え、向う岸まで歩いてゆけそうな気がした。
中州のようなところへサギが降りてきて、エサをついばんでいる。岸辺にも、メダカやタニシがいる。水が結構、澄んでいる。
こう書くと、とてもきれいな川を想像するだろうか、橋げたや岸辺には、空缶、ポリ袋などのゴミが打ちよせられ、たき火、花火の跡、犬のフン、果てには粗大ゴミの捨て場となり、汚く、臭い川となっている。常磐町周辺が、文化住宅、マンション、アパート、工場と立ち並ぶ下町だとしても、大和川流域の土地柄はそう大きく変わらないと思う。
水の都「大阪」にふさわしい川にするために出来る事はなんだろう。
生活排水を出来るだけ、きれいな状態で流す事、例えば、汚れた食器は、ペーパータオルでふき取ってから洗う。洗剤は合成洗剤を控える。風呂の残り湯は再利用する、もちろんゴミなど捨ててはいけない。各自の問題意識の大きさと実行力にかかっているのだ。
本当に庶民が憩いの場として、大和川が生活の中にとけこみ、北の淀川、南の大和川と大きな声で言えるようにしたいと思う。
大阪の二大河川、淀川と大和川
大阪市と堺市の境を流れる大和川は、まさに庶民の川である。上水道源・工場用水源・放水路と、生活にかかせない川である。
昔、母は八尾の大和川で泳いだという。とても、きれいだったそうだ。今も、上流では泳げるだろうが、私の住む堺では無理だと思う。
難波へ行き来する度に見るだけの大和川であったが、先日、常磐町三丁の堤防から、川岸に降りてみた。堤防には、雑草が生い茂り、キリギリスが鳴いていた。岸辺は砂地で気持ち良い感触がした。川は全体に浅く見え、向う岸まで歩いてゆけそうな気がした。
中州のようなところへサギが降りてきて、エサをついばんでいる。岸辺にも、メダカやタニシがいる。水が結構、澄んでいる。
こう書くと、とてもきれいな川を想像するだろうか、橋げたや岸辺には、空缶、ポリ袋などのゴミが打ちよせられ、たき火、花火の跡、犬のフン、果てには粗大ゴミの捨て場となり、汚く、臭い川となっている。常磐町周辺が、文化住宅、マンション、アパート、工場と立ち並ぶ下町だとしても、大和川流域の土地柄はそう大きく変わらないと思う。
水の都「大阪」にふさわしい川にするために出来る事はなんだろう。
生活排水を出来るだけ、きれいな状態で流す事、例えば、汚れた食器は、ペーパータオルでふき取ってから洗う。洗剤は合成洗剤を控える。風呂の残り湯は再利用する、もちろんゴミなど捨ててはいけない。各自の問題意識の大きさと実行力にかかっているのだ。
本当に庶民が憩いの場として、大和川が生活の中にとけこみ、北の淀川、南の大和川と大きな声で言えるようにしたいと思う。
<銀賞 堺市長賞>
「大和川についての会話」
大阪市立矢田西中学校3年
「なぁ、大和川に行かへん。」
「えっ大和川。別にええけどなんで。」
「たまには行ってみようかなと思って。」
「じゃゴミ袋とぐん手もっていこ。」
「ゴミ袋?なんで。」
「ゴミ拾いをするためや。」
「ゴミ?大和川にゴミなんかあったっけ。」
「知らんの、いっぱいあるで。」
「本当に?大和川にゴミ捨てる人おったん。」
「いっぱいおるで。空きカンやお菓子の袋、ひどい物は壊れたバイクや自転車まで捨ててあるで。」
「ひどいなぁ。なんでそんなことができるんやろ。つみを感じへんのかな。私やったら絶対できへんで。川がかわいそうやで。」
「でもゴミだけやないで。各家庭の台所から出る汚れた水も川を汚す原因なんや。」
「えっそれって汚れた水をそのまま川に流してるってことやん。なんか自分達が川を汚してることがまるわかりで恥ずかしいな。」
「ほんまや。そうやみんなにも大和川のゴミ拾い手伝ってもらおうや。」
「そうやな。きっと手伝ってくれるやろう。」
「みんな来てくれてありがとう。それではゴミ拾いスタートや!」
「うわーすごい!こんなにゴミが集まるとは思わんかったで。」
「本当やな。こんだけのゴミが川に捨てられていることが信じられへんほど量が多いな。」
「でも私達が拾ったゴミはほんの一部にすぎないっていうんは悔しいな。」
「そうやな。私達だけじゃほんの小さなことしかできへんから一人一人が心がけんとあかんな。」
「なぁ、大和川に行かへん。」
「えっ大和川。別にええけどなんで。」
「たまには行ってみようかなと思って。」
「じゃゴミ袋とぐん手もっていこ。」
「ゴミ袋?なんで。」
「ゴミ拾いをするためや。」
「ゴミ?大和川にゴミなんかあったっけ。」
「知らんの、いっぱいあるで。」
「本当に?大和川にゴミ捨てる人おったん。」
「いっぱいおるで。空きカンやお菓子の袋、ひどい物は壊れたバイクや自転車まで捨ててあるで。」
「ひどいなぁ。なんでそんなことができるんやろ。つみを感じへんのかな。私やったら絶対できへんで。川がかわいそうやで。」
「でもゴミだけやないで。各家庭の台所から出る汚れた水も川を汚す原因なんや。」
「えっそれって汚れた水をそのまま川に流してるってことやん。なんか自分達が川を汚してることがまるわかりで恥ずかしいな。」
「ほんまや。そうやみんなにも大和川のゴミ拾い手伝ってもらおうや。」
「そうやな。きっと手伝ってくれるやろう。」
「みんな来てくれてありがとう。それではゴミ拾いスタートや!」
「うわーすごい!こんなにゴミが集まるとは思わんかったで。」
「本当やな。こんだけのゴミが川に捨てられていることが信じられへんほど量が多いな。」
「でも私達が拾ったゴミはほんの一部にすぎないっていうんは悔しいな。」
「そうやな。私達だけじゃほんの小さなことしかできへんから一人一人が心がけんとあかんな。」
<銀賞 王寺町長賞>
「私の中の大和川」
王寺町立王寺南中学校1年
私は夏休みにはいってから大和川を久しぶりに用事の帰り見かけました。
やっぱり「きたないなぁ」と思いました。
でも大和川には幼稚園のときの思い出がたくさんあります。私の通っていた幼稚園では運動会などいろいろなことを大和川の前の河原でやります。アルバムには河原でとった写真がたくさんあります。
今は、小さい子を平気でほおっておいて殺す人も増えてきてこわい世の中になっています。
私はこんな中で暮らすしゃべれもしない小さい子がかわいそうです。
私はいい先生、いい友達がいたから、いい思い出もいっぱいあるんです。
私にとっての大和川はいい思い出ばっかりの大和川です。
もし、化学が発達して川に一滴おとすと川がすごくきれいになる薬品ができても私は、あんまり使ってほしくないです。
大和川は、私の知ってる時からずっときたないから、大和川がきれいになったら、私のいい思い出もきれいさっぱりきえてしまうようでいやだからです。それに大和川は、ゴミがういてないと大和川ではないような気がします。きれい好きな人にとっては、大和川は、たえがたい事実だと思います。でもこれはきたない川だと思うからだと思います。
もしこれが遊具がボロボロの公園だとします。すごく思い出のある公園だとします。そしたら、そのままの姿であってほしいと思うはずです。私はそれがただきたない川なだけだと思います。
もし本当に化学が発達してそんな薬品ができても、私は自分の手できれいにしたいです。自分達が汚したんだから自分達の手できれいにするのが私達の役目だと思います。
私の中の大和川は、きたないけど、どこかできれいにかがやいている大和川です。
私は夏休みにはいってから大和川を久しぶりに用事の帰り見かけました。
やっぱり「きたないなぁ」と思いました。
でも大和川には幼稚園のときの思い出がたくさんあります。私の通っていた幼稚園では運動会などいろいろなことを大和川の前の河原でやります。アルバムには河原でとった写真がたくさんあります。
今は、小さい子を平気でほおっておいて殺す人も増えてきてこわい世の中になっています。
私はこんな中で暮らすしゃべれもしない小さい子がかわいそうです。
私はいい先生、いい友達がいたから、いい思い出もいっぱいあるんです。
私にとっての大和川はいい思い出ばっかりの大和川です。
もし、化学が発達して川に一滴おとすと川がすごくきれいになる薬品ができても私は、あんまり使ってほしくないです。
大和川は、私の知ってる時からずっときたないから、大和川がきれいになったら、私のいい思い出もきれいさっぱりきえてしまうようでいやだからです。それに大和川は、ゴミがういてないと大和川ではないような気がします。きれい好きな人にとっては、大和川は、たえがたい事実だと思います。でもこれはきたない川だと思うからだと思います。
もしこれが遊具がボロボロの公園だとします。すごく思い出のある公園だとします。そしたら、そのままの姿であってほしいと思うはずです。私はそれがただきたない川なだけだと思います。
もし本当に化学が発達してそんな薬品ができても、私は自分の手できれいにしたいです。自分達が汚したんだから自分達の手できれいにするのが私達の役目だと思います。
私の中の大和川は、きたないけど、どこかできれいにかがやいている大和川です。
<銀賞 王寺町長賞>
「やまとがわ」
大和高田市立磐園小学校1年
みんながかわにごみやかんたばこいろいろなごみがあるのでぽいすてはやめよう。
わたしは、かわがすきです。だってかわのそばでみみをすましたらひゅーーーーころころころってゆうからかわがだいすきです。
やまとがわをきれいにして、さかなとりやおよいだりしたいです。
かわはごみばこじゃありません。かわはきれいなかわになりたがっているだろう。
かわのおかげでにんげんたちのたべものがたべれるから、たいせつにしよう。
みんながかわにごみやかんたばこいろいろなごみがあるのでぽいすてはやめよう。
わたしは、かわがすきです。だってかわのそばでみみをすましたらひゅーーーーころころころってゆうからかわがだいすきです。
やまとがわをきれいにして、さかなとりやおよいだりしたいです。
かわはごみばこじゃありません。かわはきれいなかわになりたがっているだろう。
かわのおかげでにんげんたちのたべものがたべれるから、たいせつにしよう。
<銅賞 大和川工事事務所長賞>
「大和川と人のつながり」
松原市立松原第五中学校2年
「昔はプールがなかったから川まで泳ぎに行ったんや。」
とおじいちゃんが言った。私は大和川についておじいちゃんに聞いてみた。やっぱり、川で友達と魚をとったりして遊んだことが思い出だと言っていた。人が入って遊べて、魚がいて、そんな昔のきれいな大和川を私も見たかったなと思った。
今の私達は、川にはいって遊んだこともないし、男の子と女の子がいっしょに遊ぶのは、本当に小さいときぐらいしかない。昔は、川で遊んでもおかしくなくて、男の子も女の子もいっしょになって遊んだとおじいちゃんは言っていた。今、川でつりをしている人はいるけど、泳いでいる人なんて一人もいない。もしいても、だれだって「こんなきたない川で。」と言うと思う。
大和川だけじゃないけど、川ってかわいそうだなと思った。昔はきれいだった川が、人口が増えるにつれてきたなくなってしまう。人がどんどんよごしていくのに、「きたない、きたない」と言われている。大和川をよごした一人かもしれないけど、そんな川が、ほんとうにかわいそうだと思った。それでも川にゴミなどを捨てる人がいるかぎり、おじいちゃんが遊んだようなきれいな川にもどすことは絶対無理だと思う。
日本で一番きたない大和川。今の大和川は川のある意味がないと思う。人がたくさん集まれるところ、川にはいって遊んでいても、なにも不思議じゃない。それが昔からつくりあげられてきた大和川の本当のありかただと思った。
「昔はプールがなかったから川まで泳ぎに行ったんや。」
とおじいちゃんが言った。私は大和川についておじいちゃんに聞いてみた。やっぱり、川で友達と魚をとったりして遊んだことが思い出だと言っていた。人が入って遊べて、魚がいて、そんな昔のきれいな大和川を私も見たかったなと思った。
今の私達は、川にはいって遊んだこともないし、男の子と女の子がいっしょに遊ぶのは、本当に小さいときぐらいしかない。昔は、川で遊んでもおかしくなくて、男の子も女の子もいっしょになって遊んだとおじいちゃんは言っていた。今、川でつりをしている人はいるけど、泳いでいる人なんて一人もいない。もしいても、だれだって「こんなきたない川で。」と言うと思う。
大和川だけじゃないけど、川ってかわいそうだなと思った。昔はきれいだった川が、人口が増えるにつれてきたなくなってしまう。人がどんどんよごしていくのに、「きたない、きたない」と言われている。大和川をよごした一人かもしれないけど、そんな川が、ほんとうにかわいそうだと思った。それでも川にゴミなどを捨てる人がいるかぎり、おじいちゃんが遊んだようなきれいな川にもどすことは絶対無理だと思う。
日本で一番きたない大和川。今の大和川は川のある意味がないと思う。人がたくさん集まれるところ、川にはいって遊んでいても、なにも不思議じゃない。それが昔からつくりあげられてきた大和川の本当のありかただと思った。
<銅賞 大和川工事事務所長賞>
「大切なのは……」
大阪市矢田西中学校2年
大和川のぐるりには、蒼々と雑草が茂っている。伸びては刈られ。伸びては刈られ。それでも、また伸びる。大和川の恵みを受けて。そして虫達はその草を糧に、命をつなぐ。その虫達も、やがて空を駆ける鳥の糧となる。すぐ近くで、こんなに偉大な食物連鎖が起こっている。私達が、気に止めていないだけで、常に新しい命が生まれている。それは、地球の本能であり、人は自然と呼ぶ。その自然が、私達のすぐそばにある。きっと何十年、何百年、いや、それをも遡る、ずっと昔から。
先日、河川敷を七、八人で清掃しているのを目にした。彼らのかたわらには、幾つものオレンジ色のゴミ袋。「大和川は汚い」とは言っても、よくそれだけ集まるな、と、感想の第一声。その数は、異常だった。片手の土手だけなのに、拾っても拾っても、ゴミは終わりを告げない。ここだけでそんな量ならばきっとその倍、もしくは三倍、川に沈んでいるに違いない。恐ろしい事だと思う。
ひとりが、缶を投げ捨てる。その転がっている缶を見て、他の誰かが、ゴミを捨てる。それが全ての始まりだと私は思う。では、これから、もっと汚くなるのか?それを止めるにはどうすればいい?いくつもの問いの結果、行きつくところは「清掃する」それも、ひとりひとりが。そして、「捨てない」これで湧き続けるゴミの泉を止める事が出来ると思う。次いで、「伝える」こういうコンクール、キャンペーンを企画したり、ポスターや冊子で、大和川を美しくしたい、という想いをあおる事が出来る。アイデアは、もっともっとあるはずだ。答えは、まだ出さなくていい。大切なのは、望むこと。未来へ続く、清らかな美しい流れを。
大和川のぐるりには、蒼々と雑草が茂っている。伸びては刈られ。伸びては刈られ。それでも、また伸びる。大和川の恵みを受けて。そして虫達はその草を糧に、命をつなぐ。その虫達も、やがて空を駆ける鳥の糧となる。すぐ近くで、こんなに偉大な食物連鎖が起こっている。私達が、気に止めていないだけで、常に新しい命が生まれている。それは、地球の本能であり、人は自然と呼ぶ。その自然が、私達のすぐそばにある。きっと何十年、何百年、いや、それをも遡る、ずっと昔から。
先日、河川敷を七、八人で清掃しているのを目にした。彼らのかたわらには、幾つものオレンジ色のゴミ袋。「大和川は汚い」とは言っても、よくそれだけ集まるな、と、感想の第一声。その数は、異常だった。片手の土手だけなのに、拾っても拾っても、ゴミは終わりを告げない。ここだけでそんな量ならばきっとその倍、もしくは三倍、川に沈んでいるに違いない。恐ろしい事だと思う。
ひとりが、缶を投げ捨てる。その転がっている缶を見て、他の誰かが、ゴミを捨てる。それが全ての始まりだと私は思う。では、これから、もっと汚くなるのか?それを止めるにはどうすればいい?いくつもの問いの結果、行きつくところは「清掃する」それも、ひとりひとりが。そして、「捨てない」これで湧き続けるゴミの泉を止める事が出来ると思う。次いで、「伝える」こういうコンクール、キャンペーンを企画したり、ポスターや冊子で、大和川を美しくしたい、という想いをあおる事が出来る。アイデアは、もっともっとあるはずだ。答えは、まだ出さなくていい。大切なのは、望むこと。未来へ続く、清らかな美しい流れを。