河川改修
4.河川改修<かせんかいしゅう>
洪水による氾濫を防ぐため、堤防を作ったり、河床を掘ったり、川幅を広げたりして整備することです。
■河川改修の方法例
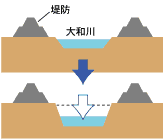
河道の掘削
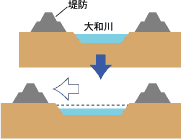
引 堤
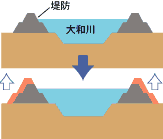
堤防の嵩上げ
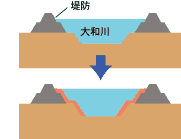
護 岸
55.流下能力<りゅうかのうりょく>
川のある区間が洪水を安全に流下させ得る能力のことをいいます。通常は流量( /s)で表します。
56.河床低下<かしょうていか>
河川において流水に接する川床の部分を河床と呼び、その部分が洪水などにより、削りとられ低下する現象を河床低下と呼んでいます。
57.多自然型川づくり<たしぜんがたかわづくり>
多自然型川づくりとは、治水上の安全性を確保した上で、草花や緑にあふれ、鳥や昆虫などさまざまな生き物を育む、多様で豊かな自然環境を保全、創出し、再生することを目指す川づくりのことです。例えば、魚類の生息に重要な瀬と淵の創出、木や石を用いた空隙のある多様な水辺環境の創出、護岸表面の覆土等による緑化などがあります。
58.河川管理施設等構造令<かせんかんりしせつとうこうぞうれい>
河川管理施設等構造令とは、河川法に基づき、河川管理施設または許可工作物のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる安全確保のための基準値を定めたものです。