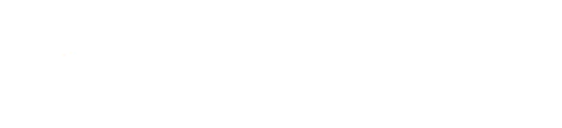周辺地域の歴史文化・名所 詳細(さ行)

上田上桐生町から狛坂磨崖仏に至る山道の途中にある、転倒した岩に刻まれた平安時代後期の阿弥陀三尊像。昔は山頂の尾根沿いにあったが地震で転げ落ちたとも、村の若衆が仏罰の有無を試すために転がしたともいわれる。元の姿にもどそうとする意見もあったが、このままの方が仏意にかなうとして逆さまのままにおかれている。
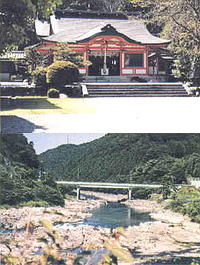
瀬田川の景勝、鹿跳の南岸の高台に鎮座する、天智朝創建と伝えられる延喜式内社。かつては、急流が激しく流れ落ちる川辺にあったが、天ヵ瀬ダムの建設にともない、現在地に移設。古くから瀬田川の激しい水流と清流にちなんで祓所として知られ、禊の聖地であった。天皇の身についた穢を、陰陽師が祓いを修して川に流し去る七瀬祓所のひとつとされる。
伊勢神宮との関わりが深く、伊勢神宮に参向する者は、貴賎の別なく必ず佐久奈度神社に詣でて、禊祓を行なってから出立したという。毎年7月31日のみたらし祭(大祓、夏越の祓)では、1千枚を超える紙人形が瀬田川に流される。「さくなど」の語源としては、
佐久奈度神社のある桜谷は、佐久良谷、佐久奈谷などとも記す。佐久奈度(サクナド←サクナダ←サクナダリ)の神がまつられているから、桜谷(サクラダニ←サクナダリ)と称するようになったと考えられている。
伊勢神宮との関わりが深く、伊勢神宮に参向する者は、貴賎の別なく必ず佐久奈度神社に詣でて、禊祓を行なってから出立したという。毎年7月31日のみたらし祭(大祓、夏越の祓)では、1千枚を超える紙人形が瀬田川に流される。「さくなど」の語源としては、
- サクナダリ(水が勢いよく流れ落ちること)の派生語、
- サ(接頭語)+クナド(道路の神)、
- アサクラ(浅洞、朝倉、谷の入口)の語頭ア音が脱落した、などが考えられている。
佐久奈度神社のある桜谷は、佐久良谷、佐久奈谷などとも記す。佐久奈度(サクナド←サクナダ←サクナダリ)の神がまつられているから、桜谷(サクラダニ←サクナダリ)と称するようになったと考えられている。

伊賀上野に至る国道422号、桜峠の近くにある、信楽町の最高峰。標高739m。山頂を少し下ったところに薬師如来を本尊とした寺があったといわれ、今も石積みの古井戸が残り、水をたたえている。ひでりが続くと山上で火を焚き、この井戸をかき回して雨乞いをしたといわれ、この風習は大正頃まで続いたという。山名のとおり、上部にはササがよく茂っている。信楽町が定める「信楽五名山」(飯道山、笹ケ岳、高旗山、小川城山、愛宕山)のひとつである。

標高433m。別称・笹生(ささふ、ささほ)岳、小竹生ケ岳、権現山。山頂に白山権現の祠と高さ約3mの八畳岩がある。
祠と八畳岩の間には、30cmほどの深さの長方形の穴が掘られており、上に切石のふたが置かれて「石の雨壺」または「石の水壺」と呼ばれている。田上関津町の人々は、毎年田植えが済むと「権現さん参り」と称して笹間ケ岳に登り、この穴の中の水の残量によって、その年の降雨量を占う習わしがある。また、昔は、登山道途中の「踊り場」と呼ばれる場所で、雨乞い行事が行なわれたという。
祠と八畳岩の間には、30cmほどの深さの長方形の穴が掘られており、上に切石のふたが置かれて「石の雨壺」または「石の水壺」と呼ばれている。田上関津町の人々は、毎年田植えが済むと「権現さん参り」と称して笹間ケ岳に登り、この穴の中の水の残量によって、その年の降雨量を占う習わしがある。また、昔は、登山道途中の「踊り場」と呼ばれる場所で、雨乞い行事が行なわれたという。

大戸川・桐生辻の三昧谷と狛坂谷の間の背にあたる岩峰を猿岩と呼ぶ。猿の顔に似ていることからこの名がついたという。

信楽町上朝宮にある、上・下朝宮村の産土神をまつる神社。産土神は古くは三照大明神とよばれ、養老年間に奈良興福寺の義淵僧正か裏白峠(うらじろとうげ、下新宮と京都府宇治田原を結ぶ)の北、志賀良山(しがらやま、標高510m)に飯尾山医王教寺を創立したおり、その鎮護のためにこの地に社を建てたのがはじまりとされる。
延元2年(1337年)の南北朝の争いでは、焼き討ちにあい炎上するが、宝永5年(1708年)に本殿が春日造り三間社(正面の柱の間が3つ)流れ造りの檜皮茸で再建された。境内にはそのほか、宮座(氏子の組合)7座の茅葺きの建物が両側に並び、独特の社殿景観を呈している。宮座建物とその伝承行事が昭和55(1980)年に町文化財に、本殿が平成元(1989)年滋賀県建造物文化財にそれぞれ指定されている。大戸川流域にはなく、西流する信楽川の流域に属する。
延元2年(1337年)の南北朝の争いでは、焼き討ちにあい炎上するが、宝永5年(1708年)に本殿が春日造り三間社(正面の柱の間が3つ)流れ造りの檜皮茸で再建された。境内にはそのほか、宮座(氏子の組合)7座の茅葺きの建物が両側に並び、独特の社殿景観を呈している。宮座建物とその伝承行事が昭和55(1980)年に町文化財に、本殿が平成元(1989)年滋賀県建造物文化財にそれぞれ指定されている。大戸川流域にはなく、西流する信楽川の流域に属する。

上信楽町牧には集落の辻々に計6体の地蔵尊がまつられている。すなわち、久保出の久保出地蔵、中牧平子の湯屋のうら地蔵、馬場出森下の横道の地蔵、馬場出水落の下出地蔵、漆原の妙楽寺地蔵、牧新開の権現寺地蔵である。
なかでも湯屋のうら地蔵は、信楽寺にあった等身大の地蔵で、明治18(1885)年の信楽寺の廃寺後、何者かが搬出しようとしたが途中で断念し、この場に放置されていたのをまつったものという。
なかでも湯屋のうら地蔵は、信楽寺にあった等身大の地蔵で、明治18(1885)年の信楽寺の廃寺後、何者かが搬出しようとしたが途中で断念し、この場に放置されていたのをまつったものという。

大津市上田上大鳥居町の信楽町との境界近く、大戸川の湾曲部にある、河川の浸食によってできた奇岩。清流と岩淵は、古くから子供たちの水遊び場であった。下流の淵をカンナ淵という。同名の「鹿跳(ししとび)」が大津市大石の瀬田川鹿跳橋上流にある。
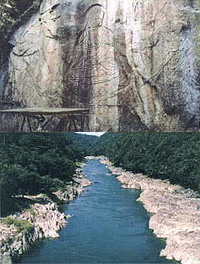
瀬田川、鹿跳橋付近の呼び名。現在は下流に天ケ瀬ダムが作られたため流れはゆるやかになったが、かつては急流が白濁して渦巻く様子が米浙(こめかし、米をとぐ意)と称された。
あたりには急流が岩をうがって作ったポットホールというくぼみのある奇石・怪石が多くみられ、庭石として珍重されている
。鹿跳という名は、昔、弘法大師がこの急流を渡れずに思案していたとき、立木観音の化身である白鹿が現われて大師を背に乗せて、川を飛び越えたことに由来する。宇治、宇治田原、信楽、伊賀方面の分岐点にあたり、古代には近くに大石の関が設けられるなど、今なお交通の要所となっている。
あたりには急流が岩をうがって作ったポットホールというくぼみのある奇石・怪石が多くみられ、庭石として珍重されている
。鹿跳という名は、昔、弘法大師がこの急流を渡れずに思案していたとき、立木観音の化身である白鹿が現われて大師を背に乗せて、川を飛び越えたことに由来する。宇治、宇治田原、信楽、伊賀方面の分岐点にあたり、古代には近くに大石の関が設けられるなど、今なお交通の要所となっている。

上田上牧町の大戸川左岸の田地の一角にある古墳跡。低い土盛の1本の木のもとに「大将軍 庄塚」と掘られた灯籠1基と手水鉢がある。さらに50mほど北東の田の中に、4個ばかりの石が配されている。前者を将軍塚、後者を馬塚という。いずれも古墳跡とされるが、これまでのところ具体的な遺構は確認されていない。
なお、大将軍は農業の神であり、周辺一帯は「ダイジョゴ」とよばれており、宝永4年(1707年)の大戸川洪水以前に牧の集落があった所である。
なお、大将軍は農業の神であり、周辺一帯は「ダイジョゴ」とよばれており、宝永4年(1707年)の大戸川洪水以前に牧の集落があった所である。

信楽町多羅尾の植の坊にある浄土宗の寺。多羅尾光太が後妻のために元和8年(1622年)に建立したと伝える。寺蔵の木造聖観音立像(平安時代)は、もと伊賀上野の平楽寺にあったが、織田信長の伊賀攻めの際に浄顕寺に移されたとされる。
国指定重要文化財となっている。境内には、もと御斎峠にあったという南北朝期の石仏十王像、法然上人お手植えと伝えられるボダイジュの大木(高さ9m、町指定天然記念物)がある。
国指定重要文化財となっている。境内には、もと御斎峠にあったという南北朝期の石仏十王像、法然上人お手植えと伝えられるボダイジュの大木(高さ9m、町指定天然記念物)がある。

信楽町長野にある町内最大の神社。祭神は神社素盞嗚命、稲田姫命、大山津見神。創建は紫香楽宮より早い霊亀2年(716年)とされる。中世以来、長野・神山・江田・小川4ヵ村の総氏神として多羅尾氏の保護を受けている。
江戸時代より宮座(氏子の組合)の存在が知られ、現在も宮座建物の一部が残る。11月の神事には古来南都より能楽師が来て能が奉納されたが、明治維新後絶えたという。現在は7月14日の祇園祭(祇園花行事)が有名である。
江戸時代より宮座(氏子の組合)の存在が知られ、現在も宮座建物の一部が残る。11月の神事には古来南都より能楽師が来て能が奉納されたが、明治維新後絶えたという。現在は7月14日の祇園祭(祇園花行事)が有名である。

上田上新免町の山麓にある古墳群。現在11基の古墳が確認されている。いずれも直径10~15mの円墳で、2号墳のみ内容が明らかになっている。

多羅尾の浄顕寺にある石仏群。平将門の乱に功のあった源兼家(甲賀三郎)は、近江国甲賀郡を賜り、信楽郷18ヵ村を治めるために多羅尾の高峯寺に役所を置き、善政をしいた。それをねたんだ兼家の兄、重宗と定頼の二人は兼家をなきものにしようと陰謀を繰り返すが、過って落命する。
兼家は二人の兄を弔うために御斎峠の路傍に塚を建てたが、兄たちの霊魂がさまよい出て旅人や村人をなやますので、兼家が高峯寺から十王地蔵十体を塚の前にまつると霊魂はしずまったという。この地蔵が浄顕寺の石仏十王像である。散逸をおそれて浄顕寺に移したという。
現在は9体で1体欠けているのは、徳川家康が本能寺変後の帰還のおり、自分の身代わりに山駕篭に乗せて持ち帰ったためと伝えられている。
兼家は二人の兄を弔うために御斎峠の路傍に塚を建てたが、兄たちの霊魂がさまよい出て旅人や村人をなやますので、兼家が高峯寺から十王地蔵十体を塚の前にまつると霊魂はしずまったという。この地蔵が浄顕寺の石仏十王像である。散逸をおそれて浄顕寺に移したという。
現在は9体で1体欠けているのは、徳川家康が本能寺変後の帰還のおり、自分の身代わりに山駕篭に乗せて持ち帰ったためと伝えられている。

大津市上田上牧町の大戸川の川べりに位置する大きな岩。昔から水はねの役割を果たし、牧村を大戸川の氾濫から守ったといわれる。この岩ひとつで、干石の米(田)が助かることからこの名がついた。

信楽町上朝宮の岩谷山仙禅寺(別名:岩谷観音)の小堂の床下の岩に彫られた三尊磨崖仏。
中央は薬師如来像で、高さ約80cmあり、上半身が浮彫り、膝から下は線彫り。両脇の小さな菩薩像も同様の手法で彫刻されている。
建長元年(1249年)の銘があり、鎌倉時代の磨崖仏としてはわが国で2番目に古いものとされている。町指足文化財。
中央は薬師如来像で、高さ約80cmあり、上半身が浮彫り、膝から下は線彫り。両脇の小さな菩薩像も同様の手法で彫刻されている。
建長元年(1249年)の銘があり、鎌倉時代の磨崖仏としてはわが国で2番目に古いものとされている。町指足文化財。