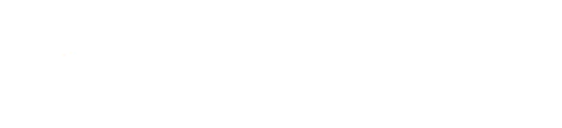周辺地域の歴史文化・名所 詳細(や行)

田上山地の主峰、太神山(たなかみやま、標高600m)に次ぐ高山。太神山の西に、三角すい状にそびえる双耳峰である。標高562m。山容が、矢筈(弓の弦につがえる矢の端部)に似ていることからこの名がついたといわれている。

信楽町の山の神信仰については、総括的な調査資料は今のところ見当たらないが、たとえば宮町の山麓では山の神の祭祀場所がいくつか見られる。多羅尾では「山の神」とよばれる場所が数十ヶ所あるという。上田上、田上、大石には、山の神がその神事とともに、各地にさまざまな形で残っている。田上山周辺地域の山の神は、林業生産を司る神と、農業に実りをもたらす神(春に山から里にくだって田の神となる)の2つの性格が備わっていると思われる。

金勝寺の近くにある、高さ1.5mほどの花崗岩の奇石。「東海道名所図会」によれば、数十人の力でも動かなかったこの岩が、身を清めてから試したら、わずか指1本で動いたという伝承があったという。
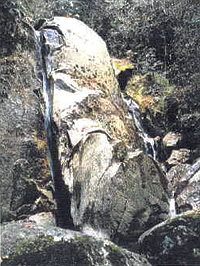
大津市上田上牧町の大戸川発電所の裏手、斧研谷にある滝。水量は多くないが、数段になり、40~50mほどの高さがある。木こりがこの滝で斧を研いだことから滝名になったという。

太神山より発する天神川の砂防工事の一環として、明治中頃にオランダ人技師ヨハネス・デ・レーケの指導、田辺義三郎の設計により、11段の石積みで造られた。高さ6.8m、天端幅4.0m。
今ではすっかり砂に埋めつくされて広い河原となっている。完成年は諸説あるが、明治22(1889)年とするのが有力である。昭和35(1960)年、すぐ下流に高さ11mの新鎧堰堤が築かれた。
今ではすっかり砂に埋めつくされて広い河原となっている。完成年は諸説あるが、明治22(1889)年とするのが有力である。昭和35(1960)年、すぐ下流に高さ11mの新鎧堰堤が築かれた。