本願寺蓮如は、海陸交通の要地でもある加越国境近くの吉崎を選び、文明3年(1471)7月に北陸門徒の布教の拠点とした。この地は、興福寺大乗院領河口荘にあり、蓮如の師である大乗院前門跡経覚との縁故および越前本願寺の中心的位置にあった本覚寺の積極的な招致などによって選ばれたものとされている。蓮如の吉崎進出後、2~3年にして加賀・越中・越前三国の僧侶の支坊である多屋が200軒程度も建ち並び、大門を有する寺内町が生まれ、多屋には各地から門徒が集まり宿泊するなど、盛況を呈して本願寺の勢力の強さに人々は驚かされたといわれている。
蓮如は、文明4年(1472)正月頃から立山・白山・豊原・平泉寺の衆徒ならびに加越両国の守護をはばかり、門徒に吉崎群参を制止したが聞き入れられず帰洛を決意し、翌5年9月に藤島超勝寺に退去した。しかし、門徒や多屋衆の要請が強く、吉崎に帰還することとなる。
応仁・文明の乱の影響が加賀にも押し寄せ、文明6年(1474)西軍に属した加賀の富樫幸千代方・甲斐氏・高田門徒と東軍の富樫政親方・朝倉氏・本願寺勢とが対立し、翌年には政親と一揆方急進派とが対立するにいたり、吉崎に居た蓮如は一向一揆を制止しようと試みたが一揆が鎮静化せず、8月には蓮如は吉崎を去ることとなる。そして、長享2年(1488)以降、加賀は一向一揆の支配するところとなる。
蓮如は、文明4年(1472)正月頃から立山・白山・豊原・平泉寺の衆徒ならびに加越両国の守護をはばかり、門徒に吉崎群参を制止したが聞き入れられず帰洛を決意し、翌5年9月に藤島超勝寺に退去した。しかし、門徒や多屋衆の要請が強く、吉崎に帰還することとなる。
応仁・文明の乱の影響が加賀にも押し寄せ、文明6年(1474)西軍に属した加賀の富樫幸千代方・甲斐氏・高田門徒と東軍の富樫政親方・朝倉氏・本願寺勢とが対立し、翌年には政親と一揆方急進派とが対立するにいたり、吉崎に居た蓮如は一向一揆を制止しようと試みたが一揆が鎮静化せず、8月には蓮如は吉崎を去ることとなる。そして、長享2年(1488)以降、加賀は一向一揆の支配するところとなる。
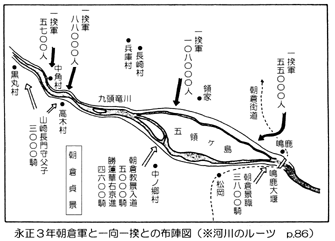
永正3年(1506)3月に本願寺実如の命を受けて加賀一向一揆は越前の一向衆に呼応し、30万人の大軍をもって越前に侵入した。しかし、一揆勢は九頭竜川の戦いで朝倉氏に敗北し、吉崎の坊舎は焼かれ中心勢力も加賀に亡命した。朝倉氏は、本願寺系浄土真宗を厳しく禁止し、一向一揆と朝倉氏との対立が約60年間続くこととなる。
織田信長の台頭によって本願寺と朝倉氏は手を結び、反織田連合を元亀元年(1570)に結成し、一向宗の禁圧も解消された。しかし、天正元年(1573)8月、信長軍が越前に侵攻し、朝倉氏は滅亡した。その後は、織田方の武将が越前を支配するが、翌年には一向一揆が蜂起して織田方の武将を討つとともに、平泉寺などの敵対勢力を攻撃し、本願寺領国として越前を支配した。これに対して織田信長は、一揆鎮圧のために約10万人の軍勢を率いて天正3年(1575)8月再び越前に向けて出陣した。一揆勢は、木ノ芽峠・鉢伏山一帯を防御線として戦ったが突破され、瞬く間に越前を制圧され、再び蜂起できなくなるように徹底した一揆狩りによって壊滅状態となった。一向一揆による越前支配は、1年半で終わりを遂げた。
織田信長の台頭によって本願寺と朝倉氏は手を結び、反織田連合を元亀元年(1570)に結成し、一向宗の禁圧も解消された。しかし、天正元年(1573)8月、信長軍が越前に侵攻し、朝倉氏は滅亡した。その後は、織田方の武将が越前を支配するが、翌年には一向一揆が蜂起して織田方の武将を討つとともに、平泉寺などの敵対勢力を攻撃し、本願寺領国として越前を支配した。これに対して織田信長は、一揆鎮圧のために約10万人の軍勢を率いて天正3年(1575)8月再び越前に向けて出陣した。一揆勢は、木ノ芽峠・鉢伏山一帯を防御線として戦ったが突破され、瞬く間に越前を制圧され、再び蜂起できなくなるように徹底した一揆狩りによって壊滅状態となった。一向一揆による越前支配は、1年半で終わりを遂げた。