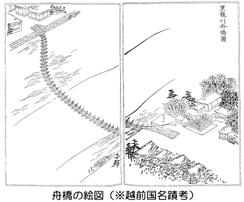2.4.1 北ノ庄と柴田勝家
織田信長による越前統治の第一歩は、柴田勝家に越前8郡を託し、北ノ庄において北陸の統括を命じ、大野郡の三分の二を金森長近に、三分の一を原政茂に、府中の周囲2郡を前田利家・佐々成政・不破光治の府中三人衆に支配させることであった。
勝家が居城とした北ノ庄は、足羽御厨の北ノ庄から出たもので、足羽川北岸に位置していた。勝家が一乗谷城を使用せずに北ノ庄の地を選んだのは、水運に便利なことや北陸道近くであることなどが理由であった。まちづくりにあたっては、一乗谷から社寺や民家などを北ノ庄に移し、城下町の繁栄を計った。また、河南と河北との連絡を便利にするため、足羽川に笏谷石を用いた半木半石の九十九橋を架設した。
勝家は、民間の鎧や甲冑、弓矢、鳥銃、刀剣、轡などを集め、不要なものを鋳つぶして農具や鉄鎖、金具などを製作させ、農具を農民に与え、鉄鎖を九頭竜川の舟橋を繋ぐために使用し、金具は城の用具として用いた。
舟橋は、柴田勝家が九頭竜川に48浦から召し上げた漁船を並べ、鉄鎖で繋いで安定させ、その上を往来できるようにしたもので、国中より人夫を使役して造ったものである。勝家はこれとあわせて、安土へ向かう道を容易にするため、今庄から板取・栃ノ木峠を経て柳ケ瀬に至る北陸道の整備を進めた。そのため、栃ノ木峠から南椿坂に至る間は、人馬の交通が容易になるように開削された。