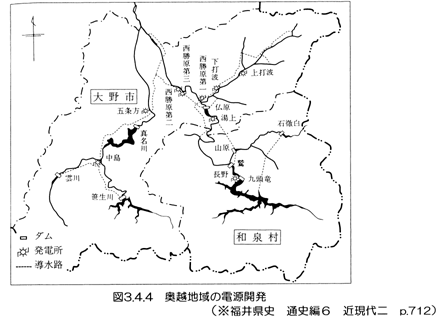
電源開発㈱と北陸電力㈱とが競願していた昭和36年(1961)には、計画調整のために「九頭竜川電源開発協議会」を設置し、具体的な計画策定、施工分担を定め事業実施に向かって活動を始めた。これと時を同じくして建設省は、昭和34年(1959)9月に来襲した台風15号(伊勢湾台風)による大洪水を契機に、九頭竜川治水計画の一環としてダムによる洪水調節計画を立案した。そこで建設省と前記2社、あるいは福井県をはじめ関係機関とが調整の上、治水、利水面からの河川総合開発事業としての「九頭竜川総合開発事業」が策定された。
この計画は、最大規模を誇る長野ダム(後に「九頭竜ダム」と改称)を中心に7つのダムを築造して、九頭竜川、石徹白川の水を集水し、長野・湯上・西勝原第三の3発電所の水源とし、洪水調節や発電など多目的にダムを利用しようとするものである。なかでも九頭竜ダムの下流に築造された鷲ダムは、長野発電所の放流水を貯留するとともに、夜間の余剰電力を利用して長野ダムに揚水するときの下池の役割を果たし、さらにその放流水を調節して、湯上発電所に送る逆調整池用としての機能を持たしている。
本格的な工事は、昭和40年(1965)5月に長野発電所関係の工事着工で始まり、42年(1967)10月に長野ダムの本体工事が完成した。12月2日より湛水を始め、43年(1968)5月下旬に満水位海抜560mに達し、3億2,000万m3を貯水した。長野発電所1号機の営業運転開始は、5月に始まった。
奥越電源開発工事の中核を占めたロックフィルダムは、地元からの改称の要求を電源開発が受け入れ、昭和43年(1968)9月18日「九頭竜ダム」と改称された。
この計画は、最大規模を誇る長野ダム(後に「九頭竜ダム」と改称)を中心に7つのダムを築造して、九頭竜川、石徹白川の水を集水し、長野・湯上・西勝原第三の3発電所の水源とし、洪水調節や発電など多目的にダムを利用しようとするものである。なかでも九頭竜ダムの下流に築造された鷲ダムは、長野発電所の放流水を貯留するとともに、夜間の余剰電力を利用して長野ダムに揚水するときの下池の役割を果たし、さらにその放流水を調節して、湯上発電所に送る逆調整池用としての機能を持たしている。
本格的な工事は、昭和40年(1965)5月に長野発電所関係の工事着工で始まり、42年(1967)10月に長野ダムの本体工事が完成した。12月2日より湛水を始め、43年(1968)5月下旬に満水位海抜560mに達し、3億2,000万m3を貯水した。長野発電所1号機の営業運転開始は、5月に始まった。
奥越電源開発工事の中核を占めたロックフィルダムは、地元からの改称の要求を電源開発が受け入れ、昭和43年(1968)9月18日「九頭竜ダム」と改称された。