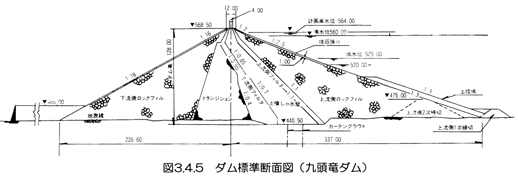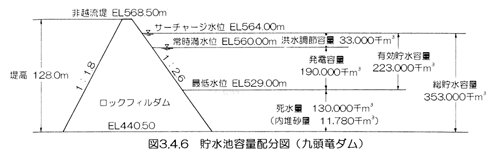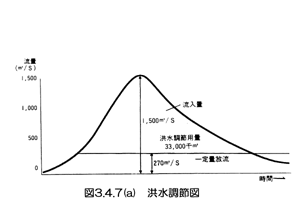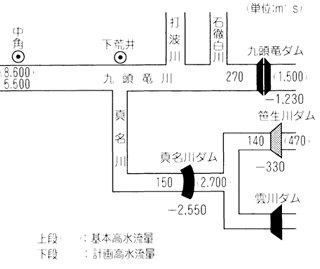(1)概要
九頭竜川は、水力による電力を確保するのに格好の電源開発地帯と注目され、水資源開発の要請が早くから各方面から起った。昭和26年(1951)には、大野市湯上付近にダム建設が計画されたが、国鉄(現JR)越美北線の建設に支障となること、福井県下最大の鉱山である中竜鉱山が水没することなどで実現しなかった。
昭和32年(1957)、北陸電力㈱と電源開発㈱は、両社それぞれの開発計画を発表した。しかし、九頭竜川の水資源開発が北陸電力㈱、電源開発㈱両者の競願であったことから紛糾し、遂に政治問題ともなり、紆余曲折の結果、両者が共同して水資源開発にあたるいうことで決着した。そして、長野・湯上両発電所は電源開発㈱が、西勝原第三発電所は北陸電力㈱が建設することになった。この方針は昭和37年(1962)12月の電源開発調整審議会で正式決定され、ダム地点の地質調査、発電計画、洪水調節計画など再度の設計調査が進められた。
昭和39年(1964)9月1日に九頭竜川建設所が開設され、昭和40年(1965)4月28日に工事に着手し、昭和43年(1968)7月27日に総事業費266億円で完成した。
九頭竜ダムは、洪水調節と発電を目的とする多目的ダムとして、建設省と電源開発㈱とが共同で建設した高さ128mの傾斜式土質しゃ水壁型ロックフィルダムである。なお、ダム湖に架かる箱ヶ瀬橋(全長266m)は、平行線ケーブルが用いられ、本州四国連絡橋のモデルケースとして架けられた橋である。
九頭竜ダムは、堤体管理を電源開発㈱で実施し、施設については共同で管理している。
昭和32年(1957)、北陸電力㈱と電源開発㈱は、両社それぞれの開発計画を発表した。しかし、九頭竜川の水資源開発が北陸電力㈱、電源開発㈱両者の競願であったことから紛糾し、遂に政治問題ともなり、紆余曲折の結果、両者が共同して水資源開発にあたるいうことで決着した。そして、長野・湯上両発電所は電源開発㈱が、西勝原第三発電所は北陸電力㈱が建設することになった。この方針は昭和37年(1962)12月の電源開発調整審議会で正式決定され、ダム地点の地質調査、発電計画、洪水調節計画など再度の設計調査が進められた。
昭和39年(1964)9月1日に九頭竜川建設所が開設され、昭和40年(1965)4月28日に工事に着手し、昭和43年(1968)7月27日に総事業費266億円で完成した。
九頭竜ダムは、洪水調節と発電を目的とする多目的ダムとして、建設省と電源開発㈱とが共同で建設した高さ128mの傾斜式土質しゃ水壁型ロックフィルダムである。なお、ダム湖に架かる箱ヶ瀬橋(全長266m)は、平行線ケーブルが用いられ、本州四国連絡橋のモデルケースとして架けられた橋である。
九頭竜ダムは、堤体管理を電源開発㈱で実施し、施設については共同で管理している。
(2)九頭竜ダムの目的
- 洪水調節
- 発電
- ダムの構造
洪水調節は、満水位560mから計画高水位564mの間、利用水深4mで容量33,000千m3を用いて行い、ダム地点における計画高水量1,500m3/sを270m3/sの一定量放流に調節し、ピーク流量で1,230m3/sの流量を低減する。
発電は下流の湯上・西勝原第三発電所とともに、九頭竜川の大規模な電源開発計画として実施されたもので、長野発電所で最大使用水量266m3/s、最大220千kwの発電を行い、その放流水を直下の鷲ダム調整池に貯留し、夜間の余剰電力を利用して最大240~260m3/sを九頭竜ダムに揚水して再使用するとともに、石徹白川筋の山原ダムに導水し、山原ダム流域の水を加えて、湯上発電所において最大54千kwの発電を行う。
さらにこの放流水を、湯上発電所の直下流にある逆調整用の仏原ダム貯水池に貯留し、西勝原第三発電所において最大48千kwの発電を行う。
九頭竜ダムは、高さ128mの傾斜式土質しゃ水壁型ロックフィルダムである。
九頭竜ダム建設地点は、フィルタイプダムとして適当な地形をなし、基礎岩盤も比較的良好で、特に傾斜しゃ水壁基礎には堅硬な岩盤が分布していることから決定された。