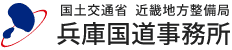~山陽道・西国街道~律令時代~山陽道の誕生
異国からの使者を迎えるためにつくられた日本唯一の大路
1300年以上もの昔、大和朝廷によってつくられた山陽道は、中国や朝鮮半島の先進文化を大宰府から都に運ぶ重要な役割を担っていました。大化の改新(645年)で律令制度が取り入れられると、地方を支配するため7本の道路が整備されます。大路であった山陽道には約16kmごとに駅屋が置かれ、労働力や文化、政府の命令がいわゆる駅伝方式で運ばれました。兵庫県内には、西宮、明石に駅屋がありました。

西宮神社

須磨の松原

明石城と道標
(R2沿い天文町1丁目)
江戸時代~西国街道として整備
参勤交代の道として、流通を支える道として、さらに発達
中世になり都の力が弱まると山陽道は衰退していきます。しかし江戸時代に徳川幕府が全国の街道を再編すると、山陽道は西国街道と呼び名を変え、再びにぎわいを取り戻します。打出村(現在の芦屋市)で旧来の本街道と、その南側を通る浜街道に分かれ、本街道は大名行列などの公用、浜街道は庶民の生活道路や商業用として発達しました。

神戸浜手バイパス橋桁撤去状況

菊正宗酒造記念館界隈

西国街道の古い道標