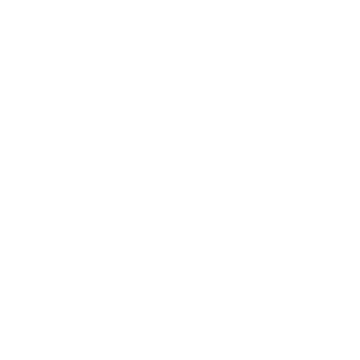淀川水系河川整備計画にむけての意見交換会(第2稿) 意見・質問と回答
意見・質問と回答
平成15年7月20日~7月28日まで
1
| 質問・意見 | 申し訳ありません。河川についての意見はありません。ただ、このチラシのすごいセンスに脱帽しました。思わず資料が欲しくなってしまいました。お金をかけなくてもこんなマーケティングができるのかと感心しました。仕事の参考にさせて頂きます。このチラシ、国土交通省の方が作られたのでしょうか。だとしたら、役人にしとくのはもったいない。 |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
2
| 質問・意見 | 最々先端のコンピューターを使って、猪名川の未来をけん作する。たとえば、有史以前からのデーターで未来をけん作する。 そんな、雄大なドラマやヒストリーがあったかなどなど。 それを思うだけで又、猪名川を見ているだけで胸がわくわくする様な、そんな未来があると思う。そうゆう事業にしょう点を合せて見まもりたい。 よろしく。(テーマは基訴) |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 今回の河川整備計画の基本的考え方は、治水、利水、環境、利用の課題に対して、流域的視点に立って、流域のあらゆる関係者が連携協力し、健全な水循環系の確保に向けた努力を積み重ねることを前提に、以下を基本に据えて河川整備計画を策定していきます。
|
3
| 質問・意見 | 淀川水系委員会が「基本的にはダムを作らない」という提言を出されたことに賛意を表します。大きく自然を破壊するダム(砂防ダムも含め)で治水、利水を考えるのでなく、川との共生を考えながら、川の景観や環境を自然のままに残して欲しいと考えます。又、すきあらば削りとろうとする開発業者や不法投棄をする輩には、パトロールを強化し、法を整備し、厳罰をもって拠すべきです。 今、猪名川のコンニャク橋周辺の改修工事が行なわれていますが、今年、塩川橋上流でたくさんのゲンジボタルでにぎわいました。今後の工事でこのゲンジボタルを保護するよう県への指導よろしくお願いします。 |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 現在、ダムおよびダム以外の治水対策の方法について併せて検討を行っています。 検討にあたっては、周辺自然環境への影響、社会的な影響、事業の効果などを考慮し、今後検討・見直しを行い、結果がでた時点で、流域委員会や流域住民、関係地方自治体等に説明し意見を頂いた上で決定していきます。 また、今後の河川改修は地形を考慮し、横断方向・縦断方向の連続性の修復を目指すとともに、瀬と淵が形成されるなどの多様な形状を持つ河道の改修を図って参りたいと思います。 今後は、河川管理施設の機能を維持するために、適切な維持管理を行うとともに、パトロールを強化したり、看板をたてる等の啓発活動を実施し、河川美化と環境保全のための維持管理に努めていきます。 ご意見いただいた場所の管理は兵庫県が行っており、ご意見を兵庫県へ送付し、以下の回答をいただいております。 「まず、不法な開発行為に対しては、兵庫県では河川・砂防パトロールを随時実施しており、関係部局と連携を図りながら、指導・勧告等を行っており、市・警察の協力も得ながらゴミ処理等に努めているところであります。 次に、ゲンジボタルの件ですが、兵庫県では生態系など自然環境との共生を図りつつ、水辺の魅力と快適さなどを活かした「ひょうご・人と自然の川づくり」に努めているところであります。 ご指摘の塩川についても、この理念に基づき、魚道の設置や自然石護岸等による多自然型河川改修を目指します。」 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
4
| 質問・意見 | 池田から伊丹寄の猪名川についての事ですが。 鳥のキジが生息しています。又5月・6月中頃まで、軍行橋の下で鯉の産卵場所が有ります。朝六時半頃まで、100匹位の鯉が背びれを見せて水面をバシャバシャと波をたてています。こんな珍しい場所を、水の汚染やゴミから守って下さい。 |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 ご意見のとおり、これまでの流域における社会活動、河川の整備や利用が川や我々自身の生活環境に与えてきた影響を真摯に受け止め、今後の河川整備は、水辺の変動によって冠水・攪乱される区域が広範囲に存在し、変化に富んだ地形と多様な生態系が形成されていた頃の河川環境を強く意識し、川に応じた横断的・縦断的形状の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生、住民が安心して利用できる水質の改善等を目指します。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
意見・質問と回答
平成15年7月29日 箕面会場 意見交換会
1
| 質問・意見 | 余野川ダムについて
|
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 余野川ダム建設事業は国土交通省が事業主体であり、一方、水と緑の健康都市事業は大阪府が事業主体となって整備を進めています。双方は別事業ですが、事業地が近接しているために事業工程や運土計画並びに環境調査などについて両者で協議・調整を行っています。 利水については現在、利水者に水需要の精査・確認を行っており、その結果を貯水池規模や貯水池運用等の見直しに反映させます。 河川整備計画説明資料(第2稿)に示すとおり、余野川ダムは一庫ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として有効であると考えています。 今後、余野川ダム以外の方法についても併せて検討を行っていきます。 各家庭で節水することは水需要を抑制する上で良い方法のひとつと考えます。 しかしながら、流域全体である程度まとまらないと定量的な評価ができません。 また、個人に管理をまかせるのではなく、適正な水需要の管理を継続して実施される補償がありません。従って、今回は検討していません。 従来の猪名川の治水計画は、一庫ダム及び余野川ダムにより猪名川の洪水を調節し、堤防の拡築、掘削護岸等の施工を行うことにより所定の安全度を確保することを目標としてきました。 今回、策定する整備計画では「狭窄部の開削は、下流への流量増により破堤の危険度を増大させるため、下流の破堤の危険度を増大させないという観点から、下流の河川整備の進捗状況等を踏まえて実施の判断を行う」ものとし、狭窄部の開削が当面できないなかで、これまでに度々浸水被害を受けている多田地区の被害軽減対策について検討しました。 現在の堤防は、材料として吟味されているとは限らない土砂を用いて逐次強化を重ねてきた歴史の産物であり、必ずしも防災構造物としての安全性について十分な信頼性を有しているとはいえません。 説明資料でご説明したとおり、今回の整備計画では、近年において浸水被害が度々発生している狭窄部上流については既往最大規模の洪水に対して被害軽減を図ることを目標としました。また、猪名川下流部については資産が集中しておりひとたび被害が発生すると甚大な被害になることが想定されることもあり、想定を上回るような洪水が起こっても堤防の破堤による甚大な被害を軽減するということを目標としました。 平成11年(1999年)6月に余野川上流域に強い雨が降り、余野川沿川の止々呂美地域の田畑が一部冠水したと聞いています。このときの余野川大向橋地点(分派堰建設予定箇所)の最大流量は約260m3/sでした。この出水時にもしも余野川ダム(分派堰)があれば、分派堰下流の余野川への流下量が約40m3/sに抑えられたと考えられ、浸水被害は回避できたと思われます。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
2
| 質問・意見 | 余野川ダムについて ムダな余野川ダム事業の中止を総合治水で災害のないまちづくりの提言をパンフで意見として提出いたします。 パンフレット(PDF) |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 これまでの余野川ダムは、
これからは、
利水については現在、利水者に水需要の精査・確認を行っており、その結果を反映させます。 今後は、環境の諸調査を含め、さらに詳細な検討を実施していきます。 なお、これらの調査・検討を出来る限り早期に完了し、その結果が出た時点で改めて流域委員会や自治体、住民の皆様に説明します。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
3
| 質問・意見 | 私は現在事業が実施されている余野川ダムの地元、箕面市止々呂美地域のまちづくり協議会の会長をしております奥村と申します。常日頃から、国土交通省におかれましては、私ども国民の生命と財産を水害から守るため、昼夜を問わず河川事業にご尽力くださり、厚く御礼申し上げます。 さて、止々呂美地域は箕面市の市街地からは離れた、周囲を山に囲まれた余野川沿いの集落でございます。その地理的条件により通勤・通学、買い物、医療機関への受診などの日常生活にも不便を強いられております。地域の課題は、高齢化が進む一方、子供の数は減っており、活力が失われつつあることです。農家は多いのですが、ほとんどが兼業農家であり、後継者不足に悩んでいます。このままでは、高齢化や過疎化が更に深刻な事態になることは、火を見るより明らかです。 そのような状況で、地域の活性化は止々呂美住民の長年の悲願となっておりました。そこで、当時の建設省で行われます「余野川ダム事業」及びそれと一体的に行われる宅地開発による地域整備などにより、地域の発展が期待できるということから、余野川ダム事業計画などが持ち上がった折に、われわれ止々呂美住民は先祖代々受け継いできた山林を売却し、その計画を受け入れるという苦渋の選択を過去にしてきたわけです。 そうであるのに、淀川水系流域委員会では、今年の1月にダムについては、事業中のものを含め、原則建設しないというような答申を出されたと聞いております。また、近畿地方整備局におかれましては、その答申を受け、「河川整備計画説明資料(第2稿)」では、事業中のダムについては「調査・検討」を行うと記述されています。その結論が出るまでに、1年から2年もかかるということを、お聞きして非常に戸惑っているところです。地元としては、ダム建設に対して、それなりの決意をもって決断し、協力もしてきたわけですから、すみやかに事業を完了していただくことを願って止みません。 また、ダムが必要であるのは地域整備の観点からだけではありません。止々呂美地域でも過去の洪水時に余野川で住民に被害者がでています。水害は実際に体験した者にしか、その恐ろしさはわからないものです。止々呂美地域に限ってみても、余野川の水位を調節する余野川ダムは治水上も大きなメリットがあります。 ダムの用地買収は99%を超えていると聞いております。巨額の税金が、すでに投入されているわけですから、もし、万が一にでもダム事業が中止になったとすれば、それこそ大きな税金の無駄使いをしたことになると私は思います。予定どおりにダムを建設することこそ、効率的でかつ効果的な税金の使い方であると考えます。 自然環境保護のため、余野川ダム事業を見直すべきだとの声を聞きますが、今まで、この山を守ってきたのは、我々、止々呂美の住民であることを忘れていただきたくありません。環境保護も大事でありますが、人の生活があっての環境ではないでしょうか。 利水につきましても、水道の蛇口をひねれば水が出るのが、今は当たり前のように思われております。止々呂美地域では、今でこそ簡易水道になりましたが、それまでは、ときに飲み水の確保に大変な苦労をしました。資源の節約には一定理解をいたしますが、異常気象に見舞われている近年において、充分な手立てをせずに、渇水による水不足に対しまして住民の合意が本当に得られるのでしょうか、はなはだ疑問に思います。 また、止々呂美地域における農業用水について言えば、今でも雨の少ない時期には水の確保が死活問題となります。昔は水の争いに、血みどろの争いをしてきたと聞きます。安定した水の供給の大切さを身にしみて感じております。机上の議論は無益どころか有害になる場合もありますので、その点は注意を払う必要があります。 ダム建設反対の声をよく耳にしますが、その意見が猪名川沿川住民の多数意見とはとても思えません。住民投票でも行われれば、そのことが明白になると思います。このような反対意見があたかも住民の総意であるかのごとくに流域委員会の委員の皆様に誤解を与えることを深く危惧いたします。 長くなりましたが、以上、地元止々呂美住民の意を充分にお汲み取りくださり、一刻も早い余野川ダム事業の完成をお願いいたします。 |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 利水については現在、利水者に水需要の精査・確認を行っており、その結果を反映させます。 今後は、環境の諸調査を含め、さらに詳細な検討を実施していきます。 なお、これらの調査・検討を出来る限り早期に完了し、その結果が出た時点で改めて流域委員会や自治体、住民の皆様に説明します。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
4
| 質問・意見 | 猪名川の環境と余野川ダムについて 今日の明会はていねいで分りやすく好感が持てた。 環境対策については、説明にあったように対応してほい。 余野川ダムについて
|
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 今後も皆様方に理解しやすい資料等を作成し、説明していきます。 これまでの流域における社会活動、河川の整備や利用が川や我々自身の生活環境に与えてきた影響を真摯に受け止め、今後の河川整備は、水辺の変動によって冠水・攪乱される区域が広範囲に存在し、変化に富んだ地形と多様な生態系が形成されていた頃の河川環境を強く意識し、川に応じた横断的・縦断的形状の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生、住民が安心して利用できる水質の改善等を目指します。 現在、ダムおよびダム以外の治水対策の方法について併せて検討を行っています。検討にあたっては、事業の効果、周辺自然環境への影響、社会的な影響、などを考慮し、検討結果がでた時点で、流域委員会や住民、自治体に改めて説明し、意見を伺った上で決定していきます。 一庫ダムの利水容量の振り替えについては、今後、振り替え先、振り替え方法、振り替え量等について精度を高めて検討し、検討結果がでた時点で、流域委員会や住民、自治体に改めて説明し、意見を伺った上で決定していきます。また、検討段階における必要な時点で利水者および自治体と調整、協議を図りたいと考えています。 将来の水需要の予測については、水道事業者などの利水者が行います。その結果を受けて、河川管理者は予測の妥当性について審査(精査、確認)します。 「費用対効果」については、ダム規模の見直しが完了後算出し、事業の妥当性を検証いたします。 今回ご説明しました氾濫シミュレーションおよび想定氾濫被害額は、国土交通省が「浸水予想区域図」などを作成する時に用いる「氾濫シミュレーションマニュアル(案)」および「治水経済調査マニュアル(案)」より算出しました。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
5
| 質問・意見 | ◎調査・検討中における工事に実施について 余野川ダムについては、水と緑の健康都市と一体の事業であり、出来る限り引き続けて行うべきである。 今までの地元との協議についても守るべきである。 |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 余野川ダム建設事業は国土交通省が事業主体であり、一方、水と緑の健康都市事業は大阪府が事業主体となって整備を進めています。双方は別事業ですが、事業地が近接しているために事業工程や運土計画並びに環境調査などについて両者で協議・調整を行っています。今後も引き続き継続して協議・調整を行っていきます。 従来から流域委員会に対し、河川整備計画策定の途中では新たな段階には入らないと説明しています。しかし、調査・検討中においても地元の地域生活に必要な道路や防災上途中で止めることが不適当な工事については実施いたします。 今後は、環境の諸調査を含め、さらに詳細な検討を実施していきます。 なお、これらの調査・検討を出来る限り早期に完了し、その結果が出た時点で改めて流域委員会や自治体、住民の皆様に説明します。 その上で、河川整備計画を策定していきたいと考えています。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
6
| 質問・意見 | PR方法について 今回のチラシ(新聞の折り込み)は、いつ頃行われたのでしょうか。 PRがあまりにも急だったような気がするのですが・・・・・・。 |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 “淀川水系河川整備計画第2稿に関する意見交換会”のご案内(新聞折り込みチラシ)は、平成15年7月20日(土)に行いました。(朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、読売新聞、神戸新聞が対象紙です。) 今後は、より多くの方が参加できるようなプログラム、周知の方法について検討していきたいと考えています。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
7
| 質問・意見 |
|
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 現在、ダムおよびダム以外の治水対策の方法について併せて検討を行っています。検討にあたっては、周辺自然環境への影響、社会的な影響、事業の効果などを考慮し、今後検討・見直しを行います。 余野川ダム計画を見直した結果については、説明資料で説明したとおり、1.既設一庫ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として余野川ダムが有効である。2.余野川ダムは下流部の浸水被害を軽減する効果がある と考えています。 河川整備計画説明資料第2稿に示すように今後、水需要について精査・確認を行い、それを踏まえて貯水池規模や貯水池運用の見直しについて検討を行います。その上で、ダムによる環境への影響と軽減方法について検討を行います。水質保全対策の検討においては、貯水池の汚濁メカニズムの検討や具体的な水質保全対策の検討を行い、対策方法について効果、事業費、維持・管理の容易性などを踏まえ実施可能で有効な方法を選定します。 余野川ダムの見直しに関わる調査・検討結果はできる限り早期(概ね1年)に検討を終了したいと考えています。検討結果が出た時点で改めて流域委員会や住民、自治体に説明し、意見を頂きたいと考えています。 そして、頂いた意見などを基に淀川水系河川整備計画原案を作り、改めて意見を頂いた上で、河川整備計画を作っていくという手順で進めていきます。 森林は土砂流出防止、景観、レクリエーションなど様々な機能を持っています。このため、流域内の森林の整備や保全は重要なことと考えています。 しかし、説明資料でお示ししたように日本学術会議(答申)(農林水産大臣の諮問に対する答申「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価について」(平成13年11月))において、「森林は中小洪水においては洪水緩和機能を発揮するが、大洪水においては顕著な効果は発揮できない」との見解が示されています。 また、猪名川の土地利用の現状をみても、これ以上、森林を増やすことが困難です。 このため、今回の多田地区浸水被害軽減の検討における対象洪水である昭和35年8月洪水に対しては、森林による流出量の抑制効果は小さいと考えます。 なお、治水・利水計画はあくまで森林の存在を前提にした上で策定されています。 森林による流出量の抑制効果及び詳細については国土交通省のホームページをご参照下さい。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
8
| 質問・意見 | 余野川ダムについて 私は余野川ダム計画の地域に住んでいるものです。余野川ダムの効果として治水効果に大いに期待します。今まで梅雨の長雨、台風時また近年の少雨だと思えは一時に大量の雨がふるそのたびに余野川を流れる水の量に非常おそれています。そしてその水が流れると同時に流れる大きな石の音、夜もねることができないです。早くダムを作ってほしいと思います。 |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
9
| 質問・意見 |
|
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。
|
10
| 質問・意見 | 河川整備計画の説明が長く、関心持って出席した目的の余野川ダム建設の説明は、説明者の早口もあって、理解し難い箇所があった。ダム建設の有効性は
建設現場を何回も見学してこのように感じた |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 利水については現在、利水者に水需要の精査・確認を行っており、その結果を反映させます。 また、ダム事業は周辺自然環境等に与える影響が大きいこともあり、他の事業にまして慎重に判断します。 現在、ダムおよびダム以外の治水対策の方法について併せて検討を行っています。検討にあたっては、周辺自然環境への影響、社会的な影響、事業の効果などを考慮し、今後検討・見直しを行い、結果がでた時点で、流域委員会や住民、自治体等の意見を伺った上で決定していきます。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
11
| 質問・意見 | 余野川ダムについて 猪名川の洪水調整と一庫ダム容量の代替としても必要で有る。 余野川の洪水調整や災害防止についても必要。 (過去において地元で7名が流され2人が行方不明となった) 現在多額の金を費いやしているので完成させるべきである。 |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
12
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 資料-3の14ページ22番の図で、森林の保全・調整池・地下貯留施設等の「実施」と書いてありますが、どのような所の森林をどのように保全していこうとしているのか、具体的な内容を教えてほしい。 |
|---|---|
| 回答 | 「水害に強い地域づくり協議会」において、住民の皆様と連携を図りながら検討し整備していこうということで、森林の保全を具体的にどうするということはこれから協議会で検討し実施していくということです。 |
13
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 流域委員会のダムの提言に基づいて検討していると思うが、整備局が説明に使用している専門的な言葉が提言における言葉と違うように錯覚してしまうので、どの説明のところが提言のどこを尊重しているのかわかりやすく解説してほしい。 |
|---|---|
| 回答 | 提言に書かれた内容を整備局なりに解釈して書いており、言葉は私たちの言葉になっているかもしれませんが、どこがどのように違うのかよくわからないところがあります。 |
14
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 下流の治水の安全度はどれくらいを目指しているのか。 |
|---|---|
| 回答 | 何年に1回の洪水対策を目指すのではなく、大きな洪水がきても被害を少しでも軽減するよう検討し対応していきたいと考えています。 |
15
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 4000年に1回の確率だという意見も聞くが、その説明がほしい。 |
|---|---|
| 回答 | 昭和46年につくった工事実施基本計画で、当時の猪名川の治水対策は200分の1だったので200年に1回の降雨量を求める式をつくり、その式にあてはめると4000年に1回という答えが出てきました。しかし、昭和35年の洪水が何分の1の確率とはこの場では答えることはできません。 |
16
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 一庫ダムの昨年の渇水は、ダムの操作を変更されているようだがそれと関係があるのか。 |
|---|---|
| 回答 | 昨年は雨が非常に少なくダムの水位が下がってきたということで、利水者の皆さんで協議会を設け、利水者さんの合意のもと、取水制限を設けました。それに基づいてダムは操作しています。 また、一庫ダムの操作変更は、洪水調節の操作ルールを変更したもので、渇水とは関係はありません。 |
17
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 一庫ダムの渇水の原因はどのように考えているのか聞かせてほしい。 |
|---|---|
| 回答 | 淀川水系全体で見ましても、計画していたよりも雨が非常に少ないというのが一番の原因だと認識しています。その中で、本当に、どれだけ水が必要なのか精査するとともに、効率的な補給を目指すということを一体となって頑張っていきたいと思っています。 |
18
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 水利権と実際の水需要との乖離の問題が報告されたが、これについてなぜ許可継続をしているのか。許可している基準の考え方を明確に教えてほしい。 この大きな課題を是正すれば、一庫ダムの治水ポケットを大きくできるのではないかと思うが、その点について説明してほしい。 |
|---|---|
| 回答 | 上水道・工業用水道については現在精査確認中です。一番不明確なのが農業用水で慣行水利権というものがあり、極端な例では受益面積が半分になっているところもあり、そういったところから乖離が非常にあるのではないかと推測しています。 許可の継続についても、見直し期間ということで精査確認を行っていく中で、安易に水利権を更新するという考えは持っていません。 |
19
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 今回の見直し・検討結果のところで、森林の保水機能は有効策ではないとあるが、その理由を聞きたい。 |
|---|---|
| 回答 | 日本学術会議という会議の答申で「森林は中小洪水においては洪水緩和の機能を発揮するが、大洪水においては顕著な効果は発揮できない」とあり、また、猪名川流域の土地の利用面からこれ以上森林を増やす余地はないというのも事実です。 昭和35年を対象とした洪水で、森林の保水機能だけに、洪水を抑制するという機能を求めることは難しいのではないかということで、このような説明をしました。 |
20
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 余野川ダムは必要なのでしょうか?狭窄部で災害が起こりやすいということだが、なぜ開削しないのか。河川整備も一つの案ではないのか。 |
|---|---|
| 回答 | 従来は大きな洪水が発生したら、それにより計画規模を見直すということをしてきましたが、今は、現在あるもので洪水がきても破堤による被害を少なくしようという目標に変わったため、狭窄部は下流の状況を見ると当面開削すべきではないというのが現在の考えです。 |
21
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 自治体はなぜやみくもに都市開発を許してしまうのか。 自治体を含めて協議会をしているのだから、都市のありかたについて議論したり、都市型災害をなくしていくということが大事なのではないか。 |
|---|---|
| 回答 | 自治体の話や、財政の話等がありましたが、これらについて私どもでは何とも言えないところがありますので、このような意見があったことをお伝えしていきたいと思います。 |
22
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 国土交通省・道路公団の問題で6兆円ほどの債務超過があるとかないとか議論されているが、財政的にも非常に大変です。 今の大型公共事業のあり方についても見直してほしい。 |
|---|---|
| 回答 | 自治体の話や、財政の話等がありましたが、これらについて私どもでは何とも言えないところがありますので、このような意見があったことをお伝えしていきたいと思います。 |
上記のほかご意見
| 1 | 域の開発とともにダムの計画に賛成し、建設を願っています。ここ1~2年は調査・検討ということですが、我々の発展、活性化を願っているので早く事業を完了してほしい。 また、自然保護という問題もありますが、地元の環境を守っているのは、我々だと思っていますし、早くダムを完成してほしい。 |
|---|---|
| 2 | 高齢化と過疎化が進んでおり、地域の活性化は大きな問題です。住宅開発とダム建設が一体で計画されて進んできたわけで、これは地域住民100%の要望です。 |
| 3 | 19年の水・緑のまちびらきとダムとが同時に完成し、箕面トンネルが開通するという、3点セットが当初から動いているので、ぜひとも進めてほしい。 |
| 4 | ダムを作ったら自然破壊と書いてあるが、現在の山林は雑木林であり、本来の緑ではないと思います。緑は固まってあるものではなく、地球全体に点在することが本来だと思う。もっと街の中で緑を作ろうという運動がなぜないのか。 |
| 5 | 住宅開発もこれから計画のところに対しては、4割の緑を保とうという意見があり、全体的な見直しあるいは検討課題というものはないのか。 |
| 6 | 河川整備計画の見直しでは、水需要の今後の予測はきちっと考えてほしい。 |
| 7 | 余野川ダムの利水面で、箕面市も必要なくなってきて、阪神水道企業団も水が余っているのではないか。工業用水も余ってきている、それらを転用するという精査をしているとのことだが、環境が変わってきているのに、それでも余野川ダムは必要なのか。 |
| 8 | 止々呂美の活性化のためにダムをつくるというのは理由がちがうと思う。「水と緑の健康都市」とダム建設の目的は違うものだと思う。水と緑の健康都市の開発と余野川ダムのことをどう考えているのか。 |
| 9 | 箕面や阪神水道企業団も国に対して余野川ダム等の利水の見直しを求めているということが議会で言われているが、それに対してどのように対応していくのか聞かせてほしい。 |
| 10 | 余野川ダムに振り替える量が1日36,000トンだと聞いているが、それ位なら節水をするとか、府営水を導入する、または地下水などを検討するなどできると思うが、そういうことをしたうえで余野川ダムに振り替えるという結論を出されたのか。 |
| 11 | 一庫ダムの利水を振り替えしなければ、治水能力が上がらないということは、当初の治水計画が見込み違いだったのか。 |
| 12 | 現在の護岸で、既往最大規模の洪水ではどのような対応になるのか具体的に教えてほしい。 |
| 13 | 余野川ダムがあったとしたら、これまでの既往洪水に対してどれくらい貢献していたのか具体的に教えてほしい。 |
| 14 | 色々な調査の結果、クロマドボタルの新型が発見されたと聞いているが、そういうものに対する対応はどうするのか。 |
意見・質問と回答
平成15年7月30日 池田会場 意見交換会
1
| 質問・意見 | ダム・利用について ダム計画の方針について、「渇水に対する安全度の確保」も余野川ダムの目的にあるのではないか?? 近年の渇水に対応する為に、単なる利水量の整理だけで議論するのではなく、「水のストック」の観点も加味すべきではないか?? 大阪の河川は自然工物ではなく都市施設の一つである。 河川敷も貴重な都市空間であり、有効活用すべきである。 これだけの空間を堤内地に求めるのは不可能である。 |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 (ダム) 近年の少雨化傾向により、渇水が頻発しており一庫ダムにおいても渇水調整を実施せざるを得ない状況となっています。 猪名川の渇水に対する安全性をどのように確保するか、今後、十分な調査および検討を行いたいと考えています。 (利水) 「水のストック」は、水の再利用や雨水利用が含まれると考えられます。これについて、渇水対策協議会等で議論したいと考えています。 (利用) 河川空間は、水面や高水敷或いはその間に挟まれた水陸移行帯等、その姿は特有のものであり、多様な生物が存在しています。高水敷利用にあたっては、周辺環境・地域性に配慮し、その特性を損なわないで「川でなければできない利用・川に活かされた利用」という観点から、現状の利用形態を見直し、グランド等のスポーツ施設のように、本来河川敷以外で利用するものについては、縮小していくことを基本としています。しかしながら、既存の利用施設が数多くの人々に利用され、また住民や自治体等からはグランド等のスポーツ施設に対する存続及び新設の強い要望或いはまちづくり全体の中での議論等の意見があります。このことから、河川敷の利用については、個々の案件毎に、学識経験者、関係地方自治体等関係機関や流域住民等の意見を聴き判断していきます。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
2
| 質問・意見 |
|
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。
|
3
| 質問・意見 | 余野川ダムは洪水軽減に有効というがについて 余野川ダムは洪水軽減に有効で実施可能な手段の有力なものとして説明があったが、その前に、ダムは「他の手段がない場合にやむなく」という重要な前提が抜けている。例えば銀橋狭窄部の開削は当面はしないと結論付けて、余野川ダムを先に建設することを選択している。これは逆で、先ず銀橋狭窄部開削して、かつ下流の被害どうなるか。その被害が大きくなる可能性があるなら、その対策に要する環境・コスト等と、余野川ダム建設の環境・コスト等の比較がされるべきだ。 ダムは他に方法がない場合の最後の手段であるという重要なポイントがぬけおちていて納得できない。 |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 河川整備計画策定に向けての説明資料(第2稿)および説明会で説明した通り、今後も、ダムおよびダム以外の治水対策の方法について併せて検討を行っていきます。検討にあたっては、周辺自然環境への影響、社会的な影響、事業の効果などを考慮し、今後検討・見直しを行い、結果がでた時点で、流域委員会や関係住民、自治体等の意見を伺った上で決定していきます。 狭窄部上流の浸水被害に対しては、下流堤防の破堤危険性を増大させるような狭窄部の開削は当面できないことから、既往最大規模の洪水に対する浸水被害の解消を目標として狭窄部上流における対策を検討します。 狭窄部を開削した場合の下流への流量増およびそれに伴う堤防の危険性については現在、検討を行っており、結果がでた時点で委員会や住民の方へご説明したいと考えています。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
4
| 質問・意見 |
|
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 森林は土砂流出防止、景観、レクリエーションなど様々な機能を持っています。 このため、流域内の森林の整備や保全は重要なことと考えています。 しかし、説明資料でお示ししたように日本学術会議(答申)(農林水産大臣の諮問に対する答申「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価について」(平成13年11月))において、「森林は中小洪水においては洪水緩和機能を発揮するが、大洪水においては顕著な効果は発揮できない」との見解が示されています。 また、猪名川の土地利用の現状をみても、これ以上、森林を増やすことが困難です。 このため、今回の多田地区浸水被害軽減の検討における対象洪水である昭和35年8月洪水に対しては、森林による流出量の抑制効果は小さいと考えます。 今後は、河川周辺の構造物については周辺景観との調和を考えたデザインにしていきたいと考えています。また、国土交通省以外が維持管理する構造物についても助言等を行っていきたいと考えています。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
5
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 ダムというのは環境に大きな影響を与えるということで「他に手段がない場合に最後の手段」という考えだと説明がありましたが、洪水軽減のため余野川ダムを作らなければならないと、これが最後の手段だというところまで検討したのか。 |
|---|---|
| 回答 | 「他に有効で実施可能な手段がない場合実施する」という考えに基づいて現在検討を進めていますが、確かに全ての検討が終わったとは思っていません。 今後も引き続き治水対策について検討を進めていきたいと思っています。 |
6
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 銀橋狭窄部を開削して、「下流にどれくらいの問題が起こるのか」、「問題を防ぐのにどれだけのお金がかかるのか」という検討後の説明がなければ、狭窄部を開削しないということに納得がいかない。 |
|---|---|
| 回答 | 「狭窄部を開削しないことを前提にしている」ということですが、流域全体のことを考えて当面は下流への影響を考えて開削しないということでやっています。 |
7
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 堤防についての回答で、10ヵ所を選んでボーリングで調査中とのことですが、それは下流部のことですか。その調査をし、工法を検討し、予想される完成は平成25年ぐらいになるということですか。 国土交通省の技術水準からすれば、どの工法でやろうとそんなに難しい特殊な堤防とは思えないのですが。 「当面10年」というような長い期間でなく、もっと早い検討をしてほしい。 |
|---|---|
| 回答 | はい。そうです。 |
8
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 多田盆地に水をあふれさすことができないということは、銀橋上流に遊水機能がないということです。橋の下の出っ張った岩は水をせき上げて水位を上げているだけだからすぐに開削すべきです。 橋の下の岩の掘削と古い能勢電鉄の鉄橋の左岸の橋台、レンガ積みのアバットの少し上流の出っ張った岩を取るべきです。 |
|---|---|
| 回答 | 「狭窄部を開削しないことを前提にしている」ということですが、流域全体のことを考えて当面は下流への影響を考えて開削しないということでやっております。 |
9
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 下流の無堤区間と絹延橋、あそこは川幅を広げて堤防をその上下に完成している堤防とつなぐべきです。非常に短い区間でこれはすぐにやるべきだし、いつ頃完成するのか。 |
|---|---|
| 回答 | 大体、平成18年度を予定しています。 あくまでも、平成15年度に整備計画が皆さんから了承を得て、法手続きが終わってからの実施と予定していますが、手続き等で遅れる場合もあります。遅くても平成19年度か平成20年度までに整備を進めていきたいと考えています。 |
10
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 「壊れない堤防」と重点的に河川改修をやられる期間を設定されていますが、この進捗はどのくらいの期間がかかるのか。 |
|---|---|
| 回答 | 10ヵ所の地区を選定しており、現在、ボーリング等を行って詳細調査を行っている段階です。その結果をもとにして具体的な工法や施工の仕方を淀川堤防強化検討委員会に諮りまして、決定後実施となりますので、少し時間的にかかると思います。 予算の都合もありますので、工程上は平成25年以降くらいに完成するのではないかと考えています。 |
11
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 「もし現状のままであれば2兆円の浸水被害が出る」というが、どこが浸水すれば2兆円にもなるのか。 また、その区域の範囲や、破堤を前提にしていると思うがこのときあふれる水の水量が計算されているはずのなで、教えてほしい。 |
|---|---|
| 回答 | 資料-3の30頁18番の資料が余野川ダムの効果ということで、氾濫シミュレーションの結果を載せています。 範囲については資料の通りですが、水量等については資料を持ちあわせていません。 |
12
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 パンフレット(余野川ダムの計画について)の浸水被害の地域を示した図ですが、これは色を塗りつぶしたところ全域が同時に洪水になるのですか。 これは「どこで堤防が切れたときに、ここまで水が来ます」というハザードマップですね。この図は知らない人を脅迫するような図になっていると思います。 右岸が切れれば左岸が助かるはずです。複数地点が切れるということはあるかもしれないが、この図ではそこらじゅうが切れていることになるでしょう?この図はあんまりではないか。 |
|---|---|
| 回答 | この図は危険区域の全てを塗りつぶしたものですが、上流で氾濫すれば水量が減ります。しかし下流でまた氾濫することもあり、上流で氾濫した分については差し引いて考えていますので、ハザードマップで最大被害の崩落線をつないだ図面とは違います。 |
13
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 ダム湖の水質の問題で、出水初期の河川にたまっている落葉落枝が相当流れ込むのではないか。こういうシミュレーションはしていないのか。 |
|---|---|
| 回答 | 現在、調査・検討が必要な項目が色々あるのですが、水需要の精査確認がまだできていません。その結果次第ではダムの規模や貯水池の運用が変わる場合もあり、それを踏まえて水質も含めた調査・検討が必要となります。 余野川ダム計画のなかでシミュレーションは行っていますが、今後の水需要の結果によって大きく変わる可能性もありますので、それを受けてきちんと検討したいと思っています。 |
14
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 水域と陸域の連続性という話があり、それは河川の生態系の中で一番大事なところです。低水護岸をつくるから陸上雑草の生える荒れ地ができ、そこに運動場をつくるという発想だと思います。 階段護岸が非常に長く、生き物の立場からいえば最悪の構造物です。この部分の見直しも進めていただきたい。 |
|---|---|
| 回答 | 河川形状の横断的な話でしたが、縦断的には相当水が流れているところのには横断構造物で堰などが入っています。 横断+縦断をあわせて、環境に配慮しつつ川で楽しめるような利用形態も考えて河川形状の修復をおこないたいと思います。 |
意見・質問と回答
平成15年7月31日 尼崎会場 意見交換会
1
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 ダムの建設予定地を見にいったが、池田市のほうにあってもいいような場所で、みんなが関心をもちにくいようなところに建設されようとしています。 |
|---|---|
| 回答 | 同じ箕面市の中でもご存じない方がおられるということで、PRというか皆様への説明が足りなかったところがあったと思っています。 これからのダムの見直しについては、このような機会を設け、住民の皆様・自治体等への説明を行っていこうと考えています。 |
2
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 「水と緑の健康都市」というのかあるが、余野川ダムの建設とセットになっている。 建設場所も非常に見えにくく、みんなが関心を持ちにくいようなところに建設されようとしている。 |
|---|---|
| 回答 | 余野川ダムの建設は国土交通省が行っています。「水と緑の健康都市」は大阪府が行っています。ただ、両者で、事業工程をあわせたり、掘削の土砂の融通をしたりして、連携をとりながら事業を進めているもので、セットというのはちょっと違うと思います。 |
3
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 流域委員会で2001年から話し合われて、今年の1月に「原則としてダムの建設はしない」というふうに提言がありました。 整備局はこの提言をどのように受け止めて考えているのか教えてほしい。 |
|---|---|
| 回答 | 提言の中には確かに厳しい意見が書いてあります。 ダム事業というのは周辺環境に対する影響が多いということで環境等の調査も改めて行っていこうとしています。 時期については早急にと考えており、検討した結果ができたものから皆様にご紹介していきたいと考えています。 |
4
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 箕面だけなら、府営水道が余っています。一庫ダムを利用している自治体からも水が足りないと聞いたことがない。 もし間違っていたら教えてほしい。 |
|---|---|
| 回答 | 昨年、年末に一庫ダムの容量が7.8%、取水制限40%という状況になりました。川西市・猪名川町・伊丹市の一部では、水源は猪名川か一庫ダムしかありません。利水者間で水を融通して何とか乗り切ったというのが実態です。河川管理者も利水者もともにPR不足のため、大きな新聞記事とならず、皆様にあまり知られないような状況で乗り切った状態です。 |
5
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 箕面市はダムに対して一切予算をもってないのです。市議会の報告によると、市の方も見直しを進めているが、今年の予算にダム建設費は計上されていないと聞いています。 箕面市はダム建設に全然関係ないのですか。 |
|---|---|
| 回答 | 水道用水の供給の中に箕面市が入っていますので、そういう意味では箕面市の関連となります。 |
6
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 渇水を知ったとき、それほど雨が少ないとは思わなかったので、ダムの放流の操作を間違えたのではないかと考えました。 |
|---|---|
| 回答 | 昨年は確かに雨が少なく6月~9月くらいまでは平年の50%をきるような雨の量になっています。 河川を通常流れている水を水道用水に取りますが、取ってしまえば川の水が全てなくなってしまうので、上流にあるダムから水を補給し、十分あるように見える川から水道用水を取っていました。それを2~3ヶ月も続けていると貯水池の水位が減って最後には数%のところまで下がったということです。 |
7
| 質問・意見 | 【口頭によるご意見】 一庫ダムの肩代わりに余野川ダムを使うという話がありましたが、そもそも一庫ダムはきちんと精密な計画のもと建設されたのでしょうか。 |
|---|---|
| 回答 | 一庫ダムの利水の一部を余野川ダムに代えたらという案は、水道用水を猪名川から取るために、一庫ダムが猪名川に水を補給している分を、余野川ダムが肩代わりするという案です。 余野川ダムが肩代わりすることで、一庫ダムは補給のために貯水する必要がなくなります。その分を治水に使うことにより多田地区等の浸水被害を少しでも軽減できないかという案です。 |
上記のほかご意見
| 1 | ダム本体は着手していないが、周辺の工事は非常に進んでいる。用地買収も99%進んでいるというのに、いまさらダムが有効だとか有効でないとか議論されること自体、ダムの計画が本当に考えてつくられたのか。 |
|---|---|
| 2 | 基本的にダムはつくらないでほしい。 |
意見・質問と回答
平成15年8月1日~9月30日まで
1
| 質問・意見 | 質問なのですが、余野川ダムに関連して「狭窄部上流の浸水被害に対しては、下流堤防の破堤の危険性を増大させるような狭窄部の開削は当面できない」との前提ですが、具体的に下流部のどこで、どのような問題があるのか、その改修にどのくらいの財政負担がかかるのか、教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。 |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 狭窄部の開削は、下流への流量増により破堤の危険度を増大させるため、下流の破堤の危険度を増大させないという観点から、原則として当面は行わないものと考えています。現在、狭窄部の開削による下流への流量増や下流堤防の安全基準等について詳細な検討を行っており、これらの結果がでた時点で流域委員会や住民の方へご説明したいと考えています。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
2
| 質問・意見 | 銀橋狭さく部開削による下流流量増について教えて下さい 多田地区では、かっての遊水地などには工場が進出し、低地部の遊水地にも宅地開発が許可され水害危険住宅などが広がり、銀橋狭さく部のために水害多発地域となっています。最近、低地部への水害をなくす河川整備が進んでいます。 提言では狭さく部の開削は、下流への影響が大きく当面開削しないようですが、猪名川の場合には、具体的にどのような効果があるのでしょうか、逆にどのような問題点があるのでしょうか、教えて下さい。 河川整備がすすめられ、河道内貯留の容量は地形的に小さいようです。また、地形的にも遊水量もそう多くはないようですが、現在、どの程度の遊水量があるのでしょうか。仮に河川整備が終り狭さく部を解消すれば、外水による水害はなくなり、内水による水害がどの程度のこるのでしょうか。 銀橋狭さく部を開削した時には、下流流量は変わらないのでしょうか、それとも増えるのでしょうか、増えるとすればその流量は何トン程度なのでしょうか。狭さく部の開削による下流流量への影響を教えて下さい。 |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 狭窄部の開削は、下流への流量増により破堤の危険度を増大させるため、下流の破堤の危険度を増大させないという観点から、原則として当面は行わないものと考えています。現在、狭窄部の開削による下流への流量増や下流堤防の安全基準等について詳細な検討を行っており、これらの結果がでた時点で流域委員会や住民の方へご説明したいと考えています。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
3
| 質問・意見 | 高水敷利用等についてのご意見を頂きました。 →別紙(PDF)を参照下さい。 |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございました。 河川空間は、水面や高水敷或いはその間に挟まれた水陸移行帯等、その姿は特有のものであり、多様な生物が存在しています。高水敷利用にあたっては、周辺環境・地域性に配慮し、その特性を損なわないで「川でなければできない利用・川に活かされた利用」という観点から、現状の利用形態を見直し、グランド等のスポーツ施設のように、本来河川敷以外で利用するものについては、縮小していくことを基本としています。しかしながら、既存の利用施設が数多くの人々に利用され、また住民や自治体等からはグランド等のスポーツ施設に対する存続及び新設の強い要望或いはまちづくり全体の中での議論等の意見があります。このことから、河川敷の利用については、個々の案件毎に、学識経験者、関係地方自治体等関係機関や流域住民等の意見を聴き判断していきます。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
4
| 質問・意見 | 7/29の意見交換会に参加しました。下記理由で余野川ダムは早期完成させるべきと考えます。
|
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 余野川ダムの利水については、現在、水需要の精査・確認を行っていることから、それらを踏まえてダム及び貯水池規模や貯水池の運用の見直しについて検討を行います。 また、現在、ダムおよびダム以外の治水対策の方法についても併せて検討を行っています。検討にあたっては、事業の効果、周辺自然環境への影響、社会的な影響、などを考慮し、検討結果がでた時点で、流域委員会や住民、自治体に改めて説明し、意見を伺った上で決定していきます。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
5
| 質問・意見 | 当自治会は絹延橋~中橋の西側に位置しておりますが、当地に於ける河川整備については、既にH15.6/18の要望書を貴庁に提出済みで、只今、貴庁、川西市と共に下打合せを行なっています。「猪名川の明日をみんなで考えよう」のパンフレットには“実施項目”として、「絹延橋のつけ替え」「無堤区間」工事が計画されているようですが、当方の要望書にあるような“検討項目”は見当らず心配しています。当地ではH7.3/31から協定書で「現在の貴庁のパンフレットの内容」のような河川整備を訴えており、今後の協議は是が非でもパンフレットの趣旨にのっとった、又嵐山計画の一環とした整備をして頂きたく考えています。 H9年の新河川整備法に基づく河川の自然環境の重視は地元住民####最も望まれる事であり、その####を見越して、地元では河川周辺の美化、街づくりを先行して只今地元一同頑張っています。新法以降貴庁所長以下、新法の趣旨を前向きにとらえ、皆様積極的に取り組んで頂き、地元も大いに期待しております。猪名川については基本的に
※「####」部分は判読不能。 |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございました。 地元におかれましては、積極的な河川周辺の美化・街づくりを実施され感謝申し上げます。
を実施して行きます。
今後ともご意見を参考にさせて頂き、今後の河川整備計画を策定する予定ですのでよろしくお願いします。 |
6
| 質問・意見 | 関係者の皆様には、淀川水系河川整備計画の策定検討に日々多大のご努力をなされておられますことに、流域住民の一人として感謝もうしあげます。 さて、ご承知おきのとおり、将来、高齢化が著しく進行し社会弱者の増大が強く懸念されていることと、これに対応した諸施策の必要性と概要が各機関から示されています。 このことは、水防避難立退(水防法 第22条から用語構成してみました)の弱者も増大することと大いに懸念されます。 そこで、わたしどもにも配布を受けました、淀川水系流域委員会への提供資料の「説明資料(第2稿)」につきまして、このことを反映させた内容にご一考いただきたく申し上げます。 なお、稚拙ながら、わたしなりに別紙(PDF)の「水防避難弱者反映案」にまとめましたが、参考となれば幸いであります。 さいごに、淀川水系河川整備計画の策定は大変な業務ですが、関係者の皆様のご健勝をお祈り申し上げます。 |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
7
| 質問・意見 | 川の真中に大木が有る川は初めて見ました。 もう何十年と浚渫をしてないと思います 浚渫をすれば水害も無くなり下流ではヘドロや腐った水は防げます |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございました。 河道内においては、高木樹木の繁茂によって、洪水の流下等に対して影響が生じているところがあります。このため、支障となる河道内樹木については、災害防止の観点から樹木群の拡大防止等適正な対策を図るため、高木の繁茂の状況や生物の生息・生育環境を配慮し、伐採の方法や時期等について住民団体等の意見も聞き伐採します。 河道内の堆積土砂の除去については、定期的に河道形状の状況を把握し、河床変動状況や河川管理施設等への影響及び河川環境への影響等から判断します。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
8
| 質問・意見 | 今年は残暑が厳しいので泳げる河川に猪名川がなれたらといつも思いつづけてます。伊丹市、豊中市、尼崎市、川西市、宝塚市、池田市と、大阪は滋賀県と余野川ダム、日吉ダム、一庫ダムと大阪や兵庫の水の貯水池があるので人口500万400万は多少大丈夫でしょう。猪名川の花火大会や大阪空港に近いこの川は田舎のようで大都会へすぐ通じていて、川の水も大変少ないのですが大人と子供が少し水で泳げたらと昔をなつかしんでいます。 どうかできる事ならヨシの葉アシの葉をふやし生態形を魚の住めるようにしてほしい。 |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございます。 河川の水質は、昭和30年代に始まる高度経済成長期から急激に悪化しましたが、水質汚濁防止法の制定や下水道整備の進捗等により改善されてきています。ただ、昨今微量有害物質など新たな物質について話題になったり、降雨初期による大気中の汚れ・市街地の汚れなどの面的な汚れの河川流入の問題があります。 今後は、河川やダム湖及び沿岸海域の水質及び底質の改善のためには、河川内での浄化対策では限界があり、流域から河川へ流入する汚濁負荷を減少させる対策等流域全体での取り組みを強力に進める必要があります。このため、現在の水質汚濁防止協議会を更に発展させ、自治体、関係機関、住民及び住民団体と連携して、河川の流入総負荷量管理を図る「琵琶湖・淀川流域水質管理協議会(仮称)」の設立を検討します。また、河川、湖及びダムの環境基準を達成することを目標とすることにとどまらず、生物及び生物の生息・生育環境から見て望ましく、安心して水辺で遊べ、水道水源としてより望ましい等の河川水質を新たな目標(生物指標による目標設定を含む)として設定し、監視地点、測定頻度や監視項目の増大等、平常時における監視を強化するとともに、自治体、関係機関、住民及び住民団体と連携を図り、流域をも対象とした情報の共有化を図っていきます。油やその他の化学物質の流出事故対応のため、即時的な水質監視体制の強化や住民による細かな水質モニタリングの支援体制を確立するほか、重金属、ダイオキシン類等の有害化学物質に関する水質及び底質モニタリングを実施し、生物及び生物の生息・生育環境にも配慮した改善対策を検討します。 河川環境は、これまでの流域における社会活動、河川の整備や利用が川に与えてきた影響を真摯に受け止め、水辺にワンドやたまりが数多く存在し、水位の変動によって冠水、撹乱される区域が広範囲に存在し、変化に富んだ地形と多用な生態系が形成されていた頃の河川環境を強く意識し、河川に応じた河川の横断的・縦断的形状の改善、残された環境の保全や失われた環境の再生等を目指すこととしています。河川環境を保全、再生して行くに際しては、「『川が川をつくる』のを手伝う」という考え方を念頭に実施するとともに、常に慎重にモニタリングを行い、河川環境の反応を把握、評価してフィードバックをしながら、また、関係機関、住民及び住民団体との連携を視野に入れて進めていきます。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
9
| 質問・意見 | 河川環境、治水、利水等いずれの視点についても実施項目の内容は具体性に欠けているように思われる。 一方、検討項目には具体的な内容が盛り込まれているように感じます。 ↓ 実施項目、検討項目のいずれについても、実施プログラムは作成されているのでしょうか?流域委員会が無駄に終わらないためにも決まっていることを“いつする”、検討を“いつする”といったプログラムをご提示願います。 また、当然のことながら、各主体の役割分担についても明確で、具体性があることを(推進方策)期待します。 以上 |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございました。 「淀川水系河川整備計画策定向けての説明資料(第2稿)」における実施項目や検討項目について、「説明資料(第2稿)に係る具体的な整備内容シート」に具体的な実施内容等を記載しています。なお、「説明資料(第2稿)に係る具体的な整備内容シート」は製本とCD-ROM版があり、要望される方には送付しております。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
10
| 質問・意見 | 前略扇千景大臣様、この度多田付近の公民館に於いて、先輩の方々と国交省設明会を聞いたときの、率直な、考えを述べますと、小四の時(S42)、私がこの地 京都より多田G.Hの工事の為父や母と三人で引っ越してきたとき、多田大橋の上の下に有る所で、初めて、広い川できれいな川で、建設現場の宿舎より夏になるといつもみんなで子供のとき、岩場の合い間より泳ぎました。たいへんきれいきれいな、それは美しい川でした。つりも国土開発の兄ちゃんとつり道具を借り毎日さ魚つりもしてました。水が、大水、台風のときS47夜間高校よりいせ口から帰るバスがとおれなく高台づたいにこわごわ西多田の方より帰ってきたとき濁流となり、旧移瀬より銀橋もとよりゴオーゴオー流れ危険でした。このように、鼓ヶ滝がはき出し口となり、水が増水時は、ノセ口に出ていった人が多田や東谷に戻れないというヒさんなありさまです。これは一庫ダムができても同んじ状態でした。 |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございました。 洪水時における鼓ヶ滝・銀橋付近の河川内の状況や多田地区等の家屋・道路等の浸水状況について、地元住民や自治体等からお聞きしています。 一庫ダムは、戦後の昭和28年・35年・42年の大水害を契機として昭和59年3月に完成しました。昭和47年の洪水は、ダム完成前のためダムで洪水を調節することができませんでした。ダム完成後は、平成14年までの20年間に7回洪水があり、その都度洪水調節を行ってきました。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |
11
| 質問・意見 | 私たちは、健康を保持・増進させる為、藻川・猪名川遊歩道を日頃より利用しておりますが、様々な点で改善の必要を感じております。 この遊歩道をより多くの市民が快適に、市民の憩いの場として、また健康増進の場としてより一層利用されるために、次の点について改善することを要望します。
|
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございました。
|
12
| 質問・意見 | 今日まで調査研究として使われた経費はどれくらいか?全てを明らかにすべしである。 平成15年3月末までに8億5240万円と聞いている。その後、どれ位かかるのか? |
|---|---|
| 回答 | ご意見ありがとうございました。 ご質問がございました費用等に関しましてはこちらを参照してください。 今後ともご意見を参考にさせていただき、今後の河川整備計画を策定する予定ですので、よろしくお願いします。 |