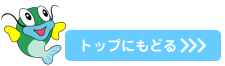琵琶湖の水質
主な水質調査
| 水の採取 | 透明度の測定 | 泥の採取 | プランクトンの採取 |
| COD(化学的酸素要求量)をはじめ、pH値や「富栄養化」の目安となる窒素・リンの量などを調べるため、採水をします。深い所の水をとるときには、バンドン式採水器を使います。 バンドン式採水器 | “透明度板”とよばれる直径30cmの白色の円板を使い、水深方向に何mまで見えるかはかります。びわ湖の場合、夏は北湖が5〜6m、南湖が2m。冬は北湖が10m、南湖が3mぐらいです。  透明度板 | 河底、湖底の泥にカドミウムやヒ素、PCB等の有害物質が混入していないかを調べるため採泥します。重さ10数kgもある“エクマンバージ採泥器”などを沈め、湖底の泥を採取します。  エクマンバージ採泥器 | 水中のプランクトンの量や種類を調べるため、“プランクトンネット”という大小の網を使ってプランクトンを採取します。口の大きなネットは深いところのプランクトンを、口の小さなネットで表層のプランクトンを、それぞれ約700Lと約50Lほどの水から採取しています。  プランクトンネット |
水質調査の主な項目
| 一般項目 | 水温や外観、臭気、透明度など |
| 生活環境に関する項目 | COD、BOD、pH値、総窒素、総リンなど |
| 健康に関した項目 | カドミウムやヒ素、PCBといった人の健康に有害な物質の有無を調べることなど |
水質の変化と現象
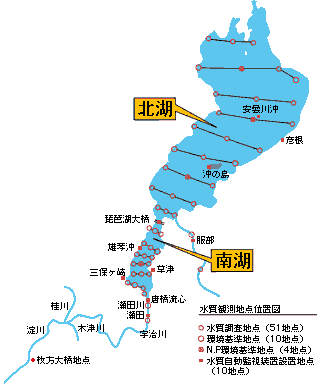 琵琶湖のような閉じられた水域では、ちっ素やリンなどの増加による富栄養化が問題となります。植物プランクトンが大量に発生し、寄り集まっておこる赤潮や水の華(アオコ)も、窒素やリンの量に左右されるといわれています。琵琶湖では、生ぐさ臭をともなう赤潮や、湖水が緑色のペンキを流したようになる水の華が毎年のように発生しています。また最近では、水道水に異臭味がつくといった問題もおこっています。
琵琶湖のような閉じられた水域では、ちっ素やリンなどの増加による富栄養化が問題となります。植物プランクトンが大量に発生し、寄り集まっておこる赤潮や水の華(アオコ)も、窒素やリンの量に左右されるといわれています。琵琶湖では、生ぐさ臭をともなう赤潮や、湖水が緑色のペンキを流したようになる水の華が毎年のように発生しています。また最近では、水道水に異臭味がつくといった問題もおこっています。
透明度
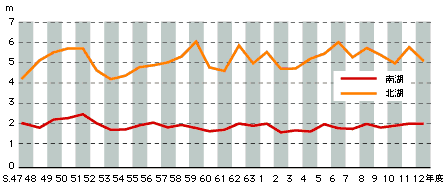 水面からどれくらいの深さまで見えるかを示す値です。直径30cmの白い円板に重りをつけ、水中に沈めていくと、その輪郭が見えなくなる深さがあります。この深さを透明度とします。透明度が4m以下になれば富栄養湖とされます。
水面からどれくらいの深さまで見えるかを示す値です。直径30cmの白い円板に重りをつけ、水中に沈めていくと、その輪郭が見えなくなる深さがあります。この深さを透明度とします。透明度が4m以下になれば富栄養湖とされます。 pH(水素イオン濃度指数)
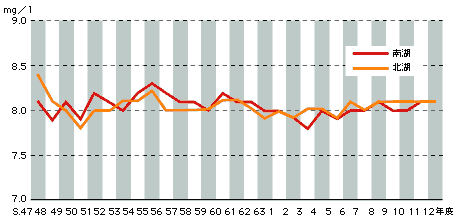 水の酸性、アルカリ性を示す指標です。中性の水はpH7で7より小さいものは酸性、7より大きいものはアルカリ性です。淡水湖は普通中性のpH7前後ですが、湖の表層で植物の光合成が盛んになるとpH値は高くなり、深層では有機物が分解されpH値は多少低くなります。
水の酸性、アルカリ性を示す指標です。中性の水はpH7で7より小さいものは酸性、7より大きいものはアルカリ性です。淡水湖は普通中性のpH7前後ですが、湖の表層で植物の光合成が盛んになるとpH値は高くなり、深層では有機物が分解されpH値は多少低くなります。 DO(溶存酸素)
水中に溶解している酸素のことです。有機物による汚染が著しいほど低い値を示します。一般に魚介類が生存するためにはDO 3mg/・以上が必要であり、良好な状態を保つためには5mg/・以上であることが望ましいとされています。SS(浮遊物質)
水中に浮遊している水にとけない物質で、粘土成分、プランクトンの死がいなどが含まれ、この値が高いと透明度の悪化、水中植物の生育阻害などが起きます。びわ湖の水を守る主な法律と条例
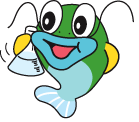
- ●水質環境基準のための[環境基本法]
- ●排水規制のための[水質汚濁防止法]
- ●湖沼水質保全計画のための[湖沼水質保全特別措置法]
- ●窒素やリン対策のための[びわ湖富栄養化防止条例]など
きれいな水を守るために私たちにできること。
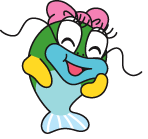
- ●三角コーナーや排水口に水切り袋をつけて、流れる残飯の量を減らす。
- ●食器や鍋などの汚れは、一度ふきとってから洗う。
- ●天ぷらで使った後の油などは凝固剤で固めたり、新聞紙にふくませて捨てる。
- ●洗濯には無リン洗剤や粉せっけんを使用し、使う量も正しく計ってよぶんな洗剤を流さない。
- ●米のとぎ汁も「富栄養化」の大きな原因。植木や畑の水やりに利用する。
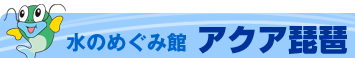
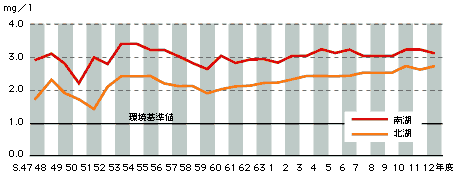 化学的酸素要求量の略語で、水中の有機物を酸化分解するときに必要な、酸素の量を示します。数値が大きいほど有機物の量が多いことになり、水は汚れています。
化学的酸素要求量の略語で、水中の有機物を酸化分解するときに必要な、酸素の量を示します。数値が大きいほど有機物の量が多いことになり、水は汚れています。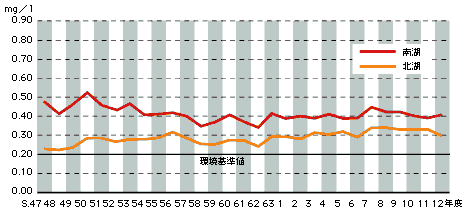 総窒素は水中にさまざまな化合物の形で溶け込んでいる窒素の総量を示します。窒素はリンとともに、湖沼の富栄養化の原因になります。
総窒素は水中にさまざまな化合物の形で溶け込んでいる窒素の総量を示します。窒素はリンとともに、湖沼の富栄養化の原因になります。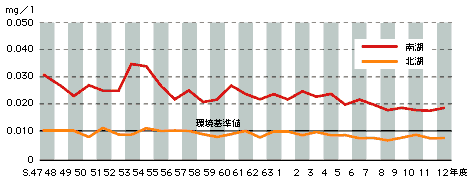 さまざまなリンの総量を示します。水中のリンの量は窒素の十分の一くらいにすぎませんが、やはり、富栄養化の原因となっています。
さまざまなリンの総量を示します。水中のリンの量は窒素の十分の一くらいにすぎませんが、やはり、富栄養化の原因となっています。