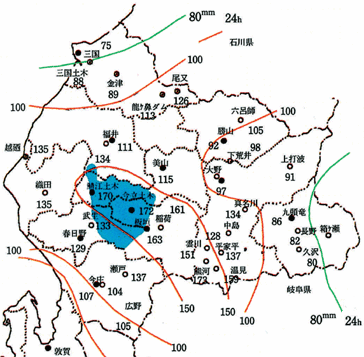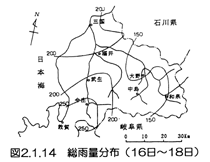
3) 台風24号(9月17~18日)
九頭竜川流域では、台風24号が潮岬を通過した午後6時頃から愛知県東部に上陸した午後10時頃まで強雨が続いた。
九頭竜川の布施田地点と日野川の深谷地点では警戒水位を越え、布施田で計画高水位下約0.1mまで達し、中角地点では計画高水位を突破した。このため、日野川や九頭竜川下流域の支川で増水し、各地で破堤や氾濫が続出した。
台風24号がもたらした降雨は、豪雨禍直後の奥越地方では幸いに200mm以下であった。むしろ、九頭竜川下流の河口部付近で降水量が多く、増水と相まって浸水被害が大きかった。また、今立郡今立町大滝では吉崎山が中腹から崩壊し、10人が死亡する大災害が発生した。
図2.1.14に総雨量分布を示す。
9月17日~18日の被害状況は、死者11人、重軽傷者29人、全壊・半壊・流失家屋数120戸な どであった。9月17日、18日には、武生市、鯖江市、今立町、清水町に災害救助法が発動された。
九頭竜川流域では、台風24号が潮岬を通過した午後6時頃から愛知県東部に上陸した午後10時頃まで強雨が続いた。
九頭竜川の布施田地点と日野川の深谷地点では警戒水位を越え、布施田で計画高水位下約0.1mまで達し、中角地点では計画高水位を突破した。このため、日野川や九頭竜川下流域の支川で増水し、各地で破堤や氾濫が続出した。
台風24号がもたらした降雨は、豪雨禍直後の奥越地方では幸いに200mm以下であった。むしろ、九頭竜川下流の河口部付近で降水量が多く、増水と相まって浸水被害が大きかった。また、今立郡今立町大滝では吉崎山が中腹から崩壊し、10人が死亡する大災害が発生した。
図2.1.14に総雨量分布を示す。
9月17日~18日の被害状況は、死者11人、重軽傷者29人、全壊・半壊・流失家屋数120戸な どであった。9月17日、18日には、武生市、鯖江市、今立町、清水町に災害救助法が発動された。
昭和40年(1965)9月の洪水による被害状況
(14) 昭和47年(1972)7月の梅雨前線による洪水
7月9日から17日にかけて、梅雨前線が活発となったため豪雨となった。九頭竜川流域では、日野川や九頭竜川上流域で1時間に40~60mmを記録するなど、主として日野川流域および真名川流域で集中豪雨による被害が生じ、深谷地点で警戒水位を越えた。
九頭竜川流域の被害は、床上浸水家屋数が96棟、床下浸水家屋数が1,580棟、農地および宅地等の浸水面積1,347ha、一般資産等被害額が433百万円であった。
7月9日から17日にかけて、梅雨前線が活発となったため豪雨となった。九頭竜川流域では、日野川や九頭竜川上流域で1時間に40~60mmを記録するなど、主として日野川流域および真名川流域で集中豪雨による被害が生じ、深谷地点で警戒水位を越えた。
九頭竜川流域の被害は、床上浸水家屋数が96棟、床下浸水家屋数が1,580棟、農地および宅地等の浸水面積1,347ha、一般資産等被害額が433百万円であった。
(15) 昭和47年(1972)9月の台風20号による洪水
台風20号は、9月16日午後6時30分頃に潮岬付近に上陸した後、福井県東部を通って17日午前3時に富山湾に抜けた。
15~16日の降雨量は、奥越地方で200mmに達した。そのため、中角・深谷地点で警戒水位を越す洪水となった。流域各地では、河川・砂防・道路などの公共施設に被害が生じた。
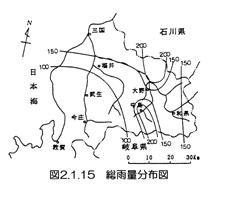
(16) 昭和50年(1975)の台風6号による洪水
台風6号は、8月23日未明に徳島県東部に上陸し、淡路島を通過したのち、午前8時頃に福井県小浜市を経て若狭湾に抜けた。その後、再び越前岬付近に上陸し、海岸線に沿って福井県を横断して東尋坊から能登半島に向かい、午前10時頃日本海に抜けた。
福井県下では、台風6号が四国の海上を北東に進んでいた22日午前7時半過ぎ頃から雨が断続的に降り始めた。その後、雷雨をともない23日午後5時頃まで降り続き、24日午前4時頃にやんだ。
総雨量は、九頭竜川本川上流山間部で300mmを突破し、平野部でも90mm近い降雨量となった。降雨が最も激しかったのは、台風6号が若狭湾を通過して越前岬に上陸し、海岸沿いを進んだ午前8~10時であった。図2.1.15に総雨量分布を示す。
九頭竜川本川の中角地点では、警戒水位を突破し、最高水位8.41mを記録した。また、深谷地点でも警戒水位を越え、最高水位が8.00mに達した。九頭竜川流域の被害は、床上浸水家屋数が6棟、床下浸水家屋数が166棟、農地および宅地等の浸水面積19haであった。
台風6号は、8月23日未明に徳島県東部に上陸し、淡路島を通過したのち、午前8時頃に福井県小浜市を経て若狭湾に抜けた。その後、再び越前岬付近に上陸し、海岸線に沿って福井県を横断して東尋坊から能登半島に向かい、午前10時頃日本海に抜けた。
福井県下では、台風6号が四国の海上を北東に進んでいた22日午前7時半過ぎ頃から雨が断続的に降り始めた。その後、雷雨をともない23日午後5時頃まで降り続き、24日午前4時頃にやんだ。
総雨量は、九頭竜川本川上流山間部で300mmを突破し、平野部でも90mm近い降雨量となった。降雨が最も激しかったのは、台風6号が若狭湾を通過して越前岬に上陸し、海岸沿いを進んだ午前8~10時であった。図2.1.15に総雨量分布を示す。
九頭竜川本川の中角地点では、警戒水位を突破し、最高水位8.41mを記録した。また、深谷地点でも警戒水位を越え、最高水位が8.00mに達した。九頭竜川流域の被害は、床上浸水家屋数が6棟、床下浸水家屋数が166棟、農地および宅地等の浸水面積19haであった。
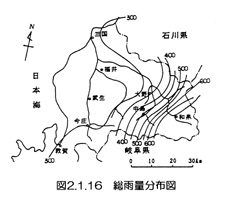
(17) 昭和51年(1976)の台風17号による洪水
台風17号は、9月13日午前2時前に長崎市付近に上陸し、その後、九州西端を縦断し、北東に向きを変えて日本海中部に去り、14日午前6時頃に温帯低気圧となった。
九頭竜川流域では、朝鮮半島の低気圧から南西に延びる寒冷前線の接近により、8日昼過ぎに雨が降り始め、10日の昼過ぎから九頭竜川流域の山間部で豪雨となった。九頭竜川本川流域では、
9月10日午後5時からの12時間に箱ヶ瀬294mm、真名川流域では午後4時からの9時間に笹生川ダム163mmを記録した。箱ヶ瀬では、8日の降り始めから13日までの6日間で869mmの大雨となったため、九頭竜ダムでは完成後始めて洪水吐ゲートから放流し、洪水調節を行った。
13日に台風17号が日本海に入り接近すると、再び九頭竜川本川上流山間部で豪雨となったが、14日未明になって6日間連続した降雨もやんだ。
図2.1.16に総雨量分布を示す。
九頭竜川本川の中角地点では、10日からの豪雨によって警戒水位を越え、8.88mの最高水位を記録した。また、日野川も増水し深谷地点で警戒水位を越えた。
九頭竜川流域の被害は、床上浸水家屋数が10棟、床下浸水家屋数が369棟、農地および宅地等の浸水面積72ha、一般資産等被害額が237百万円であった。
台風17号は、9月13日午前2時前に長崎市付近に上陸し、その後、九州西端を縦断し、北東に向きを変えて日本海中部に去り、14日午前6時頃に温帯低気圧となった。
九頭竜川流域では、朝鮮半島の低気圧から南西に延びる寒冷前線の接近により、8日昼過ぎに雨が降り始め、10日の昼過ぎから九頭竜川流域の山間部で豪雨となった。九頭竜川本川流域では、
9月10日午後5時からの12時間に箱ヶ瀬294mm、真名川流域では午後4時からの9時間に笹生川ダム163mmを記録した。箱ヶ瀬では、8日の降り始めから13日までの6日間で869mmの大雨となったため、九頭竜ダムでは完成後始めて洪水吐ゲートから放流し、洪水調節を行った。
13日に台風17号が日本海に入り接近すると、再び九頭竜川本川上流山間部で豪雨となったが、14日未明になって6日間連続した降雨もやんだ。
図2.1.16に総雨量分布を示す。
九頭竜川本川の中角地点では、10日からの豪雨によって警戒水位を越え、8.88mの最高水位を記録した。また、日野川も増水し深谷地点で警戒水位を越えた。
九頭竜川流域の被害は、床上浸水家屋数が10棟、床下浸水家屋数が369棟、農地および宅地等の浸水面積72ha、一般資産等被害額が237百万円であった。
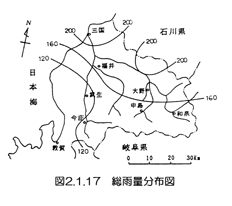
(18) 昭和56年(1971)7月の梅雨前線による洪水
東海地方東部から能登半島にかけて停滞していた梅雨前線が、次第に活発となり7月1日午後から雨を降らせ始めた。2日早朝には、九頭竜川流域の山間部で1時間に10mmを越す降雨が観測された。また、今庄では2日午後5時に1時間に32mmの局地的な豪雨となった。
7月1日の降り始めから2日午後9時までの雨量は、三国で123mm、福井で63mm、六呂師155mm、上打波123mmと九頭竜川流域の北部を中心に強雨となった。
3日には三国で1時間に42mm、勝山で31mm、中島で40mm、長野で30mmの激しい雷雨が発生した。1日~2日の降雨の上に、3日の短時間豪雨によって災害となった。
7月1日の降り始めから3日までの降雨量は、九頭竜川本川流域の勝山で230mm、日野川流域の今庄で100mm、足羽川流域の美山で177mmであった。図2.1.17に総雨量分布を示す。
九頭竜川本川の中角地点において、警戒水位を突破し、8.96mの最高水位を記録した。日野川の深谷地点では、警戒水位を越えて最高水位が6.96mを記録した。九頭竜川本川下流布施田地点では、警戒水位下0.3mまで達した。足羽川の幸橋地点では、警戒水位8.00mを突破し、9.86mの最高水位を記録した。
福井平野の下流の竹田川では、堤防を越水し、金津町営住宅が軒下まで浸水したのを始め、多くの家屋や田畑が浸水した。一方上流では、勝山市の滝波川や宮前川、永平寺町の永平寺川、美山町の大谷川で激流が溢れ、道路や水田を流れた。福井市の市内低地では、浸水被害が発生した。
九頭竜川流域の被害は、全壊流失・半壊家屋数が21棟、床上浸水家屋数が624棟、床下浸水家屋数が2,356棟、農地および宅地等の浸水面積3,756ha、一般資産等被害額が3,476百万円であった。
東海地方東部から能登半島にかけて停滞していた梅雨前線が、次第に活発となり7月1日午後から雨を降らせ始めた。2日早朝には、九頭竜川流域の山間部で1時間に10mmを越す降雨が観測された。また、今庄では2日午後5時に1時間に32mmの局地的な豪雨となった。
7月1日の降り始めから2日午後9時までの雨量は、三国で123mm、福井で63mm、六呂師155mm、上打波123mmと九頭竜川流域の北部を中心に強雨となった。
3日には三国で1時間に42mm、勝山で31mm、中島で40mm、長野で30mmの激しい雷雨が発生した。1日~2日の降雨の上に、3日の短時間豪雨によって災害となった。
7月1日の降り始めから3日までの降雨量は、九頭竜川本川流域の勝山で230mm、日野川流域の今庄で100mm、足羽川流域の美山で177mmであった。図2.1.17に総雨量分布を示す。
九頭竜川本川の中角地点において、警戒水位を突破し、8.96mの最高水位を記録した。日野川の深谷地点では、警戒水位を越えて最高水位が6.96mを記録した。九頭竜川本川下流布施田地点では、警戒水位下0.3mまで達した。足羽川の幸橋地点では、警戒水位8.00mを突破し、9.86mの最高水位を記録した。
福井平野の下流の竹田川では、堤防を越水し、金津町営住宅が軒下まで浸水したのを始め、多くの家屋や田畑が浸水した。一方上流では、勝山市の滝波川や宮前川、永平寺町の永平寺川、美山町の大谷川で激流が溢れ、道路や水田を流れた。福井市の市内低地では、浸水被害が発生した。
九頭竜川流域の被害は、全壊流失・半壊家屋数が21棟、床上浸水家屋数が624棟、床下浸水家屋数が2,356棟、農地および宅地等の浸水面積3,756ha、一般資産等被害額が3,476百万円であった。
昭和56年7月の洪水時の被害状況
(19) 昭和58年(1973)の台風10号および秋雨前線による洪水
28日午前10頃長崎県に上陸した台風10号は、九州北部を横切り午後3時に四国の宿毛付近において温帯低気圧となり、本州の南岸沿いに東進した。このとき、秋雨前線が刺激され、日野川流域で雨が9月27日早朝より降り始め、28日深夜まで続いた。
日野川流域の今庄では時間最大雨量18mm、総雨量177mm、織田で時間最大雨量22mm、総雨量183mm、武生で時間最大雨量16mm、総雨量186mmと流域で平均的に降り、42時間降り続いた。
日野川の水位は徐々に高くなり、三尾野では警戒水位5.50mを越え、最高水位が5.74mに達した。また、深谷でも警戒水位を上回り、最高水位が6.17mとなった。
九頭竜川流域の被害は、床上浸水家屋数が5棟、床下浸水家屋数が292棟、農地および宅地等の浸水面積234ha、一般資産等被害額が382百万円であった。
(20) 平成元年(1989)9月の前線による洪水
能登半島に停滞していた前線を南海上の湿った風が刺激したため、前線の活動が活発になり大雨となった。雨は、5日午後1時から7日午後5時まで断続的に続いた。各地の総雨量は、大野で162mm、勝山153mm、福井94mmであった。特に、福井市では7日午前10時からの1時間に23mmを記録した。その他の地域でも、この1時間に17~20mmの局地的な豪雨が発生した。
九頭竜川流域の被害は、床上浸水家屋数が6棟、床下浸水家屋数が381棟、農地および宅地等の浸水面積約25ha、一般資産等被害額が225百万円であった。
(21) 平成元年(1989年)9月の台風22号による洪水
停滞していた秋雨前線が、台風22号に刺激されて活動し、18日午後2時頃から雨が降り出した。19日午前中からは台風22号の接近によって雨が激しく降り、午後1時過ぎには福井市や武生市で1時間雨量が30mmを越えた。
18日午後2時から19日午後11時までの降水量は、武生市で183mm、大野市230mm、福井市129mm、勝山市121mm、和泉村124mm、美山で109mmであった。
九頭竜川流域の被害は、床上浸水家屋数が1棟、床下浸水家屋数が329棟、農地および宅地等の浸水面積約22ha、一般資産等被害額が844百万円であった。
(22) 平成10年(1998)7月の梅雨前線による洪水
7月10日未明に日本海海上にあった梅雨前線が、福井県付近まで南下し、九頭竜川流域に強雨をもたらした。雨は10日午前5時頃から降り始め、各地で1時間に30mmを越える強い雨となった。10日午前11時までの6時間に、武生122mm、織田117mmなどを記録した。また、24時間最大雨量は、鯖江(福井県鯖江土木事務所)で170mm、今立(福井県今立土木事務所)で172mmであった。
集中豪雨によって浅水川では、黒津観測所の水位観測器能力の上限値(13.6m)を越す水位が約4時間も続き、支川の鞍谷川松成観測所でも警戒水位を突破し、一部の区間では、堤防から越水した。このため、鯖江市に陸上自衛隊115名が緊急派遣された。
日野川では、三尾野と久喜津の2観測所で警戒水位を越えた。
九頭竜川流域での被害は、家屋の一部損壊1棟、床上浸水68棟、床下浸水494棟で、被害額は公共土木・農業用施設で約30億円であった。このうち、浅水川の越水氾濫によって、鯖江市と今立町では床上浸水60戸、床下浸水444戸等の被害が生じた。
建設省と福井県は、越水被害の再発防止を図るため、「災害助成事業」および「災害復旧等関連緊急事業・基幹河川改修」で、復旧工事を進めるとともに、上流部の改修効果を高めるために下流部の改修を同時に行い、上下流のバランスに配慮した治水事業を平成10年度より進めている。
28日午前10頃長崎県に上陸した台風10号は、九州北部を横切り午後3時に四国の宿毛付近において温帯低気圧となり、本州の南岸沿いに東進した。このとき、秋雨前線が刺激され、日野川流域で雨が9月27日早朝より降り始め、28日深夜まで続いた。
日野川流域の今庄では時間最大雨量18mm、総雨量177mm、織田で時間最大雨量22mm、総雨量183mm、武生で時間最大雨量16mm、総雨量186mmと流域で平均的に降り、42時間降り続いた。
日野川の水位は徐々に高くなり、三尾野では警戒水位5.50mを越え、最高水位が5.74mに達した。また、深谷でも警戒水位を上回り、最高水位が6.17mとなった。
九頭竜川流域の被害は、床上浸水家屋数が5棟、床下浸水家屋数が292棟、農地および宅地等の浸水面積234ha、一般資産等被害額が382百万円であった。
(20) 平成元年(1989)9月の前線による洪水
能登半島に停滞していた前線を南海上の湿った風が刺激したため、前線の活動が活発になり大雨となった。雨は、5日午後1時から7日午後5時まで断続的に続いた。各地の総雨量は、大野で162mm、勝山153mm、福井94mmであった。特に、福井市では7日午前10時からの1時間に23mmを記録した。その他の地域でも、この1時間に17~20mmの局地的な豪雨が発生した。
九頭竜川流域の被害は、床上浸水家屋数が6棟、床下浸水家屋数が381棟、農地および宅地等の浸水面積約25ha、一般資産等被害額が225百万円であった。
(21) 平成元年(1989年)9月の台風22号による洪水
停滞していた秋雨前線が、台風22号に刺激されて活動し、18日午後2時頃から雨が降り出した。19日午前中からは台風22号の接近によって雨が激しく降り、午後1時過ぎには福井市や武生市で1時間雨量が30mmを越えた。
18日午後2時から19日午後11時までの降水量は、武生市で183mm、大野市230mm、福井市129mm、勝山市121mm、和泉村124mm、美山で109mmであった。
九頭竜川流域の被害は、床上浸水家屋数が1棟、床下浸水家屋数が329棟、農地および宅地等の浸水面積約22ha、一般資産等被害額が844百万円であった。
(22) 平成10年(1998)7月の梅雨前線による洪水
7月10日未明に日本海海上にあった梅雨前線が、福井県付近まで南下し、九頭竜川流域に強雨をもたらした。雨は10日午前5時頃から降り始め、各地で1時間に30mmを越える強い雨となった。10日午前11時までの6時間に、武生122mm、織田117mmなどを記録した。また、24時間最大雨量は、鯖江(福井県鯖江土木事務所)で170mm、今立(福井県今立土木事務所)で172mmであった。
集中豪雨によって浅水川では、黒津観測所の水位観測器能力の上限値(13.6m)を越す水位が約4時間も続き、支川の鞍谷川松成観測所でも警戒水位を突破し、一部の区間では、堤防から越水した。このため、鯖江市に陸上自衛隊115名が緊急派遣された。
日野川では、三尾野と久喜津の2観測所で警戒水位を越えた。
九頭竜川流域での被害は、家屋の一部損壊1棟、床上浸水68棟、床下浸水494棟で、被害額は公共土木・農業用施設で約30億円であった。このうち、浅水川の越水氾濫によって、鯖江市と今立町では床上浸水60戸、床下浸水444戸等の被害が生じた。
建設省と福井県は、越水被害の再発防止を図るため、「災害助成事業」および「災害復旧等関連緊急事業・基幹河川改修」で、復旧工事を進めるとともに、上流部の改修効果を高めるために下流部の改修を同時に行い、上下流のバランスに配慮した治水事業を平成10年度より進めている。
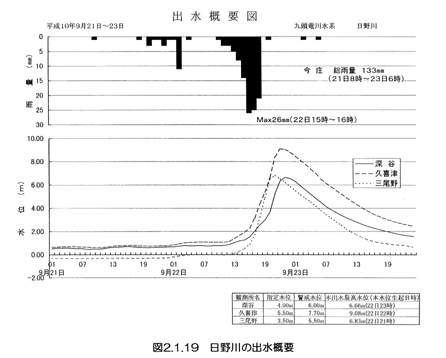
(23) 平成10年(1998)9月の台風7号による洪水
9月22日に和歌山県に上陸した中型で並の強さの台風7号は、九頭竜川流域に21日に20mm程度の雨を降らせ、22日午後から100mmを越える降雨をもたらした。特に、午後4時~6時頃の間に、各所で最大時間雨量30~50mmを記録した。雨は午後8時頃やんだ。
日野川では、22日午後5時頃から水位が急激に上昇し、三尾野、久喜津、深谷の各観測地点で警戒水位を突破し、深谷地点では最高水位が6.66mに達した。
九頭竜川流域では、日野川筋の朝日町・宮崎村が被害を受け、織田町では9月22日午後5時に災害対策本部を設置した。
朝日町では21棟が床上浸水、31棟が床下浸水した。宮崎村では天王川が越水したため、江波地区で25棟が床上浸水、29棟が床下浸水した。被害額は、公共土木・農業用施設で約81億円であった。
朝日町・宮崎町では305世帯1,252人に避難勧告を発令し、86世帯264人が避難した。また、福井市などでは、河川の氾濫などに備えて100余人が自主避難した。
※「梅雨前線と台風7号等による被害概要と対応状況 平成10年12月」 福井県消防防災課
9月22日に和歌山県に上陸した中型で並の強さの台風7号は、九頭竜川流域に21日に20mm程度の雨を降らせ、22日午後から100mmを越える降雨をもたらした。特に、午後4時~6時頃の間に、各所で最大時間雨量30~50mmを記録した。雨は午後8時頃やんだ。
日野川では、22日午後5時頃から水位が急激に上昇し、三尾野、久喜津、深谷の各観測地点で警戒水位を突破し、深谷地点では最高水位が6.66mに達した。
九頭竜川流域では、日野川筋の朝日町・宮崎村が被害を受け、織田町では9月22日午後5時に災害対策本部を設置した。
朝日町では21棟が床上浸水、31棟が床下浸水した。宮崎村では天王川が越水したため、江波地区で25棟が床上浸水、29棟が床下浸水した。被害額は、公共土木・農業用施設で約81億円であった。
朝日町・宮崎町では305世帯1,252人に避難勧告を発令し、86世帯264人が避難した。また、福井市などでは、河川の氾濫などに備えて100余人が自主避難した。
※「梅雨前線と台風7号等による被害概要と対応状況 平成10年12月」 福井県消防防災課