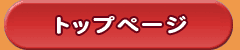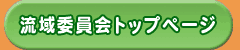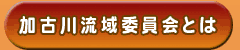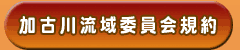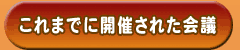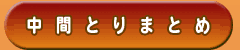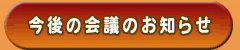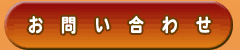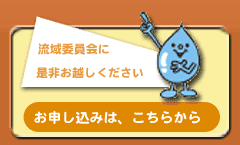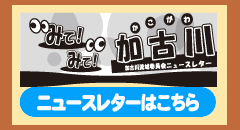- 日 時:平成20年10月29日(水)10:05〜12:05
- 場 所:西脇市生涯学習まちづくりセンター マナビータ・ホール
- 出席者:委員12名、国土交通省10名、自治体関係者1名、傍聴者23名
1.今回の議題について
加古川の河川整備計画に反映させる河川整備の内容について、洪水の選定、洪水の概要、治水メニューの検討、環境の課題整理、考えられる具体策について審議を行いました。
議題
河川整備内容について
2.第3回加古川流域委員会審議内容の報告
【説明概要】
加古川流域委員会庶務より、前回の第3回加古川流域委員会審議内容の確認が行われました。概要を以下にまとめます。
●議論のポイントは、闘竜灘、自然環境(河口干潟など)、加えて利水や河川空間利用などについての総合的な検討です。
●考えられる具体策(複数)について議論し、河川管理者が原案を策定することが確認されました。
3.河川整備の内容について
【説明概要】
河川管理者より、河川整備の内容について説明が行われました。概要を以下にまとめます。
●加古川でこれまで発生した洪水の中から、今後20〜30年間で整備する河川整備の内容を検討していく上でまず、基本高水規模の阿久根台風を除き、その他の近年発生した大きな洪水で水文資料が整っている、平成16年10月20日洪水、平成2年9月20日洪水、昭和58年9月28日洪水の3つを整備計画の目標とすべき洪水の候補に選びました。
●これら3洪水は、これまでの洪水の中でも非常に規模が大きく、目標として正しいと考えておりますが、確かにあの時のあの洪水はこんな洪水だったなという実体験を通じた思いを委員(住民)のみなさまと河川管理者が共有したいと考えています。
●環境上の課題(生物の生息・生育環境[瀬・渕、わんど・たまり、水際植生、レキ河原、河口干潟]、魚類の遡上など)を整理し、考えられる具体策をとりまとめました。例えば平成16年10月洪水を対象にすると、河口部の干潟や上流部の闘竜灘にも何らかの改修が必要になりますが、改修の方法についてはいろいろな工夫があると考えています。
【意見および質疑応答】
○阿久根台風は河川整備基本方針レベルの洪水を住民が経験したという意味で重要だと思います。阿久根台風を単に除くのではなく、河川整備基本方針で目標とする洪水をイメージし、その枠の中で20〜30年間で整備する河川整備計画を位置づけるという共通認識を流域の方に持っていただくことが非常に重要だと思います。(道奥委員)
○実績浸水区域図で堤防から離れたところで浸水がありますが、地形要因や下水道等の関連もあると思います。それらについても情報を提供頂けませんか。(玉岡委員)
→(河川管理者による回答)このような氾濫のことを内水氾濫と呼んでいます。内水氾濫にもいろいろな原因がありますので、主だった箇所の氾濫原因を整理して説明します。
○加古川の大きな特徴に中州があると思います。『播磨国風土記』にも書かれているぐらい昔からの特徴ある地形ですが、中州に茂った樹木の伐採や土砂の除去など、治水対策の議論を行う上で重要なので、この説明もお願いします。(玉岡委員)
→(河川管理者による回答)中州がどういうところにあるかを、今回の資料(環境上の課題の整理の箇所)中の図でお示しします。
○ヤナギ群落は河川にとって非常に重要な群落なので、その位置づけを検討していただければと思います。(服部委員)
→(河川管理者による回答)環境と治水のバランスは、河川整備計画をつくるにあたって一番議論になるところです。樹木の状況についても、残すべきもの、あるいは治水上問題のあるもの等についてのご意見を頂きたいと思います。
○空間分布、時間分布を考慮して洪水の選定を行うべきだと思います。(道奥委員)
→(河川管理者による回答)空間分布については原案にある程度考慮されていると考えています。
時間分布については、雨が長時間ダラダラと続く洪水についても考えていきたいと思います。
○洪水の選定で、浸水家屋だけでなく、農業関係の被害からも検討してほしい。(内田委員)
→(河川管理者による回答)農業被害についてはデータの有無を確認し、できるだけ整理します。
○河口干潟の掘削は環境への影響が大きいだけで、効果がないのではないでしょうか。(増田委員)
→(河川管理者による回答)河口域は高潮の影響で河積を広げても疎通能の向上効果が発揮されない場合もあります。干潟部分の掘削の効果については次回までに整理して説明します。
○干潟は上流から流れてくる砂レキによって成立しており、もし上流から砂レキが流れてこなくなれば自然に消滅してしまいます。干潟を検討するに際しては砂レキのところ、砂州、河川敷などをトータルに考える必要があると思います。(畠山委員)
→(河川管理者による回答)河道掘削というのは大変難しく、どこかを掘削すると他の場所で土砂がたまったり洗掘されたりします。掘削する場合には、干潟の状況などの様子をみながら徐々に進める必要があると考えています。
○ハザードマップで危険な箇所とされているところで開発を許可しているところがあります。今後は、開発の規制が必要ではないでしょうか。(畠山委員)
→(河川管理者による回答)危険箇所の開発規制などは、流域市町と情報共有しながら河川整備計画の流域対策として、計画に盛り込んでいきたいと考えています。
○上流で水を貯めて下流を守るという全体的視点から、例えば、ため池、森林保全など保水能力の視点からのアプローチを欠かしてはならないと思います。(池本委員)
→(河川管理者による回答)ため池や森林については、今の状況を保全していくことを、河川整備計画の中で明確に書いていくことになると考えています。
○前回の河川整備基本方針の説明で、「基本高水流量9,000m3/秒に対して1,600m3/秒はどこかでためる」という話がありましたが、それと先程のご発言の保水との関係を教えてください。(田辺委員)
→(河川管理者による回答)川に流れる洪水をダムや遊水地でためて、流量を少なくするというのが前回の説明です。先程の保水の話は、川に入ってくる前にどれだけためることができるかという話です。
○治水を考えると、中州や干潟よりも断面確保の効果が大きい、スポーツなどに利用している高水敷の掘削について検討していくことも必要だと思います。(播本委員)
→(河川管理者による回答)河川利用と治水のバランスをとることが重要です。環境と治水のバランスと同様、河川利用の観点からの御意見を頂きながら、どういう河道断面にしていくのかということを考えていきたいと思います。
4.傍聴者からの発言
○ため池の利用、森林保全について、現在の保水力を確保するだけでは決して十分ではなく、もっと手入れをしていく必要があると思います。
5.次回へ向けた討議のまとめ
今後20〜30年間で整備する河川整備の内容を検討していく上で目標とすべき三つの洪水の選び方で、時間分布の異なるダラダラ雨を追加することや、洪水による農業被害を考慮することが議論されましたが、基本的に一番大きな洪水を選んでいることから、洪水選定の考え方としては妥当であることが確認されました。
また整備の具体策として、例えば、三つの洪水の中で最も規模の大きい平成16年10月洪水を対象にすると、河道の掘削量が膨大になり、河口干潟や闘竜灘などへの環境上の影響が懸念されます。これらの影響に対しては、中州の掘り方、高水敷の残し方など、いろいろな工夫が必要になり、次回以降の具体的な対策検討の重要性が確認されました。
6.今後の予定
第6回以降の加古川流域委員会は
- 1月21日(水)午後、
- 2月18日(水)午後、
- 3月25日(水)午前
を候補日とします。
次回の第5回加古川流域委員会は12月18日(木)午前中を予定します。