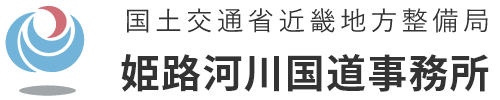第20回懇談会
日時 : 平成13年10月12日
場所 : グリーンヒルホテル明石
明石海岸の海中散歩-最近の海水汚染は深刻について
明石市特殊奉仕団 水難救助隊々長 水中写真家 南正一氏
魚の住める海水を「きれいな海」と呼びたい。つまりきれいな水でなければ魚は住めない。「魚の住める海」とは、
- エサが豊富であるところ
- 身を守ったり隠れたり出来るところ
- 卵を産めるところ
すなわち「魚のマイホーム」である。
ウミウチワは群生しており、畳一畳ぐらいになるところがある。また、サンショウウニ、アメフラシ、マナマコ、マボヤなども生息している。
放置された漁網の周りには魚が寄りつかない。 漁業者は網を引っかけるとそのまま放置し、引き上げることはない。そして、同じところで、同じように引っかけるので、漁網はどんどん積み重なる。現在の漁網はなかなか腐らないので、そのまま長期間残る。
海の中までは見えないので、10年程前までは毎年、仏壇、標識、バイク、冷蔵庫など色々なものが捨てられていた。しかし近年はマナーが向上したのか、海底のゴミが少なくなった。 川は以前に比べて随分きれいになっているが、海の中はまだ気づかない点がたくさんある。
美しい海を目指して皆さんと協力していきたいと考えている。
「海の汚れの4割が家庭排水です。この汚れた川や海を少しでもきれいにするために、いま私たちは身近な暮らしの中で工夫し、実践していかなければなりません。
今こそ、自然の厳粛さに目覚め、自然を尊び、自然の調和を損なうことなく節度ある利用に努め、自然環境の保全に国民の総力を結集すべき時です。美しい自然、大切な自然を末永く子孫に伝えようではありませんか。」
【海浜植生の危機】
- 海浜植物は、海浜でしか生きていけない。
- 自然植生は、植物全体の約20%しか残っておらず、その中でも特に、海浜植物は、0.7%と極めて少ない。この数値は、高山植物(0.3%)に次ぐ値であり、如何に海浜植物が希少であるか分かる。しかしながら、大変貴重がられ、しかも手厚い保護を受けている高山植物に対して、海浜植物はその希少性が認識されないまま、粗雑に扱われている。
- この希少な海浜植物が生息する自然海浜も減少し続けている。
- 海浜植物を圧迫する要因としては「内湾の埋め立てや防潮堤の建設」による海浜の減少と「レジャー関連施設の建設、海水浴場やキャンプ場の整備」「オフロード車の侵入」(下記写真参照)が挙げられ、現存する自然海浜の保護に加えて、海浜植物の保護も必要である。
淡路島の海水浴場における海浜植物の保全に向けて-人工海浜を用いた保全を考える
法務局人権擁護委員 神足徹雄氏
東播海岸の東端にあたる神戸市塩屋の「明石の節渕」から西に向かって進み、明石市を経て「ジョセフ・ヒコ碑」のある播磨町までの東播海岸沿岸周辺に点在する名所・旧跡について、その由来とそこにまつわる逸話をご紹介いただき、先人達が愛して止まなかった東播海岸への愛着をもっと深めてほしいと訴えられた。
また、こうした貴重な海岸環境の大事さと海岸整備との調和の必要性を説かれた。
質疑応答
Q.人工的に養浜した場合、その仕方によっては悪影響が出てくるものなのか?(那須姫路工事事務所長)
A.養浜した海は驚くほど美しい。これは、打ち上げる波が砂によって濾過されることによる。その一方で波が砂を運ぶため、次々と砂を補った結果、悪影響を及ぼす貝類や菌類が増加している。流されたものをそのままにするのではなく、元に戻すことで、ある程度問題は解消されるように思う。(南氏)
Q.昔、舞子の浜や明石の港には茶屋などが立ち並び、にぎわいのある風景であったということだが、それを示す絵図などは残っているのか?(加納委員)
A.橋本海関が「明石名勝古事談」を残しており、1~10巻に明石の歴史や名所を紹介している。当時の舞子・中崎海岸には阪神から訪れる海水浴客用の旅館が立ち並んでいたとのことである。(神足氏)
【人工海浜への植栽について】
- 広さが十分にあるのだから、もっと木を植えてもらいたい。植物は酸素を供給したり、沿岸に影をつくって魚に産卵の場を提供したりする。魚を守るためにも、今後人工的な海浜をつくる際には、どんどん植栽してもらいたい。(南氏)
- 普通の木では潮風によってすぐに枯れてしまうので、海浜植物を広い砂浜に集めて、植物園などをつくってもらいたい。山と海は川を通じて繋がっている。海岸だけではなく、遠く離れた場所に植栽することでも効果を得られるはずである。どこでもかまわないのでたくさんの植物を植えてもらいたい。(聴講者)
- 我々も海浜植物の復元に興味を持っている。今後検討したい。(那須姫路工事事務所長)
- 事務局は昨年から試験的ではあるが、海浜植生の復元を目指している。具体的には、ハマボウフウなどの自生に取り組んでいるところである。(事務局)
事務局からの補足説明
【改正海岸法について】
- 昭和31年の海岸法制定で現行のような体制が整った。
- 当時の海岸法の概念は台風や大地震等による高潮・波浪・津波等から人命や資産を防護するという役割を担ってきた。
- 近年、環境保護への意識の高まりや海岸域の植生が破壊されているなど種々の問題が出てきているため海岸制度の改正が必要となってきた。
- 以上の状況を踏まえ、海岸4省庁(農林水産省・水産庁・運輸省・建設省)が取り組み、平成11年に海岸法が一部改正された。
- 改正海岸法の主なポイントは、
- 1.防護一点張りではなく、環境・利用も含めた調和のとれた総合的な海岸管理制度の創設
- 2.地域の意見を反映した海岸整備の計画制度の創設
【海岸植生の復元について】
- 平成12年度に2回(6月・9月)、松江漁港の西側で植栽試験を行っている。
- 昨年6月に植栽したものは、秋までに枯れてしまい、ほとんど残っていない。
- 昨年9月に植栽したものは、今年7月現在で当時の約65%が残っている。
- 種類は瀬戸内海に多く見られる7種類を選定。
- ハマナデシコ、ハマエンドウ、ハマダイコン、ハマボウフウ、
- ハマボッス、ハマヒルガオ、ハマゴウ