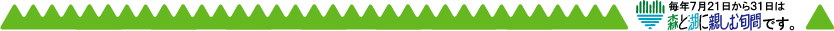 |
|
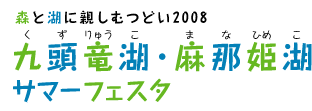 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
||||||
 |
|
 |
||||||
 |
 |
 |
| お問合せ:「森と湖に親しむ旬間」全国行事現地実行委員会事務局 TEL.0779-66-5300 E-mail info-kuzuryu@kkr.mlit.go.jp |
 |
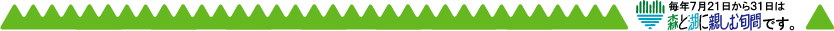 |
|
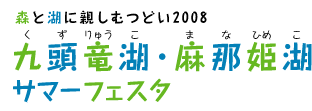 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
||||||
 |
|
 |
||||||
 |
 |
 |
| お問合せ:「森と湖に親しむ旬間」全国行事現地実行委員会事務局 TEL.0779-66-5300 E-mail info-kuzuryu@kkr.mlit.go.jp |
 |