釣りと海とのいい関係を模索中〈3〉
NPO法人 釣り文化協会代表 來田仁成さん
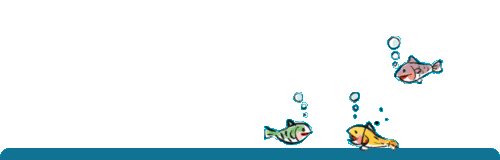 |
||||
日曜日に「大阪南港魚釣り園」に行くと、聞けば釣りのノウハウを伝授してくれる人たちがいる。「公認釣りインストラクター」の資格を持つ |
||||
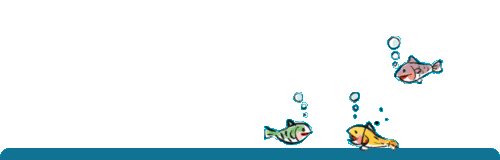 |
||||
日曜日に「大阪南港魚釣り園」に行くと、聞けば釣りのノウハウを伝授してくれる人たちがいる。「公認釣りインストラクター」の資格を持つ |
||||
「茅渟(ちぬ)の海」再び・・ |
||
來田さんが「釣れなくなった」とお感じになったのはいつごろでしたか?昭和40年代でしょうか。ちょうど高度経済成長期。大阪湾の埋立が進み、コンクリート護岸が増え、海辺の風景が激変すると共に、田畑には農薬が使われ、ゴミの質も量も変わってきていたころ。魚の産卵場が激減したばかりか餌,水温など魚をとりまくあらゆる環境が変わったから大阪湾の魚が減ったと、釣りを切り口に気づいたんですね。 |
||
「美しい大阪湾」を取り戻さなければ、釣りができなくなると?そう。何か行動できないかと思うようになった。大阪府にも話を聞いてもらい、白浜にある近大水産試験場にチヌを養殖して育ててくれるように掛け合って・・。まず24年前から、釣りクラブの集合体である (社)大阪府釣り団体協議会で、チヌの稚魚の放流を始めたんです。以来、水温のピークである8月末に、毎年2万匹放流しています。 |
||
放流した稚魚が、大阪湾で育っているわけですね。4年で成魚になるといわれますので、大阪湾にはチヌが確実に増えてきているはずです。 |
||