釣りと海とのいい関係を模索中〈4〉
NPO法人 釣り文化協会代表 來田仁成さん
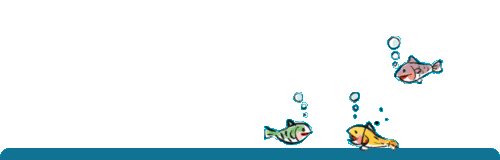 |
||||
日曜日に「大阪南港魚釣り園」に行くと、聞けば釣りのノウハウを伝授してくれる人たちがいる。「公認釣りインストラクター」の資格を持つ |
||||
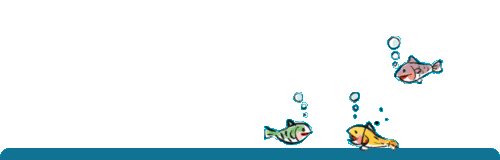 |
||||
日曜日に「大阪南港魚釣り園」に行くと、聞けば釣りのノウハウを伝授してくれる人たちがいる。「公認釣りインストラクター」の資格を持つ |
||||
調査は、どんなふうに行うのですか?
「水色見本」で海の色を確認した後、バケツで表層、リサイクルのペットボトルで作った採取器で底層の水を組みあげ、水温、比重、pH、DO(容存酸素)、塩分濃度を計り、古いCDプレートの透明度計で光がどこまで届いているかを見て記録。子どもさんにも出来る簡単な方法で、モニターの方にも釣りに行った時などに随時お願いしているんです。主体的に調査することによって、海の環境への関心がよりいっそう高まればと思っています。 |
|||
普段の釣りに加えて調査によって、改めて気づかれたことはありましたか。ありますよ。8月下旬に、尼崎港付近〜甲子園浜にかけての一帯で、青潮が発生しました。 青潮は、水質、底質が悪化した結果、大量発生したプランクトン(赤潮)が沈んだことにより起きた貧酸素状態の中で、嫌酸素プランクトンが硫化水素を発生させます。この水塊が、陸風の影響で表層にわき上がると、硫化水素の結晶ができてる状態のこと。水面が青くなり、温泉と同じ硫黄の匂いがして貝類、カニ類、小魚類が大量死するほか、数日経つと海辺は死んだ生物のため悪臭が漂いますが、8月初旬から予兆が出ていたことが,調査データから判明しました。 (1) 海底の溶存酸素が2〜3%と低かった、(2) 水の透明度が高いが、やや黒っぽい澄み潮状態、(3) 魚の泳ぐ層が浅い、(4) 魚が水面に鼻をあげて泳ぐ表面を魚が泳ぐ、(5) 魚の釣れるタナが浅い、(6) 胴突きの脈釣りで探ってもなにも釣れない、(7) 夜釣りが不振、特に夜になって浅場に出るはずのチヌがいない、(8) イガイが落ち始めた、(9) 表水温が下がったなどが予兆だったのです。 ほかにも、港の突堤の表と裏で生き物の種類や量が異なること、生き物に外来種が増えてきていることなども、調査から分かりました。 |
||
それはすごい。データの数もパワーです。大阪湾再生への一歩ですね。
そう。100年後も1000年後も釣りが楽しめる、多くの魚たちが棲む大阪湾にしていくための一歩として、今後多くのデータを収集していきたいんです。 まだ活動はここ大阪湾で始まったばかりですが、市民参加による環境モニタリングの全国的なシステムを構築すべく頑張りたいと思っています。 NPO法人 釣り文化協会 |
|||