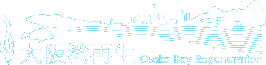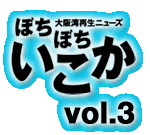自然がいっぱい残る
我らの成ヶ島を
ゴミから救いたい〈3〉
成ヶ島を美しくする会 会長 花野晃一さん
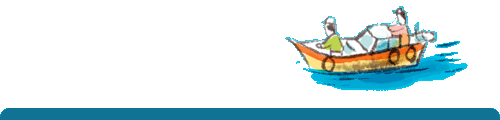 |
||||
淡路島東岸・洲本市由良沖に浮かぶ成ヶ島は、海浜性植物が群生し、ウミガメの産卵も認められるほど、自然が豊富に残る無人島だ。海は青く、島は美しい・・と言いたいところだが、じつは大阪湾に流れるたくさんのゴミが漂着する“ゴミの島”でもある。せっかくの島を、なんとかして美しくしたいと立ち上がり、15年前から手弁当で活動をしている「成ヶ島を美しくする会」の人たち。 |
||||