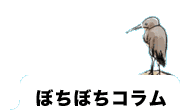 |
||||
|
「ぼちぼちいこか」vol.4 でご紹介した「生きもの育て隊 アオサ取り」活動の実施場所、大阪南港野鳥園は、人工的に干潟と緑地が造成された地である。 干潟とは、海岸部に発達する砂や泥により形成された、潮汐の時間によって陸地になったり海面下になったりする低湿地のことだ。古来、貝類の採取、養殖をはじめとする漁業やレクリエーションの場として利用されてきた。多様な生物が生息し、シギ、チドリなど渡り鳥の中継地ともなるばかりか、潮汐作用や生息する生物によって自然の浄化作用に有効な存在だ。しかし、日本の大都市は、干潟のできる大きな川の河口付近に発達してきたため、遠浅の海岸が埋め立てられ、干潟がほとんどなくなってきた。とりわけその傾向が強いのが大阪湾岸で、そのほとんどが人工護岸となっている。 干潟を再生しようという動きは、1978年に開始された熊本県玉名を皮切りに横浜金沢、広島県五日市・尾道糸崎港、東京(大井野鳥園)など日本各地で始まった。 大阪南港野鳥園は1983年に開園。海水が出入りする導水管を設置し、干潮時に干潟や磯が現れる池が造成されており、池の周囲にはヨシを主とした塩生湿地が広がっている。 また、「大阪湾再生推進会議」による「大阪湾再生行動計画」に則り、人工干潟の整備は、2006年度までに、岸和田市沖・阪南港阪南2区埋立地(阪南市地先、5.4ha)で行われてきたほか、今後、尼崎臨海地区の尼崎の森中央緑地に約0.7ha、堺泉北港堺第2区に約10haが予定されている。さらに、神戸空港には約2haの人工ラグーン、大阪港夢洲には干潟、海浜、磯場の整備計画もある。
この他、大阪湾に注ぐ新淀川でも、淀川大堰から下流約10キロの汽水域(海水と淡水がまじったところ)である海老江干潟、柴島干潟の保全、復元、再生が行われている。 これらの干潟や藻場は、さまざまな生物の生息・育成の場となると同時に、年間を通して底生生物が生息できる水質レベル、人々の親水活動に適した水質レベルの確保についても効果を発揮すると期待されている。 参考資料: |
||||