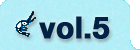 |
「かけがえのないこの浜を次世代に残したい」 |
||
|
砂浜が続く、兵庫県西宮市の御前浜(おまえはま) と香櫨園浜(こうろえんはま) は、大阪湾の湾奥部に残る自然海岸が1%に過ぎない中、貴重な存在だ。 |
|||
泳げる海を今いちど阪神香櫨園駅から夙川べりを南へ徒歩約10分。夙川の河口の東側に広がるのが御前浜(通称)、西側に広がるのが香櫨園浜(同)だ。すぐ前までマンションや戸建ての住宅がぎっしり並び、対岸には西宮浜が見え、浜辺には心地よい潮風が吹く。東側には国指定の史跡「西宮砲台(※1)」も建っている。
この辺りは、1907年(明治40)に海水浴場が開設されたのをはじめ、音楽堂などもある、かつての一大レジャー拠点だった。海水浴場は第2次大戦の間閉鎖したが、戦後いち早く再開され、賑わいを取り戻した。高度経済成長期にはプールや釣り堀ができ、風光明媚な遊び場だったという。
しかし、1980年代に人工島の南芦屋浜(現・潮芦屋)、西宮浜が次々と竣工(西宮浜は部分竣工)したのを機に、浜の景色が一変。利用する人たちのマナーも良いとは言い難く、近年は荒廃の一途をたどっていた。 かつての浜を知る近隣の人たちが「美しい浜に戻したい」と願っても、個人の力では無理と諦めざるを得なかった。そんな折に、「あまかん」から「協働して、海辺環境の再生を図りませんか」との呼びかけがあり、近隣住民たちがこれに応じ、協働が始まったのだった。 「浜を、庭のように育ちましたから、荒廃した近年の浜に心を痛めていたんです。海辺が、日常生活から遠いものになってしまった、と。正直、行政にはあまり期待していなかったのですが、再び泳げる海やきれいな浜を蘇らせたい一心で、参加してみたんです」と、近くに住む加藤一郎さんは言う。 当初の多くの参加者の思いも、加藤さんと同様だった。 |
||||||||||||||
地域住民・行政・専門家がゆるやかに連帯そもそも、御前浜・香櫨園浜プロジェクトは2003年にスタートした。住民参加を呼びかけるのに先立ち、当初2年間で、行政と民間シンクタンクが、浜の歴史の掘り起こしと、ハード面の現況把握、「利用者は何を期待しているか」など現況調査を済ませていた。 「西宮砲台が貴重な歴史資産であることを、改めて知って誇りに思いました。一方で、海と街が防潮堤で分断されてしまっていることや、浜への入口への階段が狭くて急なこと、砂浜が草地化していっていること、看板群が景観を阻害していること、ゴミの不法投棄がなくならない要因などが見えてきました」
それらの課題を整理し、有識者へのヒアリングなどを通じて、「子どもを安心して遊ばせるには?」「砂浜再生の方法は?」「防災機能を持ち浜に親しめる防潮堤は?」「御前浜・香櫨園浜ならではの海辺の使い方は?」と、模索もした。 そして、その後地域住民・利用者たちが、2005年からこのプロジェクトに参加し、行政と住民の対話が始まったのだ。 「御前浜・香櫨園浜プロジェクト」の活動の特徴は、参加者の話を聞き・語ること。初年度は、月にほぼ一度「なぎさゼミナール」や「なぎさカフェ」が開かれ、コミュニケーションの場、活動のベースづくりが開始された。参加者たちは、地元住民の視点から浜へのそれぞれの思いを語った。行政への直言も多々出された。多くの人の思いを聞くことは、自分の思いを整理することにもなる。
浜辺のテントの下で行なう「なぎさカフェ」では、口コミでやって来た人や散策中に覗いた人たちも含めてテーブルを囲み、紙コップでお茶を飲みながら、語り合った。浜の将来像を「海辺のひろっぱ──つながる未来」にしようと意見が一致。浜を「まもり・つかい・つたえる」を合い言葉に、プロジェクトとしての「行動」が具体化し始めた。 活動2年目は、この浜の魅力や問題点を多くの人たちにもっと知ってもらう必要があると「メッセージプロジェクト」として広報活動に取り組むとともに、御前浜らしい効果的なサイン計画づくりと、浜の課題やみんなの思いを行動に移す実践活動が動き出した。
そして今年は「子どもと海辺プロジェクト」として、みんなが一番願っていることを、自分たちができることからやろうと、サイン見守り、出前講座、海岸清掃、勉強会、イベント、情報発信の6グループに分かれ昨年の経験を活かし、地域住民・利用者主体の実践活動がいよいよ開始となった 。 「このプロジェクトが面白いのは、義務感からではなく、それぞれの浜への強い思いから集り、自分のスタイルで活動しているからだと思います」と、参加者は言う。 |
||||||||||||||||||||
思いが実践に発展し、6グループが活動 サイン見守りグループは、浜の看板を見直した。
総合案内板は「人と自然の“いとなみ”が共生するかけがえのないこの浜を未来へ」がキャッチコピーで、設置者の名前は、行政でもグループ名でもなく「御前浜・香櫨園浜を愛する住民・利用者、兵庫県、西宮市」。「私たちがこの浜を見守っています」と書いた。浜に飛来する渡り鳥などの絵も描かれ、「水上バイク」「犬の放し飼い」など禁止事項が夜間にソーラー電池で光る仕組みで、御前浜への西側入口に、今年4月に設置された。各地にある従前の看板とは、発想も見た目も異なるこの看板は、図らずも (社)日本サインデザイン協会主催のSDA賞関西地区デザイン賞を受賞した。
出前講座グループは、地元の小学校から要請され、今年度からスタートした兵庫県教育委員会の「体験型環境学習プログラム」として、出前授業を行っている。
イベントグループは、夙川から運ばれた砂が河口にたまることにより潮の流れが変わり、御前浜が痩せてきていることに着目。潮の流れを元に戻すために、なぎさカフェやイベントの日に、河口にたまった砂を取り、浜に上げるバケツリレー「ニテコ(※2)」を呼びかける。発案者の諏訪禎男さんは、「ニテコは6月のなぎさカフェから始め、すでに2回やりました。まだ“実験”の位置づけですが、飛び入りで参加してくれる人たちもいて、意識付けの上でも確かな手応えを感じています。今後は、きれいな砂浜を生かした子ども向けのイベントも開催したい」と話す。
ほかに、海岸清掃グループは地域の子ども会と合同での清掃活動を、勉強会グループは赤潮、青潮、海の生物、浜の植生などについての自主勉強会をしている。情報発信グループは「ツタエホウダイ」という名の通信を作り、浜での活動や浜に関する情報を、地域住民・利用者の視点で発信している。
神戸芸術工科大学の学生は、出前講座グループと協力して、浜辺に来る子どもや親子連れに向けて、浜ならではの遊びを提案した。「ひろっぱ教室」と題して、凧やかざぐるまを作ったり、遊びを通して浜のゴミ調べる探偵団や、様々な浜辺の遊びワークショップに参加することによってポイントがたまり、ポイントに応じて各家庭で不要になったおもちゃと交換できる「かえっこバザール」を開いたり。若い発想と行動力を持ち込んだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
マイペース&マイスタイルで 参加メンバーは年々増え、目下約50人。リタイア後の男性が最も多いが、女性もいる。大学生もいる。なぎさカフェでは、年配者が語る「昔の浜辺の思い出」に大学生や若いカップルが耳を傾けたり、年配者が大学生や子どもたちと一緒に浜の遊びに興じたり・・・。地域外から、時々顔を出す人も現れるようになった。
「イベントで浜に来た人が、この浜の良さを分かってくれ、『大切にしたい』との思いを私たちと共有してくれたらうれしい。活動を重ねることで、浜を少しでもきれいにして、次世代に引き継ぐのが私たちの責任だと強く思うようになってきました。私たちにできることは何か。手探りは続きますが、私たちのスタイルとペースで楽しみながら活動を続けていきたいですね」
「海辺の砂浜を最もよく利用するのは近隣の人たちですが、その人たちの所有物ではなく、訪れるすべての人に開かれた空間です。そのため、近隣の人たちを核に、来訪者のだれもが利用者であると共に主体になれるのが、このプロジェクトの特徴でしょう。行政の呼びかけからスタートしましたが、参加する側の活動の自由度が高く、まさに『協働』。今後は、行政が参加者の思いをより一層くみ取った上で、ハード面の整備とメンテナンスに関する継続的な責任部署としての役割を果たし、市民も管理の一翼を担うような形が取れればいい」 取材・高田次郎 文・井上理津子
写真・豊崎寛樹/丸井隆人 |
||||||||||||||