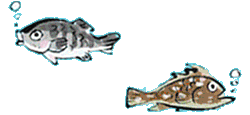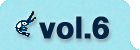 |
子どもたちに「水辺環境」の学習を |
||
|
子どもたちに、「水辺環境」への関心を深めてほしい──と、熱心に指導している小学校の先生がいる。大阪府阪南市立西鳥取小学校教諭の前田ゆきみさんだ。 大阪府南部の阪南市は、山、海、川に囲まれた豊かな自然環境の中にある。前田さんは、前任の同市立箱作小学校時代から、そんな土地の特性を生かし、地域の人たちとの交流も図りながら、総合学習(※1)やクラブ活動にユニークな環境学習を展開。2003年〜2006年度の大阪府学生科学賞なども受賞している。西鳥取小学校に伺い、これらの活動の内容と思いについて、前田さんに聞いた。 それぞれの画像はクリックするとポップアップで拡大サイズの画像をご覧いただけます。 |
|||
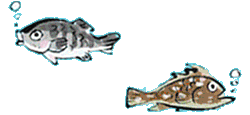
生き物観察から「西鳥取水族館」へ──西鳥取小学校の下足室に、たくさんの魚やカニ、貝が入った2つの大きな水槽が置かれています。マコガレイ、キジハタ、チヌ、トゲアメフラシ、アサヒアナハゼ、ヤドカリ・・・。びっくりしました。「西鳥取水族館」と名付け、我が校のちょっと自慢です(笑)。4年生〜6年生のクラブ活動「わくわくエコクラブ」の子どもたちが、学校近くの西鳥取の海辺に行き、生き物観察をした時に、大きなヤドカリを見つけて、学校の水槽で飼おうということになったのが始まりなんです。 ──生き物観察というのは? 毎月1回、45分間、袋を持って海辺に行っています。最初のうちは「服が汚れる」と言っていた子たちも、次第に夢中になって、貝を拾ったり、カニを取ったり。岩場でアメフラシを採って来る子もいます。アメフラシは、つつくと紫色の液体を出す軟体動物で、以前はたくさんいたのですが、目に見えて減っている。環境ホルモンに影響を受けやすいんですね。そんな話も交えながら観察しているんです。 ──下足室に水族館があると、子どもたちが日常的に目にしますね。そうなんです。「カニさんかわいいね」と見入ったり、「これ何?」「これ何?」としょっちゅう聞いてくる低学年の子もいれば、「ヤドカリは貝殻の中に頭と胸だけ出して歩き回るんやね」「カレイは両目のある側を上にしているんやね」と観察したことを目を輝かせて報告してくる高学年の子もいて、みんなそれぞれに興味を持ってくれるんですね。水を取り替えたりの世話も、わくわくエコクラブの子たちが中心になってやっています。 ──いろんな発見があるのでしょうね。ええ。魚の種類が増えてくると、あれっと思うことが起こりました。チヌが、他の魚やカニ類を食べ始めたんです。水槽をチヌと他の魚類に分けることにして、これで一件落着と思っていたんですが、水槽が2つになると、毎日水を取り替えるのが大変です。それで、わくわくエコクラブで、水槽の中の水をきれいにする方法をインターネットや本で調べました。 |
||
水槽の水の浄化実験に取り組む──水槽の中の水をきれいにする方法というのは? 最初に試みたのは、アサリに水を浄化させる方法です。 ──それで、どうされたんですか? さらに調べると、アサリよりカキのほうが水の浄化作用が大きい、と。 ──まさに、実験と調べが合わさった、素晴らしい学習ですね。もっと言うと、アサリやカキなど二枚貝は海水を大量に体内に取り込み、それをエラで濾過しているとも分かりました。水中で採った粒子を口に入れる直前に食べるものと食べないものに選り分け、食べないものを外に捨てて、他の生き物のエサになっている。つまり、二枚貝は砂浜の表面の有機物を食べて海をきれいにしているばかりか、砂の中にたまった有機物を分解していると分かりました。 ──「西鳥取水族館」の観察などから、子どもたちの海を見る目も変わったのでは?ええ。2月3日にわくわくエコクラブの子どもたちが泉南地域の「私の水辺」大発表会(於:泉南府民センタービル多目的ホール、主催:「私の水辺」大発表会実行委員会)で、「西鳥取水族館物語」と題する発表をしましたが、その時も、子どもたちは「私たちはアサリやカキの水質浄化作用を知って、海を見る目が変わりました。海はさまざまな生き物の共同作業できれいに保たれていることを知りました。これからも西鳥取の海を大切にしていきたいと思います」と締めくくりましたよ。 |
||
子どもたちに地域を愛してほしい──地域の人たちとも連携されているとか。 はい。連綿と受け継いできた知恵を持つ地域のお年寄りや保護者の協力は不可欠です。 また、市内に、環境教育の拠点作りと市民が触れ合える場を目指した整備が進められている府営「せんなん里海公園(※2)」があるのですが、そこで活動している「うみべの森を育てる会」をはじめ、「田山川の自然を守る会」「海藻おしばクラブ」など地域の自然環境関係のグループが主催するイベントに学校ぐるみで参加したり、大阪湾沿岸の生態調査を進めている大阪府立大学大学院上甫木研究室の人たちのサポートも受けています。 ──先生が主導してくださらないと、この頃の子どもたちは、昔のように屋外であまり遊びませんね。 それには学校側の生活指導も関係していると思います。私は「海や川や池に近づかないように」と言わざるを得ないことにジレンマを感じていました。子どもたちだけで行くと、足を踏み外して溺れたり、ケガをしたりする可能性がないとはいえない。万が一のことが起きた場合、責任を取れない。そういうリスクを回避できないからなんですが。 ──前田先生は、もともと前任の箱作小学校時代から、環境教育に取り組まれています 。 地域の実態に合わせた、教科の枠を超えた新しい学習を──と「総合学習」の立ち上げに参加したのがきっかけでした。クラブ活動「理科クラブ」を担当し、自然との出会いの体験活動から不思議に気づいたり、新たな発見をしたりして、自分なりの問題としてとらえる。観察や実験、情報の整理などを通して、子どもたちに問題意識を持たせ、ひいては自然環境の保全について考えるようになることを目的に、1970年代に大阪湾から姿を消したハマビシを人工海浜と自然海浜、校庭で発芽実験したり、せんなん里海公園に生息する陸ガニの生息環境調査を、川をさかのぼってしたり。 ──前田先生ご自身も、環境学習が楽しそうですね。環境学習に受けた取り組んだ子どもたちの将来が楽しみです。そう。私自身も、環境と地域と人的ネットワークを融合したこの環境学習が楽しくて・・。個人的にホームページも作っているんですよ。子どもたちは、「自分たちの今の生活があるのは埋め立てのおかげだが、人間は埋め立てのために住かをうばわれた動植物と共存し、共生していかなければならない」と学んでくれるようです。こういった学習の積み重ねは、子どもたちにある程度の科学的な目を持つことを促し、地域の環境を愛し、ひいては地域を愛する人に育ってくれるのではないか、と。これからも頑張ります。 取材・文:井上理津子 写真:丸井隆人
(* 印付画像は前田先生からのご提供です) |
||