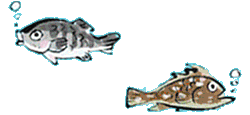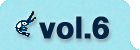 |
子どもたちに「水辺環境」の学習を*2 |
||
|
子どもたちに、「水辺環境」への関心を深めてほしい──と、熱心に指導している小学校の先生がいる。大阪府阪南市立西鳥取小学校教諭の前田ゆきみさんだ。 大阪府南部の阪南市は、山、海、川に囲まれた豊かな自然環境の中にある。前田さんは、前任の同市立箱作小学校時代から、そんな土地の特性を生かし、地域の人たちとの交流も図りながら、総合学習(※1)やクラブ活動にユニークな環境学習を展開。2003年〜2006年度の大阪府学生科学賞なども受賞している。西鳥取小学校に伺い、これらの活動の内容と思いについて、前田さんに聞いた。 それぞれの画像はクリックするとポップアップで拡大サイズの画像をご覧いただけます。 |
|||
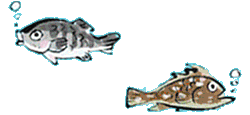
水槽の水の浄化実験に取り組む──水槽の中の水をきれいにする方法というのは? 最初に試みたのは、アサリに水を浄化させる方法です。 ──それで、どうされたんですか? さらに調べると、アサリよりカキのほうが水の浄化作用が大きい、と。 ──まさに、実験と調べが合わさった、素晴らしい学習ですね。もっと言うと、アサリやカキなど二枚貝は海水を大量に体内に取り込み、それをエラで濾過しているとも分かりました。水中で採った粒子を口に入れる直前に食べるものと食べないものに選り分け、食べないものを外に捨てて、他の生き物のエサになっている。つまり、二枚貝は砂浜の表面の有機物を食べて海をきれいにしているばかりか、砂の中にたまった有機物を分解していると分かりました。 ──「西鳥取水族館」の観察などから、子どもたちの海を見る目も変わったのでは?ええ。2月3日にわくわくエコクラブの子どもたちが泉南地域の「私の水辺」大発表会(於:泉南府民センタービル多目的ホール、主催:「私の水辺」大発表会実行委員会)で、「西鳥取水族館物語」と題する発表をしましたが、その時も、子どもたちは「私たちはアサリやカキの水質浄化作用を知って、海を見る目が変わりました。海はさまざまな生き物の共同作業できれいに保たれていることを知りました。これからも西鳥取の海を大切にしていきたいと思います」と締めくくりましたよ。 |
||