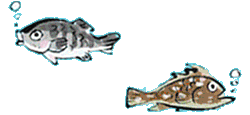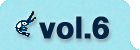 |
子どもたちに「水辺環境」の学習を*3 |
||
|
子どもたちに、「水辺環境」への関心を深めてほしい──と、熱心に指導している小学校の先生がいる。大阪府阪南市立西鳥取小学校教諭の前田ゆきみさんだ。 大阪府南部の阪南市は、山、海、川に囲まれた豊かな自然環境の中にある。前田さんは、前任の同市立箱作小学校時代から、そんな土地の特性を生かし、地域の人たちとの交流も図りながら、総合学習(※1)やクラブ活動にユニークな環境学習を展開。2003年〜2006年度の大阪府学生科学賞なども受賞している。西鳥取小学校に伺い、これらの活動の内容と思いについて、前田さんに聞いた。 それぞれの画像はクリックするとポップアップで拡大サイズの画像をご覧いただけます。 |
|||
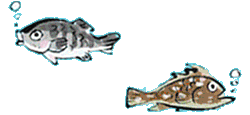
子どもたちに地域を愛してほしい──地域の人たちとも連携されているとか。 はい。連綿と受け継いできた知恵を持つ地域のお年寄りや保護者の協力は不可欠です。 また、市内に、環境教育の拠点作りと市民が触れ合える場を目指した整備が進められている府営「せんなん里海公園(※2)」があるのですが、そこで活動している「うみべの森を育てる会」をはじめ、「田山川の自然を守る会」「海藻おしばクラブ」など地域の自然環境関係のグループが主催するイベントに学校ぐるみで参加したり、大阪湾沿岸の生態調査を進めている大阪府立大学大学院上甫木研究室の人たちのサポートも受けています。 ──先生が主導してくださらないと、この頃の子どもたちは、昔のように屋外であまり遊びませんね。 それには学校側の生活指導も関係していると思います。私は「海や川や池に近づかないように」と言わざるを得ないことにジレンマを感じていました。子どもたちだけで行くと、足を踏み外して溺れたり、ケガをしたりする可能性がないとはいえない。万が一のことが起きた場合、責任を取れない。そういうリスクを回避できないからなんですが。 ──前田先生は、もともと前任の箱作小学校時代から、環境教育に取り組まれています 。 地域の実態に合わせた、教科の枠を超えた新しい学習を──と「総合学習」の立ち上げに参加したのがきっかけでした。クラブ活動「理科クラブ」を担当し、自然との出会いの体験活動から不思議に気づいたり、新たな発見をしたりして、自分なりの問題としてとらえる。観察や実験、情報の整理などを通して、子どもたちに問題意識を持たせ、ひいては自然環境の保全について考えるようになることを目的に、1970年代に大阪湾から姿を消したハマビシを人工海浜と自然海浜、校庭で発芽実験したり、せんなん里海公園に生息する陸ガニの生息環境調査を、川をさかのぼってしたり。 ──前田先生ご自身も、環境学習が楽しそうですね。環境学習に受けた取り組んだ子どもたちの将来が楽しみです。そう。私自身も、環境と地域と人的ネットワークを融合したこの環境学習が楽しくて・・。個人的にホームページも作っているんですよ。子どもたちは、「自分たちの今の生活があるのは埋め立てのおかげだが、人間は埋め立てのために住かをうばわれた動植物と共存し、共生していかなければならない」と学んでくれるようです。こういった学習の積み重ねは、子どもたちにある程度の科学的な目を持つことを促し、地域の環境を愛し、ひいては地域を愛する人に育ってくれるのではないか、と。これからも頑張ります。 取材・文:井上理津子 写真:丸井隆人
(* 印付画像は前田先生からのご提供です) |
||