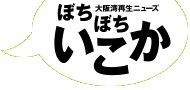ほっとかへんで!と活動4年目「大阪湾見守りネット」 |
 |
||
|
大阪湾を元気にするために、みんなで見守り、行動していこう──と、約90の団体や個人がつながるネットワークがある。その名も「大阪湾見守りネット」(事務局=地域計画建築研究所=アルパック。大阪市)。メンバーには、釣り人もいれば、ダイバーも、ゴミ拾いや生き物調査など自然保護活動をしている団体もいる。大阪湾を囲んで活動拠点もさまざまだ。共通するのは、「大阪湾を囲み、人々も大阪湾も元気にしたい」の熱い思いという。3月8日(土) に西宮市で開かれた「第4回ほっといたらあかんやん!大阪湾フォーラム」(主催:大阪湾見守りネット、国土交通省近畿地方整備局神戸港湾空港技術調査事務所) のレポートとともに、このネットワークを紹介しよう。 |
|||
「大阪湾再生」 をミッションにネットワーク今回の「大阪湾フォーラム」は4回目だが、大阪湾見守りネットは、2005年2月に大阪市立自然史博物館(大阪市) で、大阪湾の沿岸域で活動する市民団体、民間企業などの紹介が行われた第1回の同フォーラム(フォーラム実行委員会と国土交通省近畿地方整備局の共催) をきっかけに設立された。一堂に会した140人余りの人たちが、「大阪湾再生」をミッションに、緩やかなネットワークをもつことにしたのである。 「それぞれの団体が、自分のやりたいことをテーマに、いろいろなベクトルで活動している中、ネットワークすることにより協力しあい、前につなげていけたら。そんな思いでした」 目指すのは、「魅力と活力のある、美しい大阪湾の再生」や「大阪湾を囲み、人々も大阪湾も元気になれるネットワーク」。設立以来、年1回ペースでフォーラムを開き、大阪湾再生に向けた取り組みをネットワークの内外にアピールするとともに、メーリングリストなどで大阪湾に関する調査や新たな取り組みの情報などを共有している。 第2回大阪湾フォーラム(2006年2月) は、神戸市立須磨海浜水族園で「大阪湾まるごと水族館」として、水族園のバックヤードツアー、大阪湾の生き物についての情報交換など、第3回(2007年3月) は「チリモン!海もん!宝もん!」として、阪南2区の造成干潟見学、干潟再生のための調査結果報告などが、それぞれ大阪湾見守りネットのメンバーである地元の団体とのジョイントで行われた。その他、毎年の総会、2007年11月には帆船「あこがれ」による大阪湾上研修会も開かれ、皆で大阪湾の水質・流況などの実測体験をした。 「まず、知り合いが広がることに大きな意味があります。個々に活動していた団体が、顔を合わせることによって、刺激し合う。大阪湾の環境の多様性、生物的自然のポテンシャルが高いことも認識でき、個々の活動の励みにもなります」と、山西良平さん。 今回のフォーラムに、「TEAM 魚(うお)っしょい」メンバーの三輪栄子さんは、二色浜などで採取した貝を使った自作の万華鏡を持って参加。「TEAM
魚っしょい」は海遊館(大阪市港区) のボランティアをきっかけに組織し、子どもたちに遊びの中で環境問題を考えるワークショプを開くグループだ。 今回のフォーラムで、参加者に「ご協力を」との呼びかけられた「大阪湾生き物一斉調査」は、大阪湾環境再生連絡会の取り組み。2007年11月の矢倉海岸(大阪市西淀川区) での試行調査を経て、2008年6月21日に大阪湾広域で実施されるにあたり、大阪湾見守りネットが協力する予定である。前述のとおり「大阪湾再生」をミッションとする同ネットは、行政と共働する姿勢だ。 「行政に注文をつけるだけでは、前に進まない。どこにゴミが氾濫しているとか、どこの生物の生息環境が変わってきたとか、そういったそれぞれのフィールドで活動しているから得る情報を行政に伝え、じゃあどうすればよいかと提言する。見守りネットはそういった力を徐々につけてきています。撒いた種は必ず収穫できる。今後とも、我々に何が出来るかを模索し、『多くの人が海に近づけ、いろいろな思い出作りができる大阪湾』ずくりを目指していくつもりです」(田中さん) 熱い思いと、ゆるやかなネットワーク。楽しみながらの活動。大阪湾見守りネットのさらなる取り組みに、内外から期待が寄せられている。 取材・文:井上理津子 写真:丸井隆人
|
||