
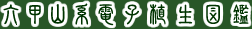
アカマツ−モチツツジ群集 |
分類 : 二次林 |
相観 : 常緑針葉高木林 |
植物社会学上の位置づけ : アカマツ群団、コナラ−ミズナラオーダー、ブナクラス
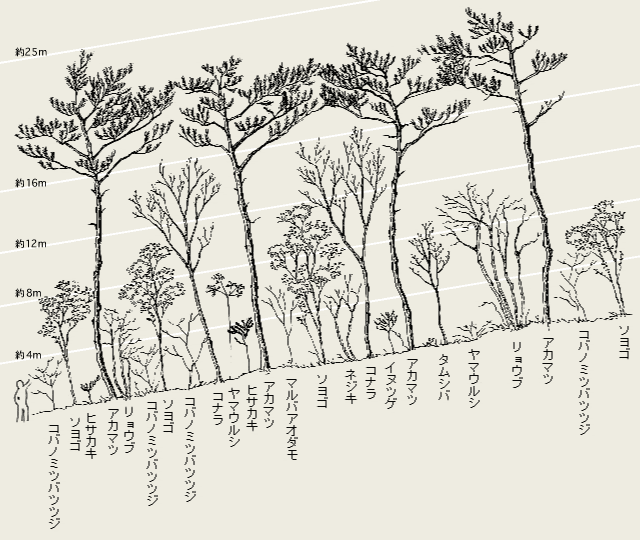
高さ12〜25mの常緑針葉樹林です。アカマツが林冠に出て、階層は4,5層に分化します。
海抜450mあたりを境に、大きくふたつのタイプに分かれます。
高海抜域のタイプは、タンナサワフタギ下位単位と名付けられたタイプで、ブナ域やカシ域に分布の偏る種が多く見られます。タンナサワフタギ,アセビ,コアジサイ,ウンゼンツツジなどが現れることが特徴です。また、照葉樹のソヨゴ,ヒサカキ,アセビなどが高い被度で現れます。このタイプの中には、ミヤコザサが密生して、見た目も種数も異なる林もあります(ミヤコザサ優占群)。
低海抜域のタイプは、シャシャンボ下位単位と名付けたタイプで、照葉樹林の構成種群など、シイ域に分布の偏る種が多く見られるます。また、高海抜域のタイプを特徴づける種がほとんど出現せず、シャシャンボやガンピが出現するのが特徴です。
本群落と同じく、アカマツの優占するアカマツ−ハナゴケ群集とは、常緑針葉樹のネズや、草原生の多年草のトダシバ,ヒメハギ,メリケンカルカヤ,トダシバなどを欠くことで区別します。コナラーアベマキ群集とは、アカマツの有無で区別できます。
|
夏緑樹 | アカマツ、コナラ、リョウブ |
|---|---|---|
| 照葉樹 | ||
| ツル植物 | ツタ | |
|
夏緑樹 | リョウブ、コナラ、タカノツメ、タムシバ、ヤマザクラ |
| 照葉樹 | ソヨゴ、ウラジロガシ、ヤブツバキ | |
| ツル植物 | ||
|
夏緑樹 | コバノミツバツツジ、ネジキ、カマツカ、ミヤマガマズミ、クロモジ、コアジサイ、モチツツジ |
| 照葉樹 | ヒサカキ、アセビ、ソヨゴ、イヌツゲ、ヒイラギ、ネズミモチ | |
| ツル植物 | ||
| ササ | ミヤコザサ | |
|
1・2年生草本 | |
| 多年草 | チヂミザサ、シハイスミレ、ミヤマウズラ、ツルリンドウ、チゴユリ、オオバノトンボソウ、ツルアリドオシ | |
| ツル植物 | サルトリイバラ、ミツバアケビ |
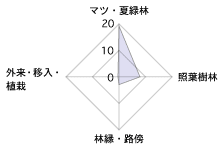 ミヤコザサの優占するタイプを除くと、マツ林・夏緑林の構成種群はブナ−シラキ群集とほぼ同じくらいの種が生育しています。一方で、照葉樹林の構成種群も多く、結果として、群落の平均出現種数が高い値となっています。
ミヤコザサの優占するタイプを除くと、マツ林・夏緑林の構成種群はブナ−シラキ群集とほぼ同じくらいの種が生育しています。一方で、照葉樹林の構成種群も多く、結果として、群落の平均出現種数が高い値となっています。
特に、低海抜域のタイプ(シャシャンボ下位単位)に注目してコナラ−アベマキ群集と比較すると、アカマツ−モチツツジ群集では、マツ林・夏緑林の構成種群がまだ欠落していないことが伺えます。このことは、低海抜域における林の整備では、尾根筋のアカマツ−モチツツジ群集を中心に行った方がいいということを示唆しています。
| 自然林 | 二次林 | 人工林 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブ ナ I シ ラ キ 群 集 |
ウ ラ ジ ロ ガ シ I サ カ キ 群 集 |
コ ジ イ I カ ナ メ モ チ 群 集 |
ア カ マ ツ I モ チ ツ ツ ジ 群 集 |
コ ナ ラ I ア ベ マ キ 群 集 |
エ ノ キ I ム ク ノ キ 群 集 |
ア ラ カ シ 群 落 |
ウ バ メ ガ シ 群 落 |
ニ セ ア カ シ ア 群 落 |
オ オ バ ヤ シ ャ ブ シ 群 落 |
ス ギ I ヒ ノ キ 群 落 |
メ タ セ コ イ ヤ 群 落 |
ク ス ノ キ 群 落 |
マ テ バ シ イ 群 落 |
モ ウ ソ ウ チ ク 群 落 |
|
平均出現数 |
25 | 20 | 22 | 30 | 33 | 30 | 18 | 14 | 32 | 41 | 22 | 59 | 10 | 6 | 22 |
照葉樹の構成種群 |
4.8 | 16.5 | 16.7 | 7.8 | 10.6 | 12.7 | 12.6 | 8.9 | 7.6 | 9.4 | 7.3 | 16.0 | 5.3 | 2.7 | 5.8 |
マツ林・夏緑林の構成種群 |
19.0 | 2.3 | 2.8 | 19.2 | 17.5 | 11.5 | 3.9 | 3.8 | 10.0 | 18.1 | 9.9 | 24.5 | 2.3 | 1.0 | 7.0 |
林緑・路傍群落の構成種群 |
0.8 | 0.5 | 1.7 | 3.1 | 5.0 | 5.4 | 1.3 | 1.6 | 11.2 | 11.2 | 4.1 | 14.5 | 1.0 | 0.7 | 6.3 |
外来・移入・植栽種 |
0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 3.2 | 2.4 | 1.1 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 2.5 |
| ア カ マ ツ I モ チ ツ ツ ジ 群 集 |
内訳 | コ ナ ラ I ア ベ マ キ 群 集 |
内訳 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タ ン ナ サ ワ フ タ ギ タ イ プ |
ミ |
シ ャ シ ャ ン ボ タ イ プ |
タ ン ナ サ ワ フ タ ギ タ イ プ |
ミ ヤ コ ザ サ タ イ プ |
ホ タ ル ブ ク ロ タ イ プ |
シ ャ シ ャ ン ボ タ イ プ |
|||||||||
平均出現数 |
30 | 35 | 22 | 37 | 33 | 38 | 17 | 5.3 | 32 | ||||||
照葉樹の構成種群 |
7.8 | 9.7 | 4.1 | 11.2 | 10.6 | 9.6 | 1.5 | 9.4 | 12.4 | ||||||
マツ林・夏緑林の構成種群 |
19.2 | 21.4 | 16.1 | 19.5 | 17.5 | 25.0 | 14.0 | 33.0 | 13.9 | ||||||
林緑・路傍群落の構成種群 |
3.1 | 3.6 | 1.7 | 5.2 | 5.0 | 3.6 | 1.3 | 10.2 | 4.7 | ||||||
外来・移入・植栽種 |
0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | ||||||