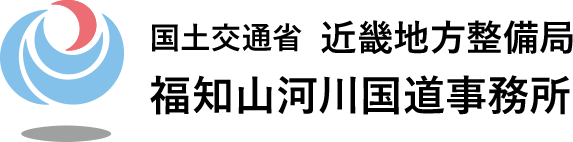河川の取り組み
River Project
第1回由良川水系流域委員会資料
6.由良川改修事業の現況
治水施設の整備:1947~1956(昭和22~31年)
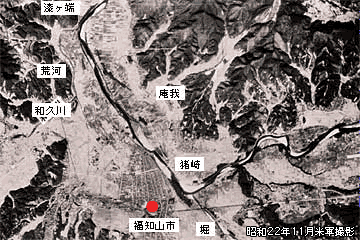
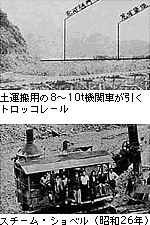 直轄改修の手始めは、かつて和久川が由良川へ合流していた地点の福知山市漆ケ端に荒河水門を築造し、あわせて荒河水門地点から上流に向けて、福知山市街地西部の堤防・護岸工事の実施です。昭和26年には、右岸の福知山市庵我地区においても築堤工事がはじまり、昭和30年度には猪崎地区の溢流堤の施工が行われ、由良川左右岸の築堤が本格的になってきました。
直轄改修の手始めは、かつて和久川が由良川へ合流していた地点の福知山市漆ケ端に荒河水門を築造し、あわせて荒河水門地点から上流に向けて、福知山市街地西部の堤防・護岸工事の実施です。昭和26年には、右岸の福知山市庵我地区においても築堤工事がはじまり、昭和30年度には猪崎地区の溢流堤の施工が行われ、由良川左右岸の築堤が本格的になってきました。●昭和22~29年度
由良川左岸荒河築堤・護岸工事
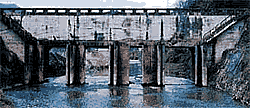 昭和28年度に完成した荒河水門
昭和28年度に完成した荒河水門
現在の荒河排水機場付近にあった
由良川左岸荒河築堤・護岸工事
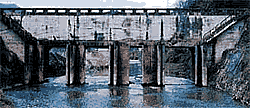 昭和28年度に完成した荒河水門
昭和28年度に完成した荒河水門現在の荒河排水機場付近にあった
●昭和26年度~37年度
由良川右岸 庵我および猪崎築堤・護岸工事
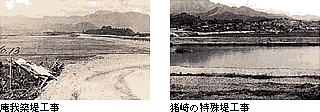
由良川右岸 庵我および猪崎築堤・護岸工事
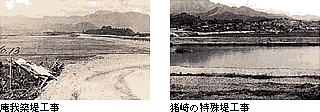
●猪崎溢流堤防工事
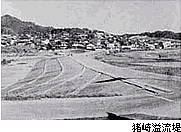 猪崎溢流堤 昭和27年度に音無瀬橋へのアプローチを兼ねた横堤が施工されましたが、昭和28年9月の台風13号によって土堤が壊れたため、コンクリート張構造の溢流堤に改築する計画が立てられました。これが猪崎の溢流堤と称された施設です。溢流堤は天端高を計画高水位高(3,100m3/sec)とし、天端を府道兼用とするため幅員7.0m確保し、法面も含めて全体をコンクリート張構造としました。また、下流側には水叩工を施工し、洗掘防止対策を施しました。工事は、昭和29~30年度に実施しました。
猪崎溢流堤 昭和27年度に音無瀬橋へのアプローチを兼ねた横堤が施工されましたが、昭和28年9月の台風13号によって土堤が壊れたため、コンクリート張構造の溢流堤に改築する計画が立てられました。これが猪崎の溢流堤と称された施設です。溢流堤は天端高を計画高水位高(3,100m3/sec)とし、天端を府道兼用とするため幅員7.0m確保し、法面も含めて全体をコンクリート張構造としました。また、下流側には水叩工を施工し、洗掘防止対策を施しました。工事は、昭和29~30年度に実施しました。
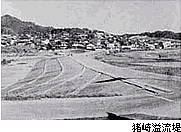 猪崎溢流堤 昭和27年度に音無瀬橋へのアプローチを兼ねた横堤が施工されましたが、昭和28年9月の台風13号によって土堤が壊れたため、コンクリート張構造の溢流堤に改築する計画が立てられました。これが猪崎の溢流堤と称された施設です。溢流堤は天端高を計画高水位高(3,100m3/sec)とし、天端を府道兼用とするため幅員7.0m確保し、法面も含めて全体をコンクリート張構造としました。また、下流側には水叩工を施工し、洗掘防止対策を施しました。工事は、昭和29~30年度に実施しました。
猪崎溢流堤 昭和27年度に音無瀬橋へのアプローチを兼ねた横堤が施工されましたが、昭和28年9月の台風13号によって土堤が壊れたため、コンクリート張構造の溢流堤に改築する計画が立てられました。これが猪崎の溢流堤と称された施設です。溢流堤は天端高を計画高水位高(3,100m3/sec)とし、天端を府道兼用とするため幅員7.0m確保し、法面も含めて全体をコンクリート張構造としました。また、下流側には水叩工を施工し、洗掘防止対策を施しました。工事は、昭和29~30年度に実施しました。| 大野ダム |
|---|
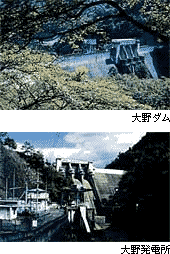 大野ダムは、昭和18年(1943)に由良川河水統制事業で、舞鶴港周辺の電力事情に応じるため計画され、同年6月4日に北桑田郡大野村樫原地内の建設予定地において起工式が執り行われましたが、第二次世界大戦の戦局が拡大し、経済的に厳しさが増し中断されました。 大野ダムは、昭和18年(1943)に由良川河水統制事業で、舞鶴港周辺の電力事情に応じるため計画され、同年6月4日に北桑田郡大野村樫原地内の建設予定地において起工式が執り行われましたが、第二次世界大戦の戦局が拡大し、経済的に厳しさが増し中断されました。その後、昭和26年度より福知山工事事務所に大野出張所を設置し、ダム建設のための予備調査に着手しました。そして、昭和28年(1953)9月建設に着手し、36年(1961)11月に竣工。翌37年(1962)4月より京都府に移管して管理運営に入ったダムで、特定多目的ダム法によって洪水調節、発電を行っています。また、福知山地点の計画高水流量6,500m3/sを、5,600m3/sに低減するよう900m3/sの洪水調節を行います。 大野ダムは、昭和32年(1957)に完成した猿谷ダムに次いで、近畿地方建設局が施工を行った2番目のダムです。ダム堤体内には高水圧大口径放流管を内臓するなど、近年における多目的ダムの原形ともいえる機能が組み込まれています。現在も、設計・施工過程において克服された研究成果は、その後のダム建設に大いに引用されています。 ダムによって誕生した人造湖「虹の湖」は、四季折々に美しい姿を見せてくれます。 |