成ヶ島でゴミ12トン
〜由良中学生ら
「成ヶ島クリーン作戦」〈4〉
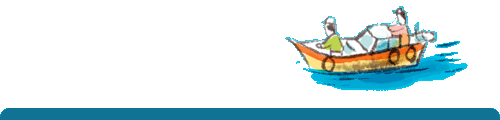 |
||||
花野さんのインタビューにも紹介したとおり、淡路島・洲本市沖に位置する成ヶ島では、1998年から毎年「成ヶ島クリーン作戦〜みんなの力で由良の自然を守ろう」という活動が行われている。「成ヶ島を美しくする会」のメンバーや市民と共にこの活動に取り組んでいるのが、成ヶ島のお膝元・洲本市立由良中学校の生徒たち。今年も1月20日に行われたばかりだ。 |
||||
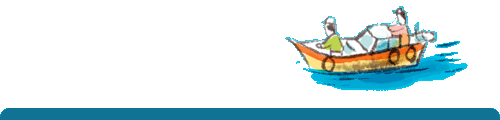 |
||||
花野さんのインタビューにも紹介したとおり、淡路島・洲本市沖に位置する成ヶ島では、1998年から毎年「成ヶ島クリーン作戦〜みんなの力で由良の自然を守ろう」という活動が行われている。「成ヶ島を美しくする会」のメンバーや市民と共にこの活動に取り組んでいるのが、成ヶ島のお膝元・洲本市立由良中学校の生徒たち。今年も1月20日に行われたばかりだ。 |
||||
外来植物の駆除から |
|||
「最初に、展望台の周辺でナルトサワギクを引き抜きました」と、森下暢己くん。ナルトサワギクとは、約30年前から国内に 広まり、近年島にも破竹の勢いで繁殖するマダガスカル原産の多年草。小菊のような形状で、黄色い花を咲かせる。一見すると美しいが、これが曲者で、既存の植物を駆逐する。 「自然の宝庫」といわれる成ヶ島には、兵庫県内唯一となったハマボウが群生しているほか、ハマウツボ、コナミキ、フサスゲなど絶滅の危機があると兵庫県レッドデータブックに登録された植物14種類の分布が確認されているが、ナルトサワギクが繁殖することによって、これら島の自然の植生への影響が心配される。引き抜いて防御するのがベストな方法なのである。 「意外とすんなり抜けました。でも、たくさん生えていたので困った」 |
|||
注射器から「変な物体」までさまざまなゴミ |
|||
|
続いて、浜に移動し、海岸に打ち上げられたペットボトルやプラスチック製品、ビニール袋などのごみを拾い集めた。
「ゴルフボールが多く、ジッポのライターもあった。ほかに、オレンジ色で重たい長方形の変な物体も、大きなタイヤも漂着していたので拾った」(山本裕貴くん) 2年生にとっては、去年に引き続き2度目のクリーン作戦参加。森下くんは、去年はテレビ、ドラム缶、1斗缶を拾ったという。 |
|||
これらのゴミは、どこから流れて来ているのか。ハングル語のペットボトルは韓国からと考えられなくはないが、外国船から投棄されたものかもしれない。明らかに「大阪府内」で捨てられたと見られる駐車違反標章、兵庫県の内陸部から川を伝って流れてきたと見られるゴルフボールも少なくなかった。生徒らは、一つひとつ確かめながら拾っていったという。 生徒一人1時間余りずつの清掃は、午前中に終わった。結果、回収したゴミは、2トンパッカー車2台と2トンダンプカー4台分となり、ゴミ焼却場へと運ばれた。 |
|||
「なんで自分たちが?」から「いつか自然の山に」へ |
|||
地元由良に生まれ育った生徒たちだが、前世代の人のように、子どもの頃に成ヶ島で頻繁に遊んだ経験はない。 5人のうち、藤本くんだけが「父と一緒に、泳いで成ヶ島に渡ったことが一度だけある」と言うが、あとの4人は「潮干狩りに行ったことがあった」程度で、「大潮の後、あさりがたくさん獲れた」という関連した記憶を思い出してくれたのも山本くんだけ。生徒たちが育った時代の成ヶ島の浜は「遊泳禁止」で、すでに荒廃した後だったわけだ。そのため、大人たちのような愛着は希薄だ。だが、毎日当たり前に視界に入り、なくてはならない風景の要素だったことは確か。 |
|||
「1年の時、初めてのクリーン作戦をする前は、なんで自分たちがこんなにしんどいことをわざわざしないといけないのかと思った」 「ゴミ拾いはしんどいが、意義があると思えた。町や自然のためになる行事だし、自分たちのためでもある行事だ。頑張れば、いつかゴミの山が自然の山に変わっていくかもしれない。由良にその日が来ることを願って、一つひとつゴミを拾ったし、また拾いたいと思う」 |
|||
環境問題は自分の問題 |
|||
「成ヶ島に漂着するゴミの中には『明石』や『大阪』と書かれた発泡スチロールなどがあった。近くで捨てられたものではなく、遠い所で捨てられたゴミが成ヶ島に漂着する。地元に住む私たちからすれば、腹立たしいことだが、すべてのゴミが遠い所で捨てられたゴミではなく、地元で捨てられたと思われる漁業に使用する網やバケツ、発泡スチロールもある」 |
|||
「地元の人が、遠くでゴミを捨てている人たちに『ポイ捨てをしないで』と訴えたとしても、私たち地元の人が捨てたゴミがあっては説得力がない。私たち地元の人から、ポイ捨てを止めないと自然環境はどんどん悪化すると思う」 |
|||
|
由良中学校校長の岡洋司さんは、 [写真提供:由良中学校(ナルトサワギクの写真を除く)] 洲本市立由良中学校2年 |
||