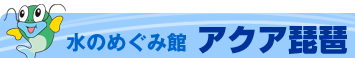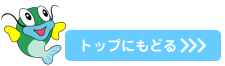琵琶湖・淀川ふれあい紀行
大いなる琵琶湖の幸、湖魚料理をもとめて。
悠久の歴史を誇り、世界に10余りしかない古代湖のひとつとして知られる琵琶湖。
その時の流れの中で独自の進化を続けてきた琵琶湖の魚たちは、滋賀の人々にとっては貴重なタンパク源でした。人は豊かな自然に感謝しつつ、湖魚をいかに無駄なく、おいしく食べるかということに知恵をしぼり、さらに、限られた水産資源を大切に守り続けることに大きな努力をはらってきました。
琵琶湖の魚はなぜ美味しいのか。
湖魚を食材にした郷土料理について、『ビワズ通信36号』にもご登場いただいた滋賀大学教育学部の堀越昌子教授にお話をうかがいました。
「まず、琵琶湖に棲む魚は固有種を筆頭にとても美味です。淡水魚はクセのある匂いや寄生虫に対する不安から他の地域ではそのまま生で食べることは希ですが、琵琶湖の魚は刺身や洗いにして湖魚本来の繊細な味を楽しみます。これは美しく水温もさほど高くない琵琶湖の水の中で魚たちが良質のプランクトンを餌にしてじっくりと時間をかけて育ってきたからに他なりません。大昔から滋賀の人たちは琵琶湖の幸ともいえる湖魚の特性をよく理解し、その持ち味を最大限に引き出す食べ方を心得ていたのです」。
刺身で食べる湖魚の代表格は琵琶湖の固有種であるビワマスです。季節によっては海のトロにも引けを取らない脂ののった味が格別です。また同じく固有種で岩礁地帯に棲むイワトコナマズは泥臭さもなく、ナマズでは珍しく刺身として食べられてきました。湖魚の刺身の中でも特筆すべきはフナの子つけなますです。これはフナの刺身に卵をまぶしたもので食卓に上る機会の多い滋賀のごちそうです。
 イワトコナマズの刺身は、クセのない淡泊な味が特徴。 |
 湖魚の中でも味は最上ともいわれるビワマスの刺身。 旬は産卵期を迎える6、7月、脂ののった冬場も美味。 |

大きいけれど、小さい琵琶湖。
「湖魚料理のもうひとつの特徴は骨ごと食べる調理方法にあります。アユやウグイも小ぶりのものは背ごしといって骨ごと輪切りにしてドロスミソなどで食します。小魚は煮付けて頭ごと食べるし、コイやフナは骨のまま味噌でじっくり煮込む。また、魚を丸ごと食べるという点では滋賀の伝統食を代表するフナずしも共通しています」。
昔の人は、貴重なタンパク源をもたらす琵琶湖に大きな感謝を抱くとともに湖魚を愛し、大切に余すところなく食べる工夫を重ねてきたのです。堀越教授は講義の中でいつも学生に次のようなことを話します。
「琵琶湖は大きいけれど小さい。水量はおよそ275億トンといいますが、これは海に比べると水溜まりのようなものです。この小さな水域の限られた水産資源を滋賀の人たちは食べ尽くすことなく、つねに再生産を念頭に湖魚と向かい合って暮らしてきたのです。この先人たちの知恵と努力を学ぶことは現代に生きる私たちにとっても大きな意味をもつのです」。
この言葉を実践するように、いま琵琶湖の魚の新たな活用法が注目を集めています。それは、ブルーギルを使った魚醤づくりです。それぞれの立場で新たな試みに取り組む二人の活動をご紹介しましょう。
 琵琶湖で獲れたフナを塩と米を使って発酵させる 滋賀を代表する伝統食、フナずし。 |
 長年、滋賀の伝統食の調査・研究をつづける堀越教授。 |
ブルーギルの活用法を探って。
現在、琵琶湖に生息する外来魚のブルーギルはエリなどで年間約500トンが捕獲されていますが、その活用法は肥料や飼料となる魚粉などに限られています。しかし、魚粉以外の用途を見出すことによってその価値が高まる可能性もあるのです。滋賀県農業総合センター農業試験場の長谷俊治専門員は、以前からブルーギルの新たな活用法として魚醤づくりに着目していました。
魚醤とは”うおしょうゆ“とも呼ばれ、魚介類を原料として作った調味料の総称です。ベトナムのニョクマム、タイのナンプラ、国内では秋田のしょっつるや能登のいしるなどが有名です。一昨年の6月、長谷さんは醤油こうじを使った魚醤づくりをスタートしました。
「試験場に近い能登川町漁協でブルーギルを入手し、6月6日に漬け込みを開始。気温の上がる夏場から10月下旬までの140日間に発酵させました。分解力の強い醤油こうじの働きで魚体は骨と皮だけの状態にまで変化しました。一昨年はできるだけ手間をかけずに作る方法を試したかったので、20リットルのタンクに水洗いしただけのブルーギルと水を入れ、こうじ・食塩・砂糖・イーストを加えて漬け込みました」。こうじや食塩などの量を変えて9種類の魚醤を試作。 11月には瓶詰めしたものを、80人のモニターに配り、アンケート調査も実施しました。
「魚醤は日本人には馴染みの薄いものですが、評価は全般的に良かったと思います。実用化についてはまだ最終的な結論を出すまでには至っていませんが、昨年はスケールアップした際のデータを採るために200リットルのタンクで試験を行いました。長谷さんは、専門の農産加工の研究を進める一方で、将来的にブルーギルの魚醤が製品化されることを想定し、製造技術の構築に努めています。
 昨年の成果について説明する長谷さん。 |
 発酵がすすむブルーギルの魚体。 |
実習授業で作る新しい湖魚の味。
滋賀県立湖南農業高等学校で食品加工の授業を受け持つ野洲道広教諭も、長谷さんとほぼ同時期にブルーギルの魚醤づくりに取り組み始めました。そのきっかけは堀越教授との出会いでした。高校で教鞭をとる傍ら、1年間にわたる研修の機会を得た野洲さんは、週1回、堀越ゼミに参加し、魚醤づくりを研究しました。そして、堀越教授の助言によってブルーギルの魚醤づくりにチャレンジ。研究内容は高校での授業にも反映されました。
「3年生の実習にブルーギルの魚醤づくりを採り上げました。最初は魚醤を知らない生徒も多く、ヒレや骨の硬いブルーギルをさばくことにも苦労しました。とくに漬け込みは強烈な匂いを伴うので大騒ぎでした(笑)」。野洲さんと生徒たちは、頭と内臓を取り除いたり、ブツ切りにするなど、幾種類かの下ごしらえをしたものを漬け込みました。
「11月中旬に出来上がった時は、教室に歓声が響きましたね。ちゃんと醤油状になったことにみんな感激したようでした。魚醤は実習授業の中でも鍋料理に使用して全員で試食しました。味についての評価は上々でした。生徒たちは大変だった製造過程を体験していますから、完成の喜びは大きかったと思います」。
生徒たちの魚醤づくりは新聞や情報誌でも採り上げられ、地元の自然食レストランからも引き合いが来るなど、地域の話題として注目を集めています。
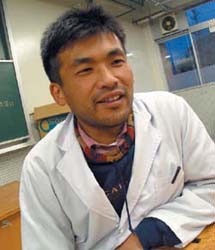 実習授業のようすを話す野洲さん。 |
 強烈な匂いにも負けず実習教室で漬け込みをする生徒たち。 |