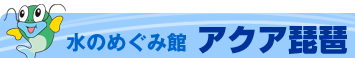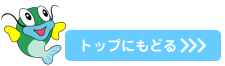再発見! 琵琶湖・淀川水辺の遺産
淀川のワンドに行こう。【大阪市旭区・城北ワンド群】
琵琶湖・淀川水系には、明治から大正時代にかけて、砂防や治水、利水のためにつくられたいくつもの土木施設がのこされています。
今号のビワズ通信では、そのひとつである淀川の水制を取り上げ、今日では生き物の貴重な生息地であるワンドとの関係をさぐるとともに、みなさまを水辺の遺産へと誘います。
 |
 大阪市旭区・城北ワンド群 |
ご存知ですか、ワンドの生い立ち。
淀川のワンドは、都心に近い距離にありながら、国の天然記念物のイタセンパラをはじめ、さまざまな動物や植物が見られる場所として有名です。しかし、この貴重な自然環境を誇るワンドが、どのようにして生まれたかについては、あまり知られていません。
幕末から明治にかけて、大阪はわが国の経済の中心地でした。そのため、明治時代に入ると外国船を受け容れるために大きな港をつくる必要に迫られました。また、大型の蒸気船が大阪湾から京都の伏見港まで上れるように1・5mの水深をもつ水路(低水路)を淀川につくらなければなりませんでした。この大役を任されたのが、当時、水に関わる土木技術が発達していたオランダより招かれた技師のデ・レーケでした。彼が、最新の土木技術を駆使してつくった低水路こそが淀川のワンドを生む、大きなきっかけとなったのです。
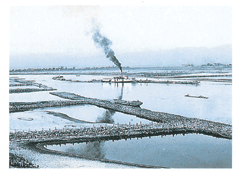 淀川低水路 枚方大橋下流(昭和14年頃) |
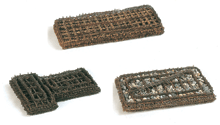 粗朶沈床工(そだちんしょうこう)の模型「淀川資料館蔵」 |
ヨーロッパの伝統工法「粗朶水制」とワンド。
淀川に大型の蒸気船が上れる水路をつくるためには、いくつかの課題がありました。まず、あまり急な水路にすると川の流れが速くなって船が思うように進めません。そこで、水路をくねくねと曲げて、ゆっくりとした流れをつくる必要がありました。ところが、川の水は上流から下流へとまっすぐ流れる性質を持っているので、曲がったところに水が当たると水路をこわしてしまいます。
これを防ぐためにデ・レーケは、岸から川の中央に向かって垂直に突き出した「水制」というものをつくり、水の流れをコントロールしたのです。
オランダなどでは何百年も前から、木の小枝や下草を編んで大きなマットレスをつくり、それを何層にも積み重ね、石といっしょに川床に沈める「粗朶(切り取った木の枝の意味)水制」が使われてきました。粗朶水制の大きな特長は、水制のすき間を水が通り抜けるとともに、小枝がたわんで水の力を受け止め、流れを優しく、穏やかに曲げることができることでした。ヨーロッパからもたらされた粗朶水制は、明治7年から、天満橋から伏見までの約40kmにわたる両岸に設けられました。そして、この時につくられた多くの粗朶水制が、長い歳月を経て、淀川のワンドの基となったのです。水制に囲まれたところは流れが穏やかで、水が浄化され、魚たちの格好のすみかや産卵の場となり、川によって運ばれた土や砂の上には木や草が生い茂り、野鳥が飛来するようになりました。水制工事は昭和20年代頃まで行われましたので、現在ある淀川のワンドが必ずしも同じようにしてできたとは限りませんが、ひとつの近代土木事業が、期せずして貴重な河川環境を形づくることになったのです。

明治18年の水制配置図 「写真提供:淀川資料館」
新しい生命に満ちるこの季節のワンド。
淀川のワンド群の中でも代表的な城北ワンドへは、JR大阪駅から大阪市営バスを利用して約30分で訪れることができます。市民から親水空間としても親しまれているワンドの見どころについて淀川環境委員会委員や淀川水系イタセンパラ研究会会長を務める小川力也さんにお話をうかがいました。

ワンドの自然を守るために活動を続ける小川さん。
「ゴールデンウィークの頃は、一年のうちでも魚がいちばん活発に活動する時期で産卵期にも当たりますから、うまくすれば水辺でタナゴの仲間などが産卵するようすを見ることができるかもしれません。また、水草のそばや浅い所では孵化した稚魚が群れをつくって泳ぐ姿を比較的簡単に眼にすることができるでしょう。ポイントは、水の中をしっかりと見つめることです。一匹見つかれば、目が慣れて次々に魚の姿をとらえることができるはずです。水中だけでなく、この季節のワンドは一週間ごとに陸上の景観も移り変わります。たとえば水辺のヨシも、今は冬枯れの色を残していますが、やがて下の方から新芽が伸びはじめ、みるみるうちに鮮やかな緑に衣替えをします。ここ城北ワンドは、淀川の中でも、とくに昔ながらの緑豊かな風景が楽しめるところです。人間によって作られた構築物に、川の流れという自然の力が働いてできた世界でも類を見ない河川環境をぜひ子どもたちといっしょに観察してください。」
 目で見るだけでなく、水に触れてみることも大切な自然観察。 ワンドへは、はき古した運動靴などを持参すると重宝です。 |
 小川さんとともに取材に同行していただいた淀川環境委員の 河合典彦さん。手にしているのは畳表にも使われるイグサ。 |
自然環境に配慮した新たな取り組み。
本来、ワンドは、川の水かさの増減によって、ある時は干上がり、ある時は本流に飲み込まれ、ワンド特有の環境を維持してきました。また、ワンドに棲む魚たちもそのような環境の変化に生活スタイルを合わせることで連綿と種を守り続けてきました。しかし、人間が洪水や渇水を防ぐために川の水を堰などでコントロールするようになってからは、生き物の生活スタイルと水かさの変化がそぐわなくなりました。例えば、コイやフナは雨が降って水位が上がるのを待ち、いっせいに産卵しますが、降雨の後に逆に水位が下がって産卵できなかったり、せっかく産卵しても急にワンドの水位が下がることで卵が干上がり、死んでしまうようなケースも起こっていました。そこで、国土交通省では、昨年より試行的に下流の淀川大堰の水位コントロールを生き物に配慮して行うことを始めました。

鮮やかな婚姻色をみせる
タイリクバラタナゴ
この取り組みについて小川さんは次のように評価されています。「まだ試行段階ですが、さまざまな調査を通じて、継続的に生物の生活への対応が検討されています。これは、従来の河川管理では考えられない画期的な試みだと思います。
さらに、この他にも産卵や稚魚の成育環境に適した浅い水辺をもつ小さなワンドを新設するなど、国土交通省の新しい取り組みは、着実に成果を上げていると考えられます」。
 子どもたちが水の中で見つけた2枚貝。左からイシガイ、 ドブガイ。観察が終わったら必ず見つけた場所に。 |
 右上:淀川の春の代表的な野草、カラスノエンドウ。 左下:ユーモラスな形状のオオイヌノフグリ。 |
◎ワンドを訪れるみなさまへ◎
天然記念物イタセンパラを守るためにご協力をお願いします。
- 産卵に必要な二枚貝を大切に。
- 水辺の稚魚を網などでとらないで。
- ブラックバスやブルーギルを放さないで。
- ゴミは捨てないで必ず持ち帰って。