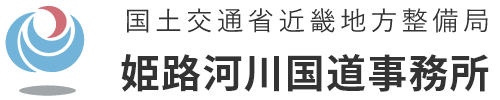加古川の歴史
播磨地域の中でもっとも大きい河川、加古川。
この加古川がもたらす肥えた土地のおかげもあって、播磨は早くから文明が開けた地域でもあった。それは加古川周辺エリアに数多くの埋蔵文化財や石造遺品、鶴林寺本堂・太子堂(589年、当時16歳の聖徳太子が仏教を広めるために建立したとされる)などの存在から窺い知ることができる。
豊かな水は、同時に人々に潤いと、とどまらない想いを与えるようになる。記録に残っているだけでも百回以上の洪水を起こしている。地域の発展を支えてきた加古川と、その流域で暮らす人たちが共生できるように、行わなければならないことは、決して少なくない。
この加古川がもたらす肥えた土地のおかげもあって、播磨は早くから文明が開けた地域でもあった。それは加古川周辺エリアに数多くの埋蔵文化財や石造遺品、鶴林寺本堂・太子堂(589年、当時16歳の聖徳太子が仏教を広めるために建立したとされる)などの存在から窺い知ることができる。
豊かな水は、同時に人々に潤いと、とどまらない想いを与えるようになる。記録に残っているだけでも百回以上の洪水を起こしている。地域の発展を支えてきた加古川と、その流域で暮らす人たちが共生できるように、行わなければならないことは、決して少なくない。
| 701年 大宝律令の頃 |
加古川に「舟」を常時配置した記録 野口村(現在の加古川市)の加古駅の西に水駅(渡船場)があり、舟が2隻から4隻常時配置されていた、という記録が残っている。既にこの頃から、加古川を利用して舟運が盛んに行われていたようである。 |
| 1225年 嘉禄元年 |
大洪水で国包村が流出 大洪水のため、当時の国包村の屋敷や田畑は残らず流出。一面の河原となった。住民の一部は出屋敷に移り、また別の一部は井の尻と川を隔てて東西に住むようになった。このことから推測すると、洪水と同時に川の流れが一部変わったようである。 |
| 1267年 文永4年 |
鎌倉時代中期「かこがわ」という名前が定着 民部卿為家の歌合に詠んだ歌の中に「かこ河」の名前で加古川が登場。「旅人の 駒うちわたず むさし鎧 たたなそかへる かこの河なみ」このことから、鎌倉時代の中期には「かこがわ」の名前が定着していたことがわかる。 |
| 1585年 天正13年頃 |
播磨・高砂百軒蔵の始まり 加古川流域より年貢米を運び込むため、豊臣秀吉が木下定家に高砂の川岸に米倉を建てさせた。これが播磨・高砂百軒蔵の始まり。百軒蔵が完成したのは姫路五十二万石、池田輝政の時代。池田輝政は、百軒蔵に大阪の堂島に送る東播磨の年貢米を収納した。 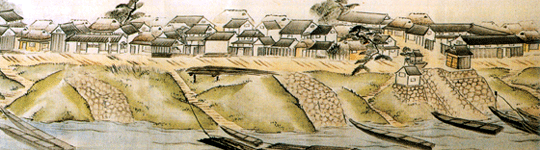 <国包浜実況図> 年次:嘉永(1848~1853)畑東助氏所蔵 |
| 1655年 明暦元年 |
姫路城城主榊原が築堤工事実施 姫路城主・榊原忠次の築堤計画着工(加古川市東神吉町升田から、米田町船頭に至る堤防)。庄屋が人足を出し合い工事を進行。昼夜を問わず工事を続けたため、1ヶ月余りで堤は完成。工事に要した人数は、延べ36万人に及んだ。 |
| 1756年 宝暦6年 |
国包出身の長浜屋新六郎が、人々や牛馬を水害から救うという目的で築山を築く。そこに植えられたのが「国包の榎・椋の樹」、そして、人々が感謝の気持ちと安全への祈りを込めて築山神社を建てた。 |
|
1878年 ≀ 1910年明治43年頃 |
樹木の伐採により山崩れ・洪水が頻発 廃藩後、野林の払い下げが行われたことにより、樹木が自由伐採され、山崩れと洪水がたびたび起こるようになった。そのため堤防の修理、流民の救済が年中行事のようになる。周辺の住人は、一日たりとも安らかに過ごすことができなかったという。 |
| 1918年 大正7年頃 |
何度も架橋が流されたために鉄橋を架設。その後加古川改修工事に着手 江戸時代から何度も架橋を作っては水害で被害をうけ、明治には大工事を行い、加古川橋を完成させるが、大洪水が重なり流失してしまう。そこで県は、大正2年に強固な鉄橋を架設、その後大正7年に加古川改修工事に着手し、昭和8年に一応の完成を見る。 |
| 1943年 昭和18年頃 |
度重なる出水により難航した三ケ村井堰工事が竣工 度重なる出水により難行した三ケ村井堰が竣工。昭和15年7月1日に工事に着工したが、出水が続き工事は進まなかった。翌16年には春から秋にかけて出水9回、仮締切の決潰5回、その度に焚出しをして昼夜兼行で井堰を支え、昭和17年には2回の洪水にもその経験をいかして危機を乗り越え、ついに昭和18年5月に竣工した。 |
| 1947年 昭和22年頃 |
現在の加古川堰堤竣工 現在の加古川堰堤竣工。河水統制事業による、取水施設は加古川堰堤と呼ばれ、昭和13年3月1日に起工している。そして終戦後、昭和22年5月31日に竣工した。現在の一般国道2号加古川バイパスより下流側に、また山陽本線から上流側にみられる鉄筋コンクリートの半可動堰がそれである。 |
| 1964年 昭和39年 |
河川法に利水が加わる 新河川法の改正にともない、治水・利水の体系的な制度の整備を目指し、水系一貫管理制度の導入と利水関係規定の整備を進める。  <1965年(昭和40年)の水害>
 <1974年(昭和49年)7月 台風8号の水害>  <1983年(昭和58年)9月 台風10号の水害> |
| 1967年 昭和42年 |
国の管理へ 洪水への対応と播磨工業地域の水需要の拡大に伴い、加古川は国の管理へ移管。 |
| 1980年 昭和55年 |
加古川大堰事業に着手 加古川大堰事業に着手する。加古川大堰の建設事業は、洪水の安全な流下を図り、下流部の既得用水の補給と河川維持用水の確保、さらに新規水道用水の開発によって、加古川市の逼迫する水需要に対処することを目的としていた。昭和63年度に完成。昭和62年4月から試験湛水を行い、平成元年に本格的な運用に入っている。 |
| 1997年 平成9年 |
河川法に環境が加わる 社会環境の変化により新河川法が改正され、治水・利水の役割を担うだけではなく多様な生物の生息・生育環境として捉え、地域の風土・文化を形成する個性ある川づくりを進める。 |
| 2004年 平成16年 |
平成16年10月20日に上陸した台風23号は、加古川流域で流域平均2日雨量225mm(国包上流域)の降雨をもたらし、国管理区間周辺では浸水面積537ha、浸水家屋516戸に及ぶ甚大な被害が発生した。国管理区間においては台風23号と同規模の洪水があった場合でも、再び同じ被害を繰り返さないために緊急的かつ集中的な加古川の河川改修を実施している。
 <2004年(平成16年)10月 台風23号の水害>
|