第1条
(主旨) |
建設工事事業者の再生資源の利用を促進するため、再生資源の利用の促進に関する法律(リサイクル法)第10条の規定に基づき、建設工事に伴い副次的に得られた土砂、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊ついて、工事現場での利用に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 |
第2条
(用語の定義) |
再生骨材等
コンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊から製造した骨材またはそれらに補足材料(骨材の品質を改善するために加える砕石、砂等をいう。)、 セメントもしくは石灰を加え、混合したもの
再生加熱アスファルト混合物
アスファルト・コンクリート塊から製造した骨材またはそれらに補足材料もしはアスファルトを加えたものを加熱し、混合したもの。
再生資源利用計画
建設工事に係る再生資源の利用に関する計画 |
第3条
(再生資源利用の原則) |
建設工事事業者は、請負契約の内容及び再生資源の利用に関する技術水準を踏まえるとともに、建設工事を施工する場所の状況及び再資源化施設の立地状況等を勘案し、再生資源を建設資材として用いる建設工事を施工することによりその利用を行う。 |
第4条
(建設発生土の利用) |
建設工事事業者は別表1建設発生土の区分及びその用途の右欄に掲げる区分に応じ、主として左欄の用途に利用するものとする。
また、建設発生土を利用する場合には、その品質等に関する技術的知見に基づいて、建設工事の施工又は完成後の工作物の機能に支障が生じないよう適切な施行を行うとともに、あらかじめ建設発生土の発生又は利用に係る必要な情報の収集又は提供に努めるものとする。 |
第5条
(コンクリート塊の利用) |
建設工事事業者は別表2コンクリート塊の再生骨材としての区分及び用途の右欄に掲げる区分に応じ、主として左欄の用途に利用するものとする。
建設工事事業者は、建設工事の施工又は完成後の工作物の機能に支障が生じないときは、区分及び用途にかかわらず、コンクリート塊を再生骨材等以外の建設資材として利用することができる。
建設工事事業者はコンクリート塊を利用する場合には、その品質等に関する技術的知見に基づいて、建設工事の施工又は完成後の工作物の機能に支障が生じないよう適切な施行を行う。 |
第6条
(アスファルト・コンクリート塊の利用) |
建設工事事業者はアスファルト・コンクリート塊を利用する場合において、再生骨材等として利用するにあたっては、別表3アスファルト・コンクリート塊の再生骨材としての区分及び用途の右欄に掲げる区分に応じ、主として左欄の用途に利用するものとする。
再生加熱アスファルト混合物として利用するにあたっては、別表4アスファルト・コンクリート塊の再生加熱アスファルト混合物としての区分及び用途の右欄に掲げる区分に応じ、左欄の用途に利用するものとする。
建設工事事業者は、建設工事の施工又は完成後の工作物の機能に支障が生じないときは、区分及び用途にかかわらず、アスファルト・コンクリート塊を再生骨材等以外の建設資材として利用することができる。
建設工事事業者はアスファルト・コンクリート塊を利用する場合には、その品質等に関する技術的知見に基づいて、建設工事の施工又は完成後の工作物の機能に支障が生じないよう適切な施行を行う。 |
第7条
(再生資源の現場内利用) |
建設工事事業者は、適切な施工方法の選択、資材置場の確保及び施工機械(再生資源を建設資材として利用するために必要な行う装置を含む。)の選定に配慮し、再生資源が発生した当該工事現場内での利用に努める。 |
第8条
(再生資源利用計画の作成等) |
発注者から直接工事を請け負った建設工事事業者は、下記の表に該当する建設資材を搬入する建設工事を施工する場合においてあらかじめ再生資源利用計画を作成するものとする。
| 項目 |
利用計画を作成
すべき規模 |
記載事項 |
| 土砂 |
1,000m3 以上 |
(1)建設資材の種類毎の利用量
(2)(1)のうち、再生資源の種類毎の利用量
(3)その他、再生資源の利用に関する事項 |
| 砕石 |
500t 以上 |
| 加熱アスファルト混合物 |
200t以上 |
建設工事事業者は、建設工事の完成後速やかに、再生資源利用計画の実施状況を記録するものとする。
建設工事事業者は、再生資源利用計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後1年間保存するものとする。 |
第9条
(管理体制の整備) |
建設工事事業者は、再生資源利用計画の作成等再生資源の利用に関する事務を適切に行うため、工事現場において責任者を置く等管理体制の整備を行うものとする。 |
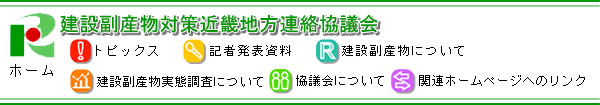
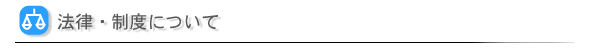
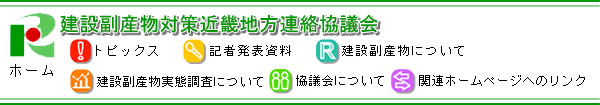
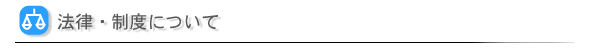

![]()