|
|
| ホーム > 大和川の歴史 > 付替え後の大和川と流域 |
| 付替え後の大和川と流域 |
| 大和川の付替え後、綿工業が発達してんで。 |
|
宝永元(1704)年に大和川の付替え工事が竣工した以後から、旧川筋などで新田開発が始まりました。新田では、主に綿が栽培されました。 |
| ● 関連ページ 「付替えがもたらしたもの」 |
| ■綿摘みのようす(『綿圃要務』より) | ■糸紡ぎのようす(『綿圃要務』より) |
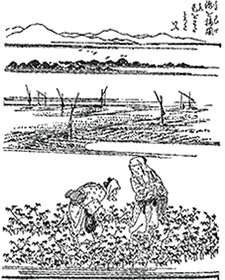
|
 |
| 急激に進む近代化で、大和川流域の産業も変わっていったんや。 |
明治の殖産興業(=明治時代前期の近代工業育成政策のこと)政策のひとつであった紡績産業において、明治10年ごろから大阪や奈良にも近代的な紡績工場ができました。河内では、綿実油(めんじつゆ)や菜種油の伝統から生まれた製油業においても近代的な工場ができました。 |
|
農作物の栽培種も変わっていきました。 |
| 戦後の高度経済成長期、大和川は・・・。 |
第二次世界大戦後、日本は復興による急速な経済発展と工場や宅地の開発が進みました。大和川流域でも急激に都市化を広げました。しかし、利便性がはかられる一方で、大和川は流域の排水路と化し河川環境が悪化しました。大和川の水は浅香山浄水場から取水し堺市の上水として利用されていましたが、昭和53(1978)年12月、水質悪化のため取水を止めました。 |
| 技術の進歩で、大和川の水害は減ったんや。 |
特に、戦後は度重なる台風などによる災害から流域を守るため、治水事業は堤防の嵩(かさ)上げや護岸(ごがん)強化の方法で行われてきました。 |
| 参考資料: | 『図説 大阪府の歴史』(河出書房新社) 『よみがえれ!大和川』(つげ書房新社) 『大和川物語』(大阪府柏原市役所) 『大和川流域のあゆみ 時の流景』(国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所) |