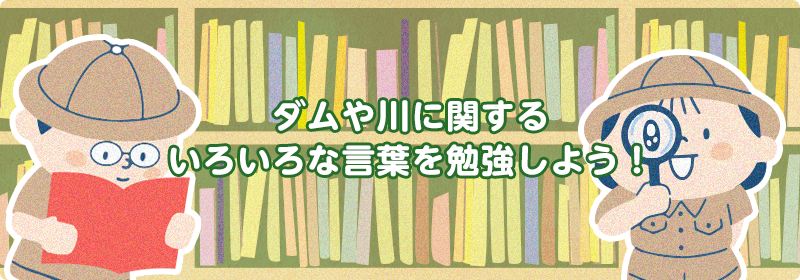
あ行
越水(えっすい)
川の水が洪水の時などに堤防の上をあふれて越えていくことです。H.W.L(エッチ・ダブル・エル)
High Water Level(ハイウォーターレベル)とは、計画高水位(けいかくこうすいい)又は氾濫危険水位(はんらんきけんすいい)と言うこともあります。
堤防などを造るときに目標としている川の水位のことで、この水位までの洪水は安全に流れるように計画します。
逆に、この水位をこえると氾濫するおそれがあるということにもなります。
か行
河川管理施設(かせんかんりしせつ)
洪水による被害を防いだり、川の水を利用できるようにしたり、川の環境を守ったりするために造られる施設です。ダム、堰、水門、堤防などがこれにあたりします。
河川激甚災害対策特別緊急事業(かせんげきじんさいがいたいさくとくべつきんきゅうじぎょう)
洪水などにより大きな被害(浸水家屋数 2,000戸以上、または流出(全壊)家屋数 50戸以上)を受けた地域において、およそ5年間で緊急的に工事を行い、同じような被害が起きないよう整備することです。
省略して、激特事業(げきとくじぎょう)と言うこともあります。
河川整備基本方針(かせんせいびきほんほうしん)
川の整備を行うために、将来の川の整備の考え方などを決めたものです。
河川整備計画(かせんせいびけいかく)
河川整備基本方針のうち、20~30年間で行う具体的な川の整備について決めたものです。
渇水(かっすい)
雨が少なく、川の水の量が減り、水を利用している人々が影響を受けるような状況のことです。
冠水(かんすい)
いつもは陸地(道路など)である場所が、洪水の時に水に浸かることを指します。
魚道(ぎょどう)
堰などで、魚が川を上ったり降りたりできないところに造られる魚の通り道のことです。
決壊(けっかい)
洪水が堤防を越えたり、堤防にしみこんだりして堤防が壊れることです。
さ行
砂州(さす)
川の流れによって砂が運ばれ、流れの弱くなった場所にたまってできたものです。
捷水路(しょうすいろ)
川の曲がりくねった場所をまっすぐにして、洪水を安全に流すために作った水路のことです。
浸水想定区域(しんすいそうていくいき)
洪水で氾濫が起きた場合に、どのあたりまで浸水するのかという範囲を示したものです。
水利権(すいりけん)
川から水を利用する権利のことです。
占用(せんよう)
ある決まった目的のために、必要な範囲で川の敷地を使うことをいい、川を管理する人の許可が必要となります。
堰(せき)
農業、工業、水道などに使う水を川から取るために、川を横ぎって造られる施設のことです。
た行
谷底低地(たにぞこていち)
山や台地を流れるゆるやかな谷川に、やわらかい土などが堆積してできた地形です。
治水(ちすい)
人の命や家、田畑などを洪水から守るために、川に堤防やダムを造り被害を防ぐことです。
治水安全度(ちすいあんぜんど)
洪水の氾濫が起こらない程度をいいます。
堤外地(ていがいち)・堤内地(ていないち)
堤外地とは、堤防からみて川の流れている側の土地をいいます。その反対に、人が住んでいる所など堤防で守られている側の土地を堤内地といいます。
堤防(ていぼう)
洪水などで川の水が増えて、川から人の住んでいる所などに水が流れ込むのを防ぐために、土などを積み上げて造ったものです。土手。
特殊提(とくしゅてい)
市街地の中で、土で堤防を造る場所がない時などに、コンクリートなどで造る壁のような堤防のことです。
山や台地を流れるゆるやかな谷川に、やわらかい土などが堆積してできた地形です。
治水(ちすい)
人の命や家、田畑などを洪水から守るために、川に堤防やダムを造り被害を防ぐことです。
治水安全度(ちすいあんぜんど)
洪水の氾濫が起こらない程度をいいます。
堤外地(ていがいち)・堤内地(ていないち)
堤外地とは、堤防からみて川の流れている側の土地をいいます。その反対に、人が住んでいる所など堤防で守られている側の土地を堤内地といいます。
堤防(ていぼう)
洪水などで川の水が増えて、川から人の住んでいる所などに水が流れ込むのを防ぐために、土などを積み上げて造ったものです。土手。
特殊提(とくしゅてい)
市街地の中で、土で堤防を造る場所がない時などに、コンクリートなどで造る壁のような堤防のことです。
な
内水(ないすい)
川よりも堤内地の土地の高さが低いため、堤内地側の水が自然に流れずに、たまってしまう水のことです。
川よりも堤内地の土地の高さが低いため、堤内地側の水が自然に流れずに、たまってしまう水のことです。
は
排水機場(はいすいきじょう)
洪水の時に水門などを閉じてしまうと堤内地側に降った雨水が川へ出ていかないので、この水をポンプによって川へくみ出す施設のことです。
ハザードマップ(はざーどまっぷ)
もしもの洪水の時に、みなさんが安全に避難できるように、浸水する水の深さや避難する場所などを示した地図です。
氾濫(はんらん)
洪水で増水した川の水が堤防をこえて農地、市街地などへ流れ出すことです。
不法投棄(ふほうとうき)
決められた場所以外にゴミなどを捨てることです。
洪水の時に水門などを閉じてしまうと堤内地側に降った雨水が川へ出ていかないので、この水をポンプによって川へくみ出す施設のことです。
ハザードマップ(はざーどまっぷ)
もしもの洪水の時に、みなさんが安全に避難できるように、浸水する水の深さや避難する場所などを示した地図です。
氾濫(はんらん)
洪水で増水した川の水が堤防をこえて農地、市街地などへ流れ出すことです。
不法投棄(ふほうとうき)
決められた場所以外にゴミなどを捨てることです。
ま
水裏部(みずうらぶ)
水の流れが弱く、土や砂がたまりやすい場所のことです。
水の流れが弱く、土や砂がたまりやすい場所のことです。
ら
利水(りすい)
生活、農業、工業などのために水を利用することです。
利水者(りすいしゃ)
生活、農業、工業のために水を利用する権利を持っている人のことです。
流域(りゅういき)
降った雨や雪がその川に集まる区域のことです。
流量(りゅうりょう)
ある場所を流れる1秒あたりの水の量です。単位はm3/s(りっぽうめーとるまいびょう)で表されます。
生活、農業、工業などのために水を利用することです。
利水者(りすいしゃ)
生活、農業、工業のために水を利用する権利を持っている人のことです。
流域(りゅういき)
降った雨や雪がその川に集まる区域のことです。
流量(りゅうりょう)
ある場所を流れる1秒あたりの水の量です。単位はm3/s(りっぽうめーとるまいびょう)で表されます。
川について
山などの川の源のほうから上流(じょうりゅう)、海に向かって下流(かりゅう)と言います。ふつう上流から下流に向かって右側の岸を右岸(うがん)、左側を左岸(さがん)と呼びます。
洪水(こうずい)
大雨や雪どけなどで、川の水が急に増えることです。また、川から氾濫することも言います。
堤防(ていぼう)
洪水などで川の水が増えて、川から人の住んでいる所などに水が流れ込むのを防ぐために、土などを積み上げて造ったものです。土手。
護岸(ごがん)
川岸や堤防などをコンクリートや石で強くして、洪水などから守るものです。
洪水(こうずい)
大雨や雪どけなどで、川の水が急に増えることです。また、川から氾濫することも言います。
堤防(ていぼう)
洪水などで川の水が増えて、川から人の住んでいる所などに水が流れ込むのを防ぐために、土などを積み上げて造ったものです。土手。
護岸(ごがん)
川岸や堤防などをコンクリートや石で強くして、洪水などから守るものです。
ダムについて
治水・利水・発電などのために、川の流れをせき止めて造るものです。使われている材料からコンクリートダムやフィルダム、造り方から重力式ダムやアーチダムなどに分けられます。
治水(ちすい)
人の命や家、田畑などを洪水から守るために、川に堤防やダムを造り被害を防ぐことです。
利水(りすい)
生活するための水道水や、農業や工業をするために水を使うことです。
発電(はつでん)
ダムにためた水を高いところから落とし、水の勢いを使って電気をつくることです。
「コンクリートダム」と「フィルダム」
コンクリートダムは、その名のとおりコンクリートでできています。コンクリートは、セメント、水、砂、砂利などから造られます。フィルダムは、土と岩から造られます。
重力式コンクリートダム
貯水池からの水の力を、ダムの重さで支えています。横から見ると、三角形の形をしています。
アーチ式コンクリートダム
貯水池からの水の力を、ダムの両側や底の地盤に伝えて支えています。重力式コンクリートダムに比べて、壁の厚さが大変薄く、上から見るとアーチ(円弧)の形をしています。
治水(ちすい)
人の命や家、田畑などを洪水から守るために、川に堤防やダムを造り被害を防ぐことです。
利水(りすい)
生活するための水道水や、農業や工業をするために水を使うことです。
発電(はつでん)
ダムにためた水を高いところから落とし、水の勢いを使って電気をつくることです。
「コンクリートダム」と「フィルダム」
コンクリートダムは、その名のとおりコンクリートでできています。コンクリートは、セメント、水、砂、砂利などから造られます。フィルダムは、土と岩から造られます。
重力式コンクリートダム
貯水池からの水の力を、ダムの重さで支えています。横から見ると、三角形の形をしています。
アーチ式コンクリートダム
貯水池からの水の力を、ダムの両側や底の地盤に伝えて支えています。重力式コンクリートダムに比べて、壁の厚さが大変薄く、上から見るとアーチ(円弧)の形をしています。