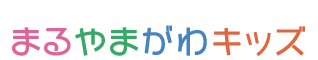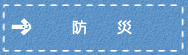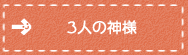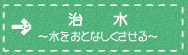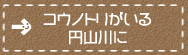国土交通省近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 まるやまがわキッズ
本文へ 文字サイズ
【江戸時代の年表】【明治・大正時代の年表】【昭和時代の年表】【平成時代の年表】
記録に残っている江戸時代の水害
※年表の注意:記録によって、きちんと数字がのこっているものや、おおまかに書いたものなど、いろんな書き方があります。くわしく書かれていないから大きな被害ではなかった、とは言えません。
| 天正1年(1573)3月 | 円山川・六方川が氾濫、豊岡東部で大洪水、六方平野の収穫皆無で農民困窮。城崎では大きな家がならぶ商業のまち「灘千軒(なだせんげん)」が一夜ですべて流された |
|---|---|
| 天正2年(1574) | 多くの川ではんらん |
| 慶長11年(1606)6月 | 多くの家が流された(天児の家、高柳の家流される) |
| 慶長13年(1608)4月 | 広い地域で洪水(近畿諸国に風雨洪水) |
| 慶長15年(1610) | 大洪水で円山川の流れが変わった(もとは竹田城の下を流れていた) |
| 寛文12年(1672)7月 | 大雨で洪水、農作物が育たなかった |
| 延宝1年(1673)5月 | 大雨で洪水 |
| 延宝2年(1674)8月 | 広い地域で大洪水(翌年春に多くの人が飢え死にした) |
| 延宝3年(1675) | 洪水 八鹿村で家15軒が流された |
| 延宝7年(1679)5月 | 洪水 |
| 延宝8年(1680)5月26日~6月7日 | 3回洪水 |
| 延宝8年(1680)10月 | 大雪で麦がほとんどくさった |
| 天和1年(1681) | 数回洪水があった。農作物が育たなかった |
| 貞享3年(1686)7月 | 大風雨、洪水で農作物が育たなかった |
| 貞享3年(1686)9月 | 八鹿村で家1軒が流された |
| 元禄8年(1697) | 数回洪水があった。農作物が育たなかった |
| 元禄9年(1698) | 全国にききん |
| 元禄14年(1701)8月 | 大風雨 |
| 享保7年(1722)6月 | 洪水 家150軒がこわされ、22軒が流された。死者8人 |
| 享保14年(1729) | 洪水 被害多かった |
| 享保16年(1731) | 何回も洪水があった |
| 延享3年(1746)8月 | 大風雨 家385軒がこわされ、死者2人 |
| 寛延1年(1748)6月 | 大風雨 出石で洪水 |
| 寛延1年(1748)9月 | 大風雨 出石で家106軒がこわされ、死者8人 |
| 寬延2年(1749)7月 | 但馬、丹後、播磨で大風雨により洪水、死者1000人以上 豊岡では家138軒がこわされ、死者2人 出石でも大洪水で田畑がぜんめつ。死者3人、牛2頭が死んだ |
| 寛延3年(1750)6月 | 大雨、洪水で家11軒が流され、43軒がこわされた。死者2人 |
| 寛延3年(1750)7月 | 伊佐村(八鹿町)で3尺(90cm)水につかった |
| 宝暦6年(1756)9月 | 風雨、洪水で出石で家4軒がこわされた |
| 宝暦7年(1757)8月 | 大風雨、洪水で死者3人、牛2頭が死んだ |
| 宝暦8年(1758)8月 | 大雨、洪水 |
| 宝暦9年(1759)7月 | 洪水 |
| 宝暦12年(1762)秋 | 大洪水 多くの村で大きな被害があった |
| 明和5年(1768)7月 | 四国、近畿に大風雨、洪水(翌年農作物はほとんどしゅうかくできなかった) |
| 安永1年(1772)8月 | 伊佐村(八鹿)洪水、秋にも大洪水 |
| 安永2年(1773) | 疫病流行、円山川は5月から洪水13回 |
| 安永5年(1776)7月 | 円山川大洪水 ほかの川も増水。豊岡城の外堀でもある和久田堤がくずれそうになったが、農民が土のう積みを行って防いだ |
| 安永9年(1780) | 春先から但馬に冷たい雨が降りつづく。稲の植え付けができなかった 5月大洪水、奈佐川の堤防がくずれた |
| 天明3年(1783) | 6月から9月、日本の多くの地方で霜雨。大ききん |
| 天明4年(1784) | 水害、ききん、漁獲少なかった |
| 天明6年(1786)8月 | 出石洪水のため大橋一丈(3m)まで水が上がった ※全国的な天明のききんのなかでも、もっともひどかった |
| 寛政1年(1789)6月 | 大洪水 大きな被害があった |
| 寛政2年(1790)8月 | 大洪水 |
| 寛政7年(1795)閏8月 | 大洪水 豊岡の町中の家が床上まで水につかった |
| 寛政8年(1796)4月 | 但馬地方に暴雨風 家がこわされ、死者もでた |
| 享和2年(1802) | 多くの地方で洪水 |
| 文化1年(1804)7月 | 大雨 豊岡城下の北の守り・和久田堤防がくずれた。稲も大半が流された |
| 文化4年(1807)8月~9月 | 洪水20回 |
| 文化4年(1807)10月 | 出石城下洪水 |
| 文化5年(1808)6月 | 出石大風洪水 251の橋が流され、家70軒がこわされた。農作物のしゅうかくが少なかった |
| 文化8年(1811)5月 | 大風雨 洪水 |
| 文化9年(1812)7月 | 洪水 野田の堤防(縄手)がくずれた(切れた) |
| 文化9年(1812)8月 | 大雨 洪水 |
| 文化11年(1814) | 全国にききん |
| 文化13年(1816) | 8月に2回(8月と閏8月)出石領内洪水 家55軒が流された。出石で135の橋が流され、死者1人 |
| 文政2年(1819)5月 | 大雨 洪水 死者1人 |
| 文政7年(1824)2月 | 大雨 洪水 |
| 文政8年(1825)8月 | 10年来の大洪水 田畑すべてが水につかった |
| 天保1年(1830)8月 | 洪水 |
| 天保6年(1835)5月 | 大雨洪水 和久田堤防がくずれた。農作物が実らず諸国大ききん |
| 天保7年(1836) | 洪水 |
| 天保8年(1837) | 「とり年の大水」宿南(八鹿町)に洪水。諸国大ききん |
| 弘化3年(1846)3月 | 洪水 農作物のしゅうかくが少なく、翌47年大ききん |
| 嘉永1年(1848) | 洪水 |
| 嘉永3年(1850)9月 | 大洪水 出石は3.6m水につかった。出石城がこわされた。多くの家と出石のほとんどの橋が流され、田畑の被害もものすごく大きかった。豊岡と出石、日高で死者37人(「今までにない大水害」と記録あり) |
| 嘉永5~6年(1852~3) | 洪水 不作つづく |
| 安政1年(1854)11月 | 夜大暴風雨 |
| 安政2年(1855) | 数回の洪水 |
| 万延1年(1860) | 洪水 |
| 元治1年(1864)8月 | 大洪水 ものすごく多くの家が水につかった |
| 元治1年(1864)12月 | 大雨 円山川の水位約5m。堤防がくずれそうになった |
| 元治2年(1865)8月 | 大洪水 円山川の水位7~8m。あちこちで堤防がくずれて、豊岡盆地は湖のようになった。多くの家が流され、3000戸以上が水につかった |
| 慶応2年1866年8月 | 「寅年の大洪水」堤防がくずれた。多くの家が流され、出石川の周辺は1週間水につかった |
記録に残っている明治時代の水害
※年表の注意:記録によって、きちんと数字がのこっているものや、おおまかに書いたものなど、いろんな書き方があります。くわしく書かれていないから大きな被害ではなかった、とは言えません。
| 明治3年(1870)9月 | 大風雨により夜中に洪水(18日) |
|---|---|
| 明治4年(1871)5月 | 洪水 農作物のしゅうかくのうち4割が被害を受けた |
| 明治18年(1885) | 大洪水 慶応2年の水害よりもひどかった |
| 明治25年(1892) | 洪水 |
| 明治26年(1893) | 洪水 |
| 明治27年(1894) | 洪水 |
| 明治28年(1895) | 洪水 |
| 明治29年(1896) | 大洪水 大きな被害 |
| 明治30年(1897) | 洪水 |
| 明治31年(1898) | 洪水 |
| 明治32年(1899) | 洪水 |
| 明治33年(1900) | 洪水 |
| 明治35年(1902) | 洪水 |
| 明治36年(1903) | 洪水 |
| 明治37年(1904) | 洪水 |
| 明治38年(1905) | 洪水 |
| 明治40年(1907)8月 | 台風 3万戸被害 |
| 明治41年(1908) | 洪水 |
| 明治43年(1910) | 洪水 |
| 明治44年(1911) | 洪水 |
記録に残っている大正時代の水害
※年表の注意:記録によって、きちんと数字がのこっているものや、おおまかに書いたものなど、いろんな書き方があります。くわしく書かれていないから大きな被害ではなかった、とは言えません。
| 大正1年(1912)9月 | 台風 大洪水 家610戸がこわされた。死傷者29人 |
|---|---|
| 大正2年(1913) | 洪水 |
| 大正4年(1915) | 洪水 |
| 大正5年(1916) | 洪水 |
| 大正6年(1917) | 洪水 出石で死者2人 |
| 大正7年(1918) | 洪水 出石で堤防がくずれ128戸が水につかった。2つの橋が流された。死傷者34人 |
| 大正8年(1919) | 出石で洪水 |
| 大正10年(1921) | 大洪水 但馬全体で3000haが水につかった。約6m(20尺)の高さまで水につかったところもあった |
| 大正14年(1925) | 北但大震災 |
昭和時代の水害
※年表の注意:記録によって、きちんと数字がのこっているものや、おおまかに書いたものなど、いろんな書き方があります。くわしく書かれていないから大きな被害ではなかった、とは言えません。
| 昭和2年(1927)3月 | 北丹後烈震 橋がくずれた |
|---|---|
| 昭和4年(1929)8月 | 豪雨 城崎で13戸の家が一部こわされた |
| 昭和5年(1930)8月 | 豪雨 出石で堤防がくずれ、まちが水につかった。道路もくずれ、6つの橋が流された |
| 昭和9(1934)年1月 | 豪雪 死者24人 |
| 昭和9年(1934) | 室戸台風 城崎で家が200戸こわされ、3000戸が水につかった |
| 昭和11年(1936)7月 | 八鹿で八木川から水があふれた。死者1人 |
| 昭和13年(1938)9月 | 洪水 養父で家70戸がこわされ、500戸が水につかった。死傷者5人 |
| 昭和17年(1942)9月 | 洪水 出石で家22戸が流された |
| 昭和20年(1945)9月 | 枕崎台風 但馬地方中心に死者19人 |
| 昭和20年(1945)10月 | 阿久根台風 但馬地方と播磨中心に死傷者35人 |
| 昭和25年(1950)9月 | ジェーン台風 兵庫県の死者41人 |
| 昭和26年(1951)10月 | ルース台風 風台風で家や道路(公共土木施設)などがこわされた |
| 昭和28年(1953)6月 | 台風2号 和田山と養父で死者2人 |
| 昭和28年(1953)7月 | 豪雨 多くの家が水につかった |
| 昭和28年(1953)9月 | 台風13号 城崎で大きな被害があった |
| 昭和29年(1954)9月 | 台風15号 兵庫県で死者7人 |
| 昭和32年(1957)6月 | 台風5号 |
| 昭和34年(1959)9月 | 伊勢湾台風 16ha、約17000戸の家が水につかった |
| 昭和36年(1961)9月 | 第二室戸台風 2.3ha、約2000戸の家が水につかった |
| 昭和39年(1964)7月 | 豪雨 |
| 昭和40年(1965)7月 | 豪雨 |
| 昭和40年(1965)9月 | 台風23号・秋雨前線・台風24号 約7800戸の家が水につかった |
| 昭和41年(1966) | 台風24号 城崎町で家84戸が水につかった |
| 昭和44年(1969)6月 | 豪雨 |
| 昭和45年(1970)6月 | 豪雨 |
| 昭和45年(1970)8月 | 台風9号 |
| 昭和46年(1971)8月 | 台風23号 |
| 昭和46年(1971)9月 | 大雨と異常潮位 |
| 昭和47年(1972)7月 | 梅雨前線と台風6号 7.7ha、約750戸の家が水につかった |
| 昭和47年(1972)9月 | 台風20号 |
| 昭和49年(1974)9月 | 台風18号 |
| 昭和51年(1976)9月 | 台風17号と秋雨前線 2.1ha、約3000戸の家が水につかった |
| 昭和52年(1977)7月 | 豪雨 和田山で床下浸水 |
| 昭和52年(1977)11月 | 大雨 |
| 昭和53年(1978)9月 | 台風18号 家々が水につかった |
| 昭和54年(1979)10月 | 台風20号 円山川の水位が6.74mまであがり、約1000戸の家が水につかった |
| 昭和55年(1980)10月 | 強風波浪と異常潮位 家々が水につかった |
| 昭和56年(1981)10月 | 大雨 生野などで家々が水につかった |
| 昭和57年(1982)8月 | 台風10号 家々が水につかった。 兵庫県で死者2人 |
| 昭和58年(1983)9月 | 台風10号 |
| 昭和61年(1986)7月 | 大雨 |
| 昭和62年(1987)10月 | 台風19号 |
| 昭和63年(1988)8月 | 大雨 |
| 昭和63年(1988)9月 | 大雨 家々が水につかった |
平成の水害
※年表の注意:記録によって、きちんと数字がのこっているものや、おおまかに書いたものなど、いろんな書き方があります。くわしく書かれていないから大きな被害ではなかった、とは言えません。
| 平成2年(1990)9月 | 台風19号 約2ha、家約2500戸が水につかった |
|---|---|
| 平成2年(1990)11月 | 台風28号 出石で道路がこわされた |
| 平成3年(1991)9月 | 台風19号 田畑や港に被害 |
| 平成16年(2004)10月 | 台風23号 約4083ha、家 約8000戸が水につかり、4000軒以上がこわされた。死者7人、負傷者51人 |
| 平成21年(2009)8月 | 台風9号 346ha、家77戸が水につかった |
| 平成25年(2013)9月 | 台風18号 17.5ha、1戸が水につかった |