大和川の生き物
大和川は奈良県の笠置山地を源とし、生駒山地と金剛山地の間を通って大阪平野に流れる全長約68キロメートル、178本の支川を保有する水系です。大和川流域にはいろいろな生物がみられ、調査区間では魚63種、植物653種、鳥128種、小動物類(両生類・爬虫類・哺乳類)28種、陸上昆虫類等(クモ類含む)1584種、底生動物266種の合計2722種の様々な動植物が確認されています。(平成27年までの河川水辺の国勢調査)。
全体の自然環境区間図
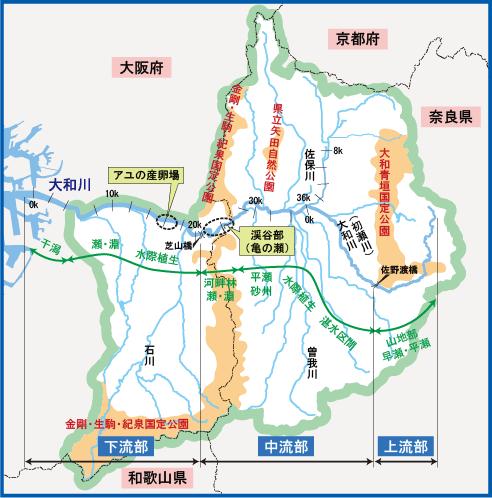
河川の区分と自然環境
下流部:平瀬が多いが早瀬にも見られ、河口では干潟が形成される。
中流部:平瀬や堰による湛水区間の緩やかな流れが多い平地部と、早瀬、淵が連続する渓谷部(亀の瀬地区)で構成される。
上流部:照葉樹林、スギ・ヒノキ植林等で構成される山地部であり早瀬、平瀬が多く、ツルヨシ等の水際植生が見られる。
中流部:平瀬や堰による湛水区間の緩やかな流れが多い平地部と、早瀬、淵が連続する渓谷部(亀の瀬地区)で構成される。
上流部:照葉樹林、スギ・ヒノキ植林等で構成される山地部であり早瀬、平瀬が多く、ツルヨシ等の水際植生が見られる。
大和川の動植物(下流部)
河口区間(~4.4km)
← 左右にスクロールできます →
| 区分 | 下流部 | 中流部 | 上流部 | |
|---|---|---|---|---|
| 区間 | 河口部 | 河口部以外 | 芝山~佐野渡橋 | 佐野渡橋~源流 |
| 地形 | 平地 | 平地 | 山地・平地 | 山地 |
| 特性 | 干潟・感潮域 砂州 |
瀬、淵、砂州 | 河畔林、早瀬 平瀬、砂州 |
源流・河畔林 早瀬、平瀬 |
| 河床材料 | 砂主体 | 砂主体 | 岩、砂、礫 | 岩、砂、礫 |
| 植物相 | セイカタヨシ | セイカタヨシ エノキ ヤナギ類 |
セイカタヨシ 河畔林(ムクノキ、エノキ、ヤナギ類、マダケ等) |
スギ、ヒノキ植林 照葉樹林、 ツルヨシ |
| 動物相 | ボラ メダカ カモ類 ユリカモメ コアジサシ ホシハジロ ウミネコ |
ギンブナ モツゴ カマツカ ヌマムツ ドンコ アユ |
オイカワ カマツカ ギンフナ モツゴ ヌマムツ ドジョウ メダカ カワラヒワ セッカ アオジ カモ類 ハマシギ |
カワムツ アカザ ドジョウ ドンコ カワニナ ゲンジボタル ヘイケホタル |
河口区間(~4.4km)
【現状】
- 広大な干潟が形成され、ユリカモメやウミネコ等の集団休息地となっています。
- 水面や水際ではカモ類やカモメ類が多く飛来し、ホシハジロの集団越冬地、コアジサシの集団採餌場となっています。
- 魚類ではボラ、メナダなどの汽水性魚類が多く生息しています。


下流区間(4.4キロ~20.8キロ)
【現状】
- 大阪平野の平地部を流れ、平瀬の多い水域で、瀬と淵もみられ、ギンブナ、モツゴ等の他、カマツカ、ヌマムツ、ドンコ等の重要種が生息しています。
- 早瀬ではアユの産卵場が確認されています。
- 河川敷では、セイタカヨシ等の草本類にエノキやヤナギ類等の中高木林が混在した多様な植生がみられます。


大和川の動植物(中流・上流)
中流部(芝山橋20.8km~佐野渡橋50.8km)
【現状】
- 奈良盆地の平地部は、堰による湛水区間や平瀬、砂州の多い緩やかな流れとなっており、水際にはセイタカヨシ等の植生がみられ、オイカワ、ギンブナ等の他、カマツカ、ヌマムツ、ドジョウ、メダカ等の重要種が生息しています。
- 渓谷部(亀の瀬地区)では、早瀬と淵が連続し、オイカワ、キンブナ、モツゴ等が生息、水辺にはエノキ、ムクノキ、マダケ等からなる河畔林がみられます。
- 水際のヨシ帯では、カワラヒワ、セッカ、オオヨシキリ等が多く確認されている他、水面や水際では休息するカモ類、砂州ではハマシギの集団越冬地が確認されています。





上流部(佐野渡橋50.8km~源流)
【現状】
- 照葉樹林、スギ・ヒノキ植林等からなる山地部となっており、水際にはツルヨシ等の植生がみられます。
- 早瀬~平瀬が多く、カワムツ、ゲンジボタル、ヘイケボタル等の他、アカザ、ドジョウ、ドンコ、カワニナ等の重要種が生息しています。

